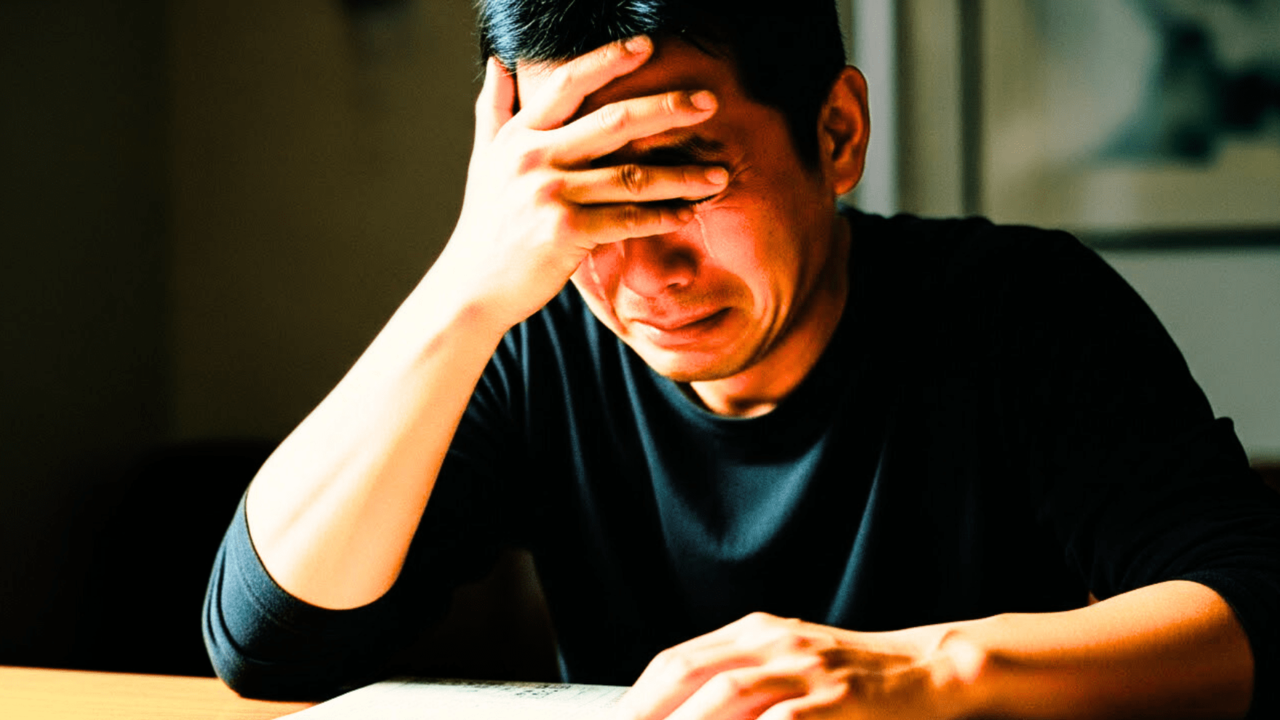治療の〝エビデンス〟とは?
臨床医学は経験的技術の集積であり、建築や土木における工学技術が伝統的な技であることに似ています。しかし、いかに「伝統ある治療」でも一歩間違えば「誤った伝統」に陥りかねません。私が医者になった昭和の終わり頃は、日本の整形外科学はまだ伝統医学にどっぷりつかっていました。
学会や論文でも「〝私の術式〟による腰痛治療の成功率は95%!」といった発表が散見されました。今から見ると驚くのは、成功・不成功の判断を医者が行っていた点です。つまり執刀医が「治った」と見なせば、〝すぐれた手術〟と報告されていたのです。
臨床医学では「三段論法」ならぬ「サンタ論法」という言葉があります。「やった、治った、よかった(これでいいのだ)」という「三つのた」だから〝サンタ〟です1。今にしてみるとトンデモな論理ですが、つい最近まで痛みの医療の分野ではしばしば見かけました。ただ、21世紀に入り、少なくとも臨床研究の分野では〝サンタ医学〟は〝EBM〟により放逐されました。
EBM(EvidenceBasedMedicine)とは「エビデンス(科学的証拠の意)に基づく医学」のこと⑵。エビデンスという言葉は、新型コロナウイルス感染症とともに一般にも一気に広まった感がありますが、臨床医学(治療学)におけるエビデンスとは「治療効果があるという科学的証拠」のことです。
すなわち「Xという病気にかかっている患者さんをふたつのグループに無作為に振り分けて、ひとつのグループには治療Aを行い、他のグループにはプラセボ=偽治療を行い、その結果、治療Aを受けた患者さんグループの方に病気がよくなる人が、〝確率的に有意〟に多かったならば、治療Aは病気Xに有効といえる証拠がある」という論法です。