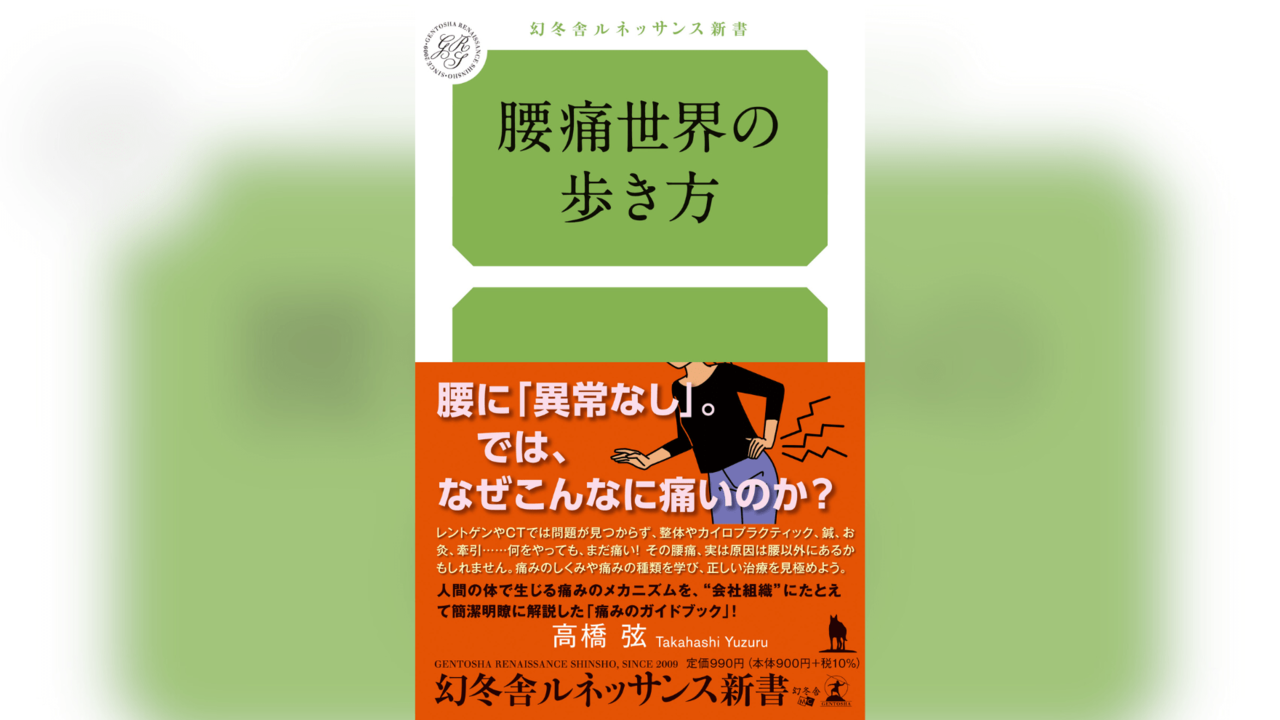【前回の記事を読む】「やった、治った、よかった(これでいいのだ)」の〝サンタ医学〟から〝EBM〟「エビデンス(科学的証拠の意)に基づく医学」へ
序章
治療の〝エビデンス〟とは?
たとえば本書ではこの先、腰痛の治療についてあれこれ〝講評〟していきますが、疼痛科学の事実に合わないからといって、その治療の価値を評価できるわけではありません。どのような治療であっても(〝思いつきの治療〟でも!)、RCTで証明されれば「エビデンスあり」となるのです。民間療法の「名人」の治療とて、例外ではありません。
しかし、さしものRCTにも限界はあります。RCTは2集団間における「集団としての差」を比較しますが、個々の患者さんにどの程度効いたかは評価していません。たとえば「効果のエビデンスなし」と判定された治療法であっても、その治療法によりよくなる人はたいてい少しはいるものです。
医者自身しばしば自嘲的に「臨床医学は玉石混淆」だと言いますが、〝玉治療〟もあなたには無価値かもしれず、〝石治療〟でも「ありがたい治療」になるかもしれないのです。
腰痛の場合は、さらなる「重大な問題」があります。腰痛とは、さまざまなタイプの腰痛をひっくるめた総称、すなわち〝総合的疾患概念〟であり、ひとつの病気として分析するには無理があるのです。理想的にはより細かく、個々の病態ごとの治療のエビデンスが検討されるべきなのですが、今のところそのような状況にはなっていません。
現在、医学のさまざまな分野においてEBMに基づいた「診療ガイドライン」がつくられており、腰痛分野でも「腰痛診療ガイドライン」(3)などが日本整形外科学会から発刊されています。一般の方には馴染みはないかもしれませんが、臨床医にとっては今やガイドラインは無視できない存在となっています1。
けれども、ガイドラインは臨床医学の世界において医師が遵守しなければならない〝憲法〟ではありません。ガイドラインはエビデンスが確認された治療を推奨しますが、エビデンスのない治療を否定しているわけではありません。たとえば、すでに多くの医者と患者さんに支持されている伝統的治療を、あらためてRCTの俎上に載せようと考える臨床医はほとんどいません2。
また、手術や救急救命治療など「1回限りの治療」に対してRCTを実施することは倫理的に困難です。こうしたことから、最新のガイドラインはRCT研究に基づく「エビデンスの強さ」だけでなく、編纂を手がけた「委員会による推奨度」も併記されるようになりました3。
以上、基礎医学と臨床医学、理論とエビデンスの位置付けと違いについて、何となくでもご理解いただけたでしょうか? 今日、腰痛に対してはさまざまな治療が行われており、そのすべてにエビデンスが提示されているわけではありません。
本書の後半でも「腰痛の治療」について個々に論評していますが、それはEBMに基づくものではなく、あくまで疼痛科学の知見に照らして各治療の位置付けを私なりに解釈し説明したものです。「腰痛の治療者」に関する記述は、完全に筆者の〝個人の感想〟(笑)です。その意味で「腰痛の治療者に関する研究」は絶無であり、先にあげた高野さんの本は貴重な〝体験報告〟といえるでしょう。
さあ、それでは痛みとは何かについて、いよいよお話を始めましょう。このうち、1章と2章は疼痛科学により明らかにされた「痛みのしくみ」についてのお話です。3章は痛みの医療を考えるうえでの重要な観点、「主観と客観」をめぐる話です。