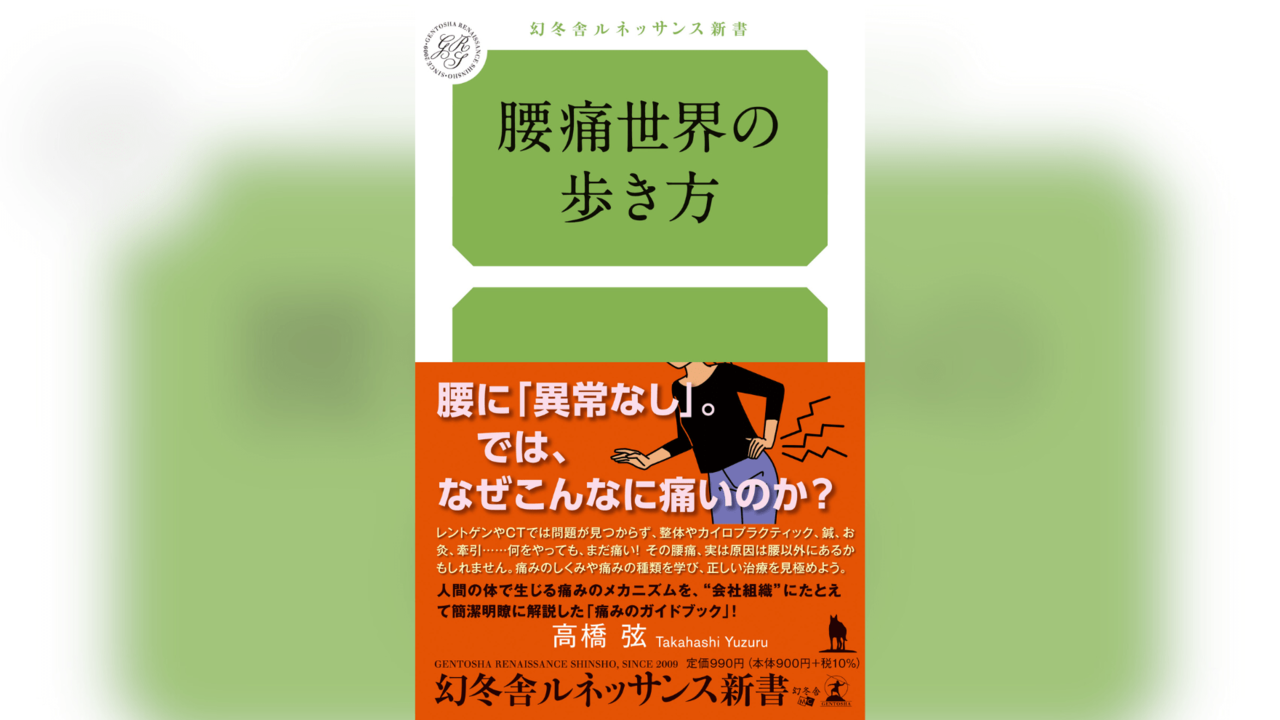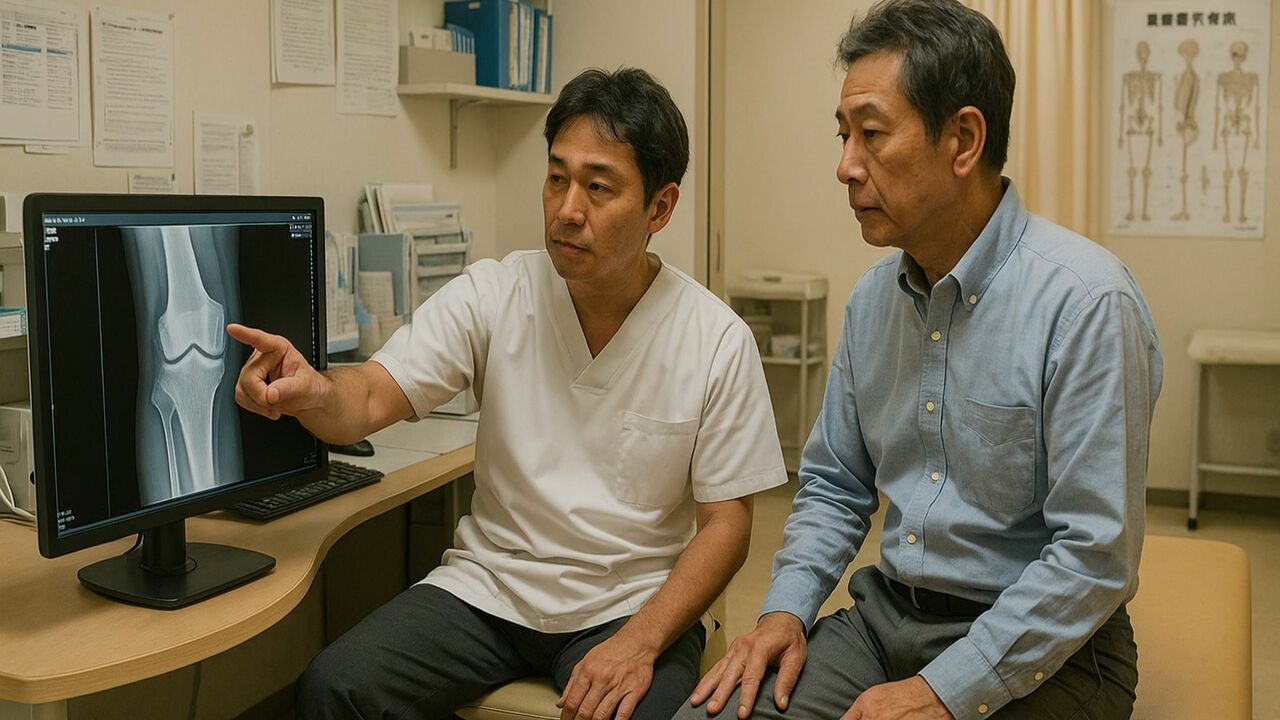【前回の記事を読む】どのような治療であってもRCTで証明されれば「エビデンスあり」!たとえば湿布や温熱療法のエビデンス(RCT研究)はない
第1章 痛みのしくみ
痛みとは? 〜専門家の定義〜
「痛み」を一度も体験したことがない人はいないでしょう。私たちはめまい1、吐き気、かゆみなど、さまざまな体の異変を体験しますが、そのなかでも痛みは医者にかかる動機となる、最も多い症状です。痛みは体のあらゆるところに現れます。整形外科医は頭から足先まですべての痛みを診ています2。
いきなり余談ですが、骨・筋・関節などを運動器といい、近年「整形外科」の診療科名を「運動器科」に変更しようという動きがあります。理由は、整形外科を美容外科や形成外科と間違える人が多いこと、一般には整形手術=美容手術の意味で使うことが多いからです。
さらに治療の実際としても、外科手術よりも薬物療法、理学療法を行うことが多いことも改名の動機です。ただ、残念ながら「運動器」という言葉自体がさほど広まっていないようで、また運動=体育・スポーツという一般的な解釈もあり、科名の変更は新たな誤解の元になるかもしれません。
整形外科医は「運動器の病気とケガ」を診る医者です。ちなみに私が所属している運動器の痛みを研究する学会は「日本運動器疼痛学会」といいます。頭部、胸部、腹部の疾患も多くは痛みを症状としますが、そうした病気では痛みの原因疾患そのものの研究が中心です。
一方、運動器慢性痛のなかには慢性腰痛に代表される慢性化の原因が不明のものも少なくなく、運動器慢性痛は疼痛学全体のなかでも重要な研究課題となっています。
そもそも痛みとは何でしょうか? 私たち人間は病気やケガをしたときに、どうして、どのようにして痛みを感じるのでしょうか?
痛みは病気やケガの徴候(しるし、サイン)だといわれますが、指にトゲが刺さっただけもすごく痛いのに、命に関わるはずのがんは進行してからでないと痛みを感じません。痛みは病気の発見や自己診断にあまり役立っていないようにも見えます。そもそも、痛いのは病気やケガをしている場所なのでしょか?
光は目で、音は耳で、それぞれとらえられているのは確かですが、それを知覚している3のは脳であることが古くから知られていました。それでは、体の痛みも脳がつくり出しているのでしょうか?
疼痛科学の研究により「痛みのしくみ」がわかってきました。結論をあっさり言えば、痛みもまた「脳でつくられたもの」なのです。
科学では、論じる事象をまず定義します。痛みはあまりにもありふれており、誰もが経験するために、長らくその定義はありませんでした。
本来は体の病気やケガにより生じる異常を表現する言葉だったのが、やがて「心の痛み」や、個人を超越した「社会の痛み」などの比喩的な表現も生まれ、近年はさらに「痛い人」「痛車(いたしゃ)」など、新たな表現も見受けられます。