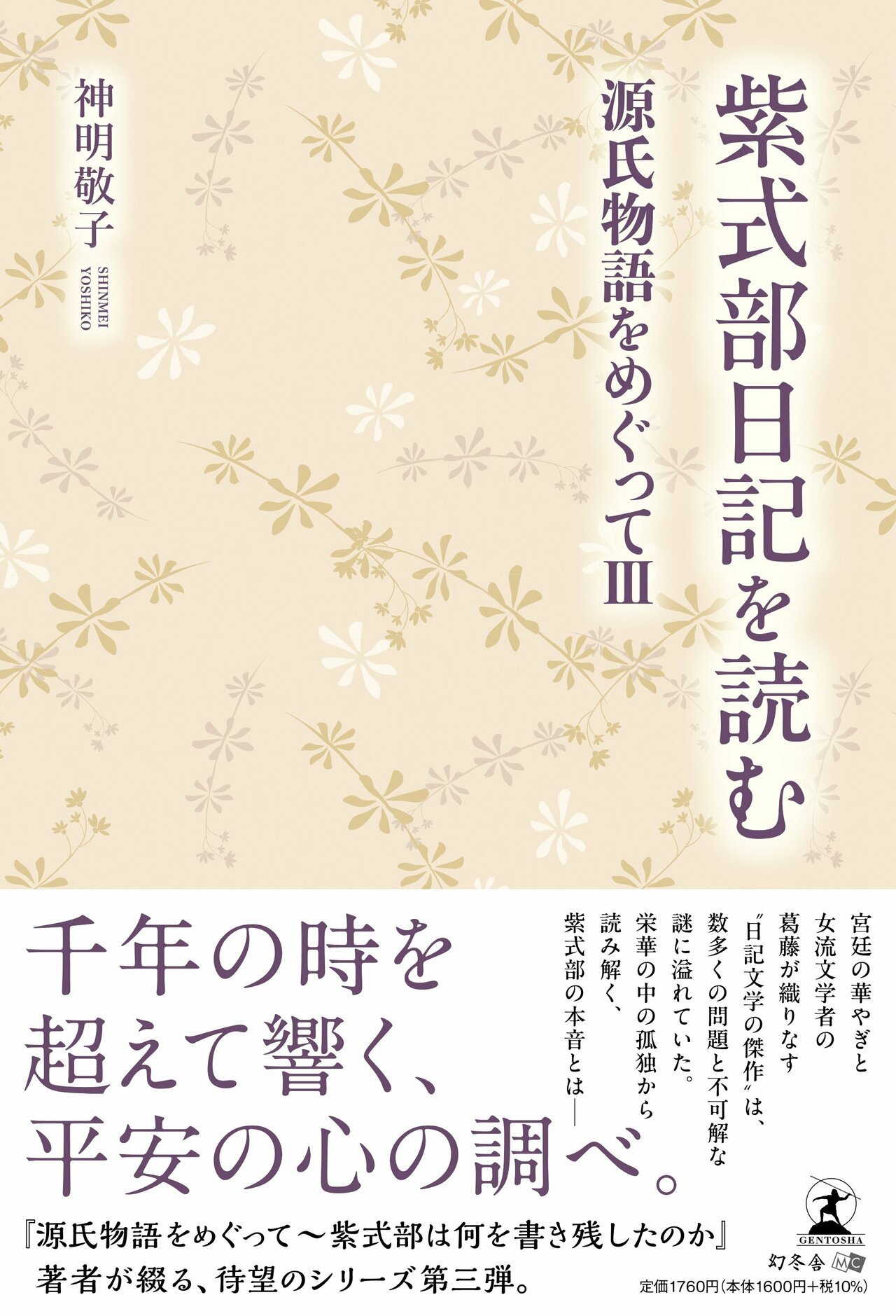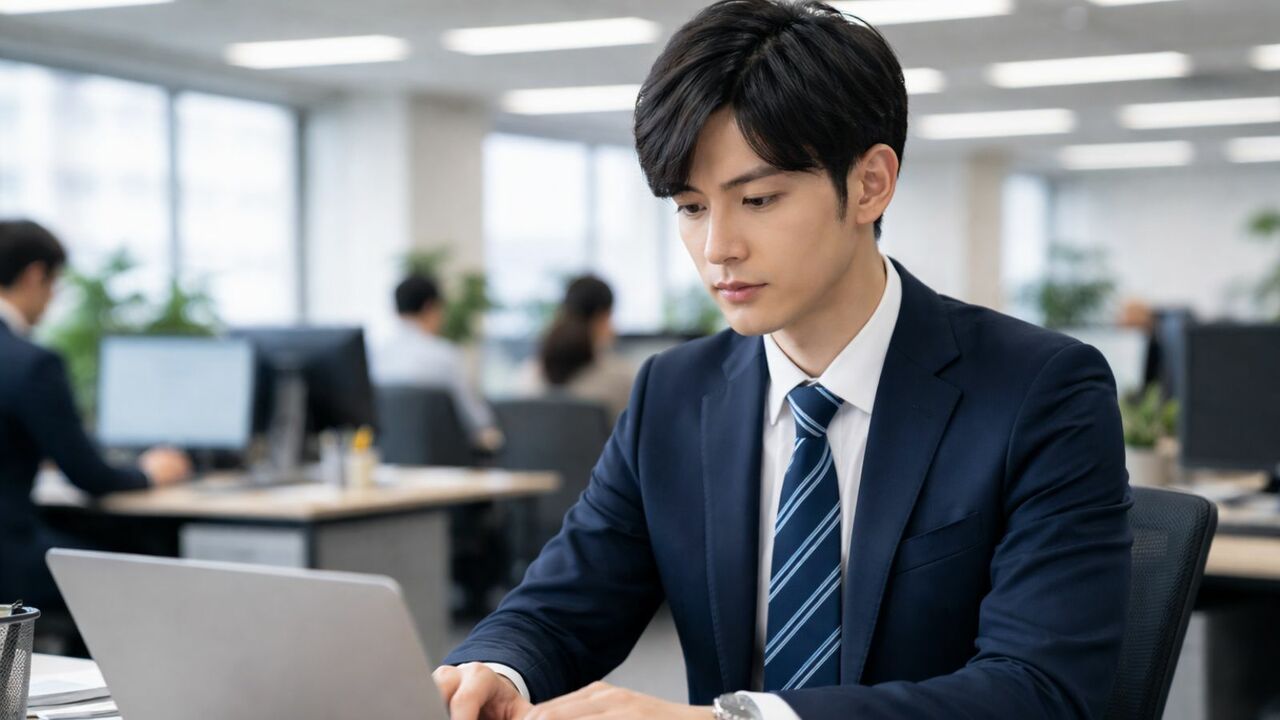このように、世間の人のことをあれこれと思って、その果てに(自分のことについては何も答えを出すこともなく)閉じるので、わが身を思い捨てない心が深いですね(自分のことは後で何とかなると思っていますね)。こんなことで、これから私はどうしようというのでしょうか。
この引用文の「閉じる」を、私はかつて、「このついでに」から脇道にそれていた文章を閉じて、ここで日記に戻ると解釈して、一月十一日の日記に戻ったと思っていた。しかし、十一日の暁は一月十一日ではなかった。
前著に述べたように、十一日の暁は、次のすきものと水鶏の歌へ続く寛弘六年五月の日記であると考えられる。
寛弘五年、彰子は四月十三日に土御門邸へ帰り、法華三十講は四月二十三日から五月二十二日まで行われ、彰子の御堂詣では五月五日に行われている。寛弘六年には、彰子は四月十余日に土御門邸に帰り、法華三十講は、四月二十六日から五月二十三日に行われている。寛弘六年の五月にも彰子の御堂詣でが行われたと考えられる。
「何せむとにかはべらむ」の箇所から、作者は日記に戻っていない。それでは、作者がここで閉じたのは何なのだろうか。
「閉じる」のは、作品であり、日記である。そこで、作者がここで閉じたのは、冒頭からこの部分まで約半年にわたって書いてきた日記であると考えられる。寛弘六年一月三日に続く、寛弘六年二月、三月、四月の日記が書かれていないのは、作者が日記を閉じたからである。
作者は長く日記を書く決心をして八月に冒頭を書き、翌年一月に自分の意志で日記を閉じているので、日記は人に命じられて書かれたものではない。