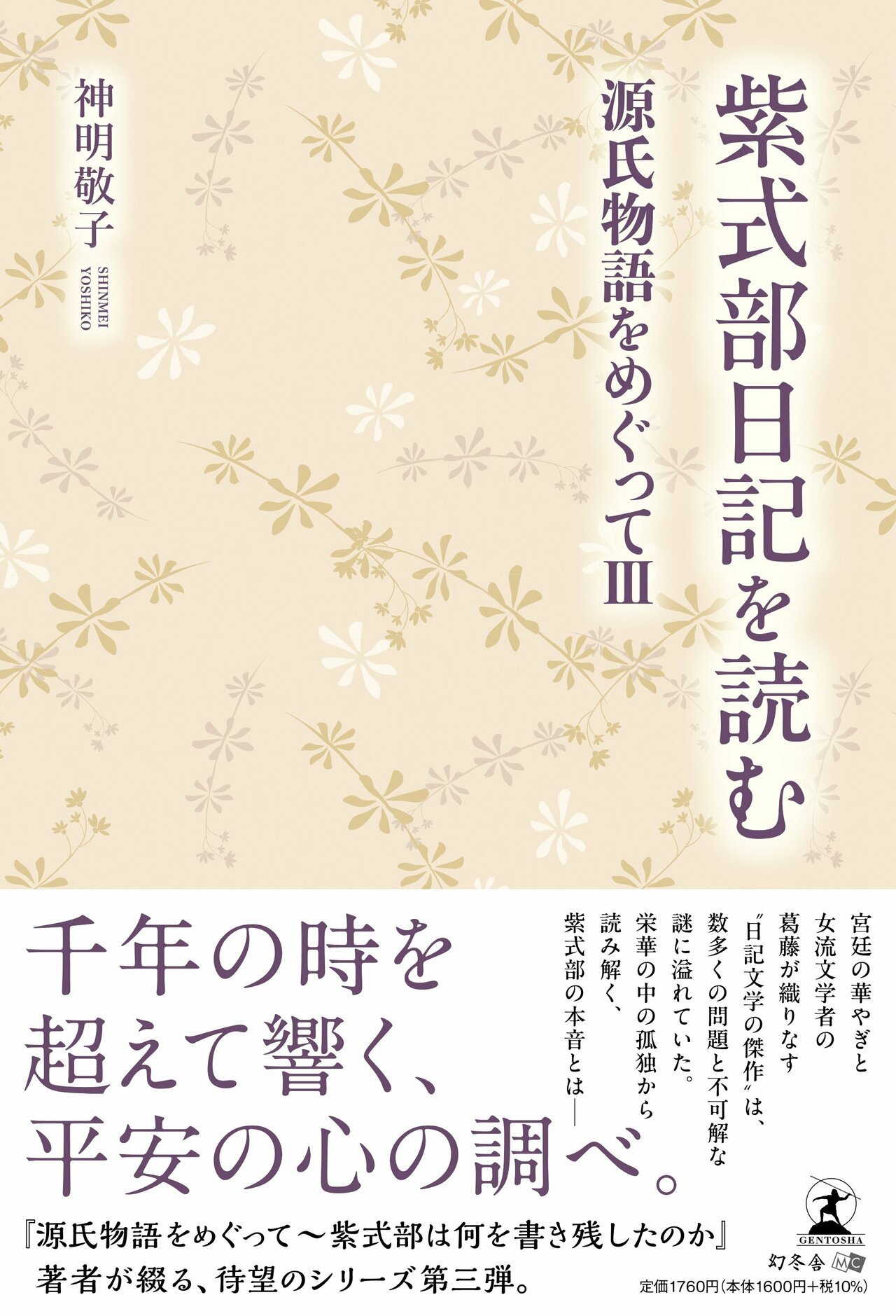消息文竄入説
寛弘六年正月三日の記事に続く大納言の君、宣旨の君の二人の女房批評に続いて、
このついでに、人のかたちを語りきこえさせば、ものいひさがなくやはべるべき。(一八九)
と述べて、宰相の君、小少将の君、宮の内侍の女房批評へと移っていく。この箇所は、「このついでに」以下は、消息文が竄入(ざんにゅう)しているという説がある。しかし女房批評へ移る文章の続き方は自然であり、消息文は竄入していないと考えられる。身近でよく知っていて詳しく書ける人物から、しだいによく知らない書きにくい人物に移っていくところも自然である。
人物批評は、やがて和泉式部、赤染衛門、清少納言の三人の批評に移り、ここで一転して自分について語り、相手の作品を求めて結ばれている。
八月に書き始められた日記は、もともと手紙として送られていた。それが「このついでに」以下は、日記という枠を離れてしまったので、この部分は、ひたすら相手に語りかけることになっている。この部分は、一見消息文のように思える。なぜ消息文のような部分が書かれたのか、後に詳しく述べる。
日記を閉じる
寛弘五年十二月二十九日から書き始められた日記は、寛弘六年一月三日の行事の途中から、「このついでに」と女房批評に移り、人のことや自分自身のことをさまざまに語り、次のように結ばれている。
かく世の人ごとのうへを思ひ思ひ、はてにとぢめはべれば、身を思ひすてぬ心の、さても深うはべるべきかな。何せむとにかはべらむ。(二一二)
この部分は次のような意味だと考えられる。