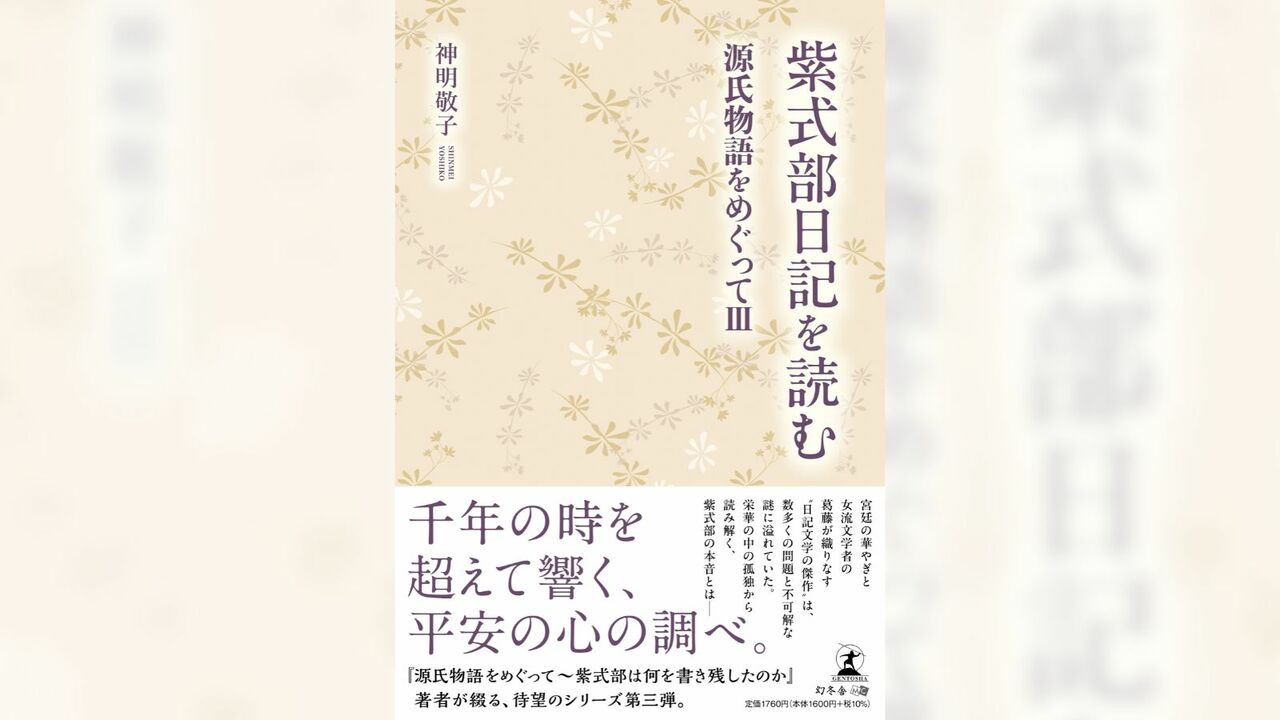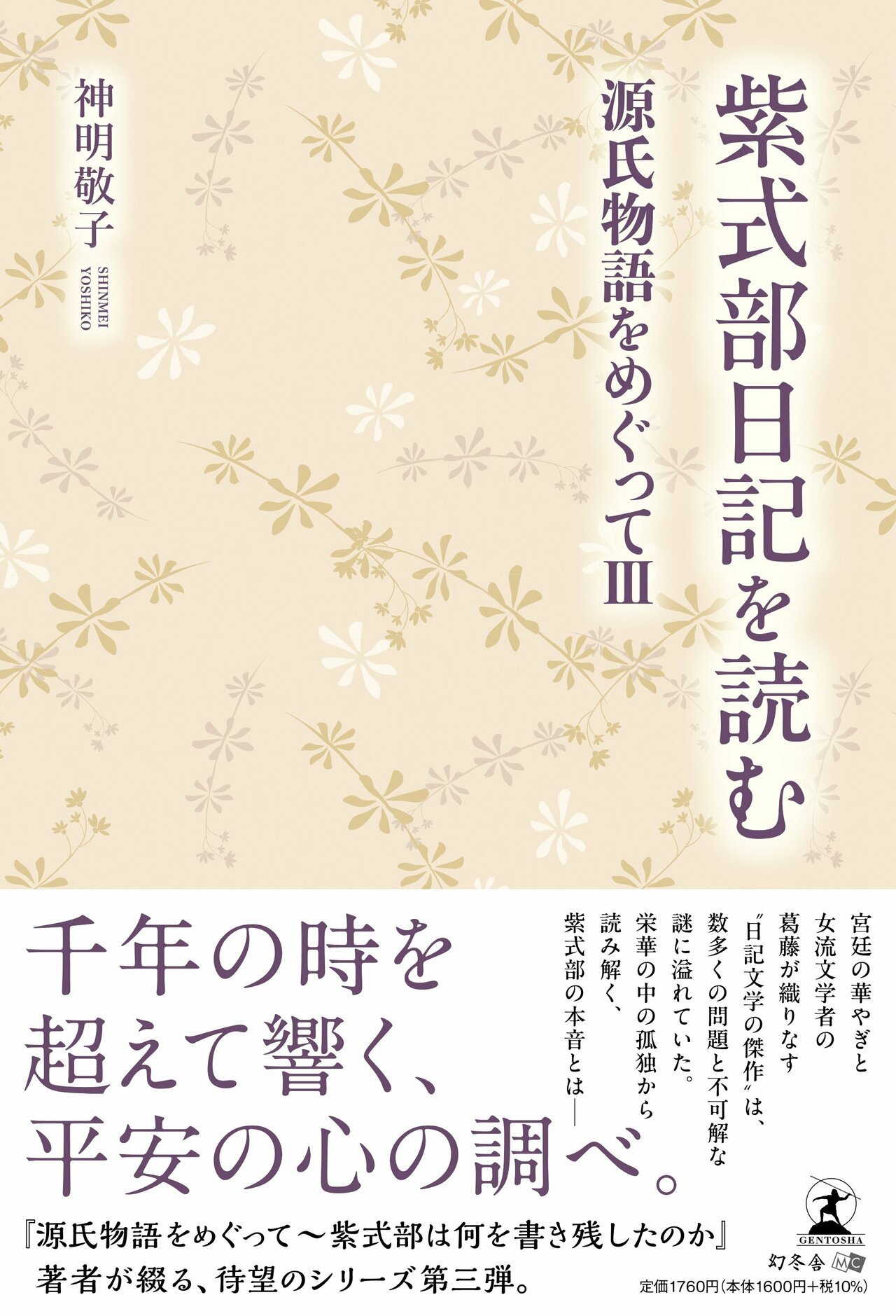【前回記事を読む】【紫式部日記】なぜ閉じたはずの日記が再開? 五月と翌年正月に加筆された謎に迫る
第一章 紫式部日記
二 日記はいつ書かれたか
寛弘五年八月――物語に惹かれる心
八月はまだ皇子誕生にかかわる行事は、五壇の御修法くらいしかなく、八月の日記は比較的短い。日記は秋の夜から書き起こされ、その夜の彰子の様子は、
憂き世のなぐさめには、かかる御前をこそたづねまゐるべかりけれと、うつし心をばひきたがへ、たとしへなくよろづ忘らるるも、かつはあやし。(一二三)
と、思わず現実の憂いを忘れて、引き込まれてしまうほど美しい。夜が明けて、露もまだ落ちないころの、道長との女郎花の歌のやりとりも物語の一場面のようである。八月には、他に二つの物語的な場面が描かれている。
しめやかなる夕暮に、宰相の君と二人、物語してゐたるに、殿の三位(さんみ)の君、簾(すだれ)のつま引きあげて、ゐたまふ。年のほどよりはいとおとなしく、心にくきさまして、(略)うちとけぬほどにて、「おほかる野辺に」とうち誦(ず)して、立ちたまひにしさまこそ、物語にほめたるをとこの心地しはべりしか。(一二六)
宰相の君と二人でいるところに頼通が訪れて、しみじみと話をして去る様子を、作者は物語の中の人物のようだと感じている。
上よりおるる途(みち)に、弁の宰相の君の戸口をさしのぞきたれば、昼寝したまへるほどなりけり。(略)
絵にかきたるものの姫君の心地すれば、口おほひを引きやりて、「物語の女の心地もしたまへるかな」といふに、見あけて、「もの狂ほしの御さまや。寝たる人を心なくおどろかすものか」とて、すこし起きあがりたまへる顔の、うち赤みたまへるなど、こまかにをかしうこそはべりしか。
おほかたもよき人の、をりからに、またこよなくまさるわざなりけり。(一二八)
通りがかりに、宰相の君の戸口をのぞくと、昼寝をしていた。絵に描いた物語の姫君のようだったので、思わず口を覆っていた袖を引きのけて起こしてしまった。起きあがった宰相の君の顔は、日ごろから美しい人が、またこよなく美しかったという。