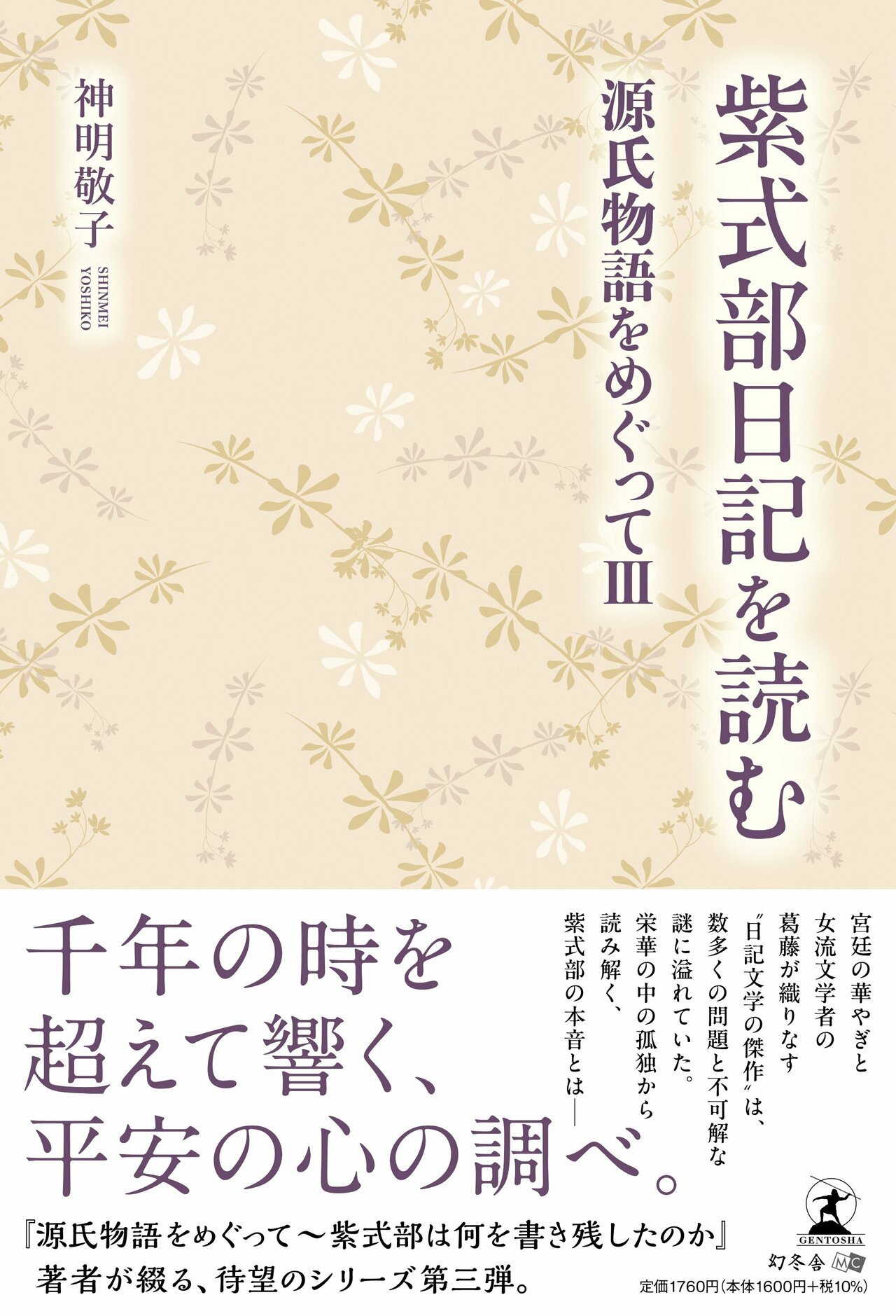寛弘五年十一月――草子作り
入らせたまふべきことも近うなりぬれど、人々はうちつぎつつ心のどかならぬに、御前には、御冊子(みさうし)つくりいとなませたまふとて、明けたてば、まづむかひさぶらひて、いろいろの紙選りととのへて、物語の本どもそへつつ、ところどころにふみ書きくばる。かつは綴ぢあつめしたたむるを役にて、明かし暮らす。(一六七)
草子作りは、まず依頼状を書くことから始まる。依頼状には、紙と見本が添えられる。見本は、作者が清書したもので、「物語の本どもそへつつ」と、綴じられて本の形になっている。依頼状を届けると、依頼された相手が書写を始めるので、書写されている間、何日か、何もすることがなくなる。
草子作りの後半は、一条天皇への献上本が綴じられる。草子作りは、まず前半の依頼状の発送があり、「かつは」と、後半のもう一つの仕事がある。草子作りの終了は、十一月十日より前だと考えられる。草子作りは比較的小規模に、短い日数で終わっている。
局に、物語の本どもとりにやりて隠しおきたるを、御前にあるほどに、やをらおはしまいて、あさらせたまひて、みな内侍の督の殿に、奉りたまひてけり。よろしう書きかへたりしは、みなひきうしなひて、心もとなき名をぞとりはべりけむかし。(一六八)
作者は草子作りに使う本を局に隠していた。この中には書写の見本が含まれているが、書写の見本は依頼状とともに、すべて発送されてしまう。局にあった本の中には、書写の見本の他に、道長が持っていった本があった。書写の見本は、「よろしう書きかへたりし」という清書本であり、その他は清書されていない作者自身の本であったと考えられる。
【イチオシ記事】まさか実の娘を手籠めにするとは…天地がひっくり返るほど驚き足腰が立たなくなってその場にへたり込み…
【注目記事】銀行員の夫は給料50万円だったが、生活費はいつも8万円しかくれなかった。子供が二人産まれても、その額は変わらず。