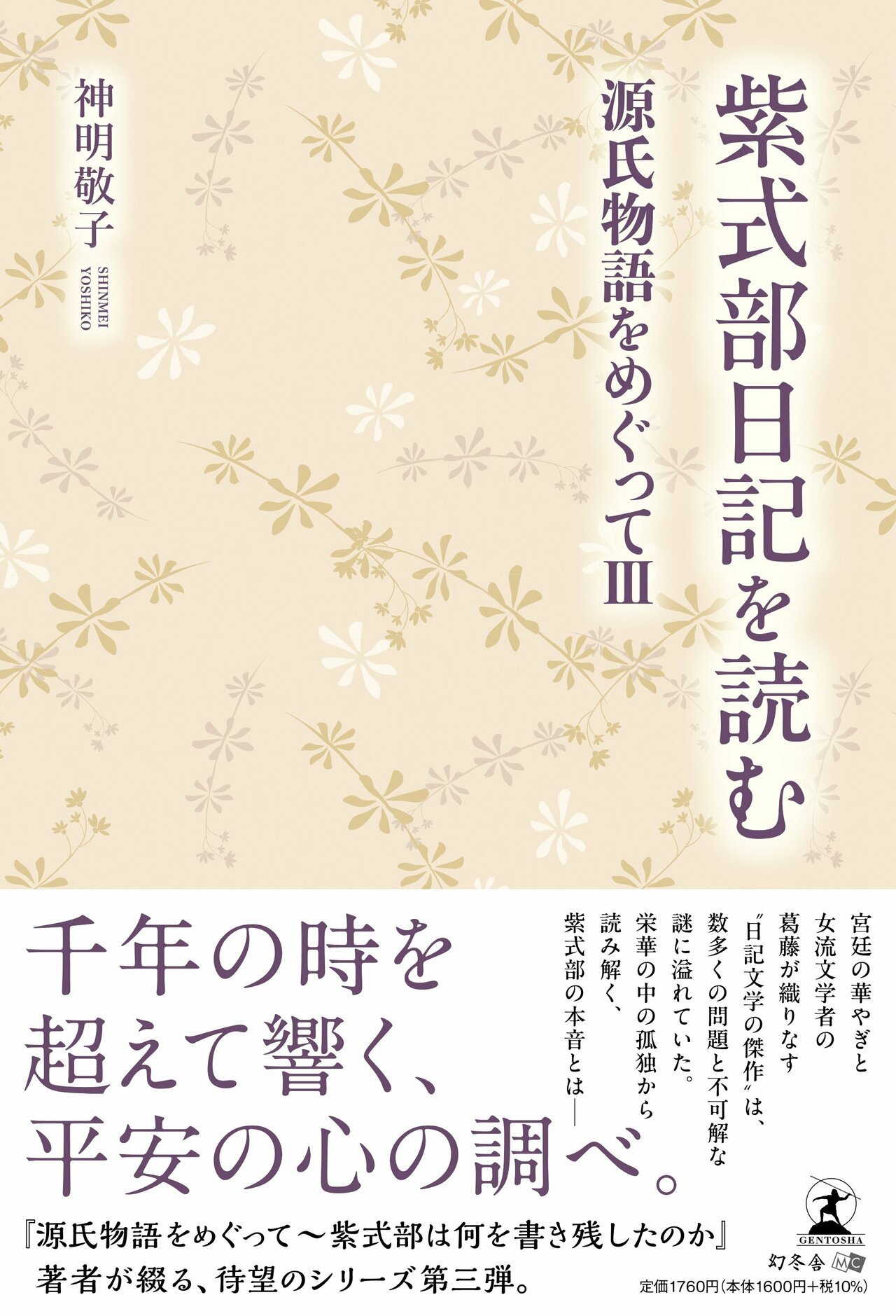宰相の君は、日記にもっとも多く名が出てくる女房で、宰相の君、小少将の君、大納言の君は、作者がもっとも親しかった三人である。
八月の日記の中に、四箇所も物語を思わせる場面が描かれている。このころの作者は、第二部を書き終えて、何も書く物語はなかったと思われるが、見たものから、自然に物語を思わずにはいられなかったようである。やはり無意識にも物語作者の目で見ているのだと思われる。そして、相手に物語のようだったと伝えずにはいられないのであろう。
日記が、公的な記録であれば、同僚の女房の昼寝の様子が書かれることはないであろう。日記はやはり親しい相手に、見たこと思ったことを伝える私的な作品であったと考えられる。
寛弘五年九月
九月の日記は、九日の菊の節句に、倫子(りんし)から贈られた菊の綿のことから書き始められ、皇子誕生と、それに続く儀式や行事が詳しく書かれている。
十一日 敦成親王の誕生・十三日 三日の産養(うぶやしない)・十五日 五日の産養 十六日 月夜の舟遊び・十九日 九日の産養
寛弘五年十月
彰子の出産予定は九月であり、草子作りの最初の予定は十月の出仕日の中だったと考えられる。作者は草子作りがあると思って十月十日ごろに出仕し、その後彰子の体調によって草子作りが延期になり、仕方なく十七日で帰ったと考えられる。
十月の日記は、行幸当日の記事以外に書かれているのは、道長の祖父ぶり、庭を見ての思い、小少将の君との歌のやりとり、たまたま局に来た斉信と実成のことだけであり、十月の日記に書かれた日数は、とても短かった。