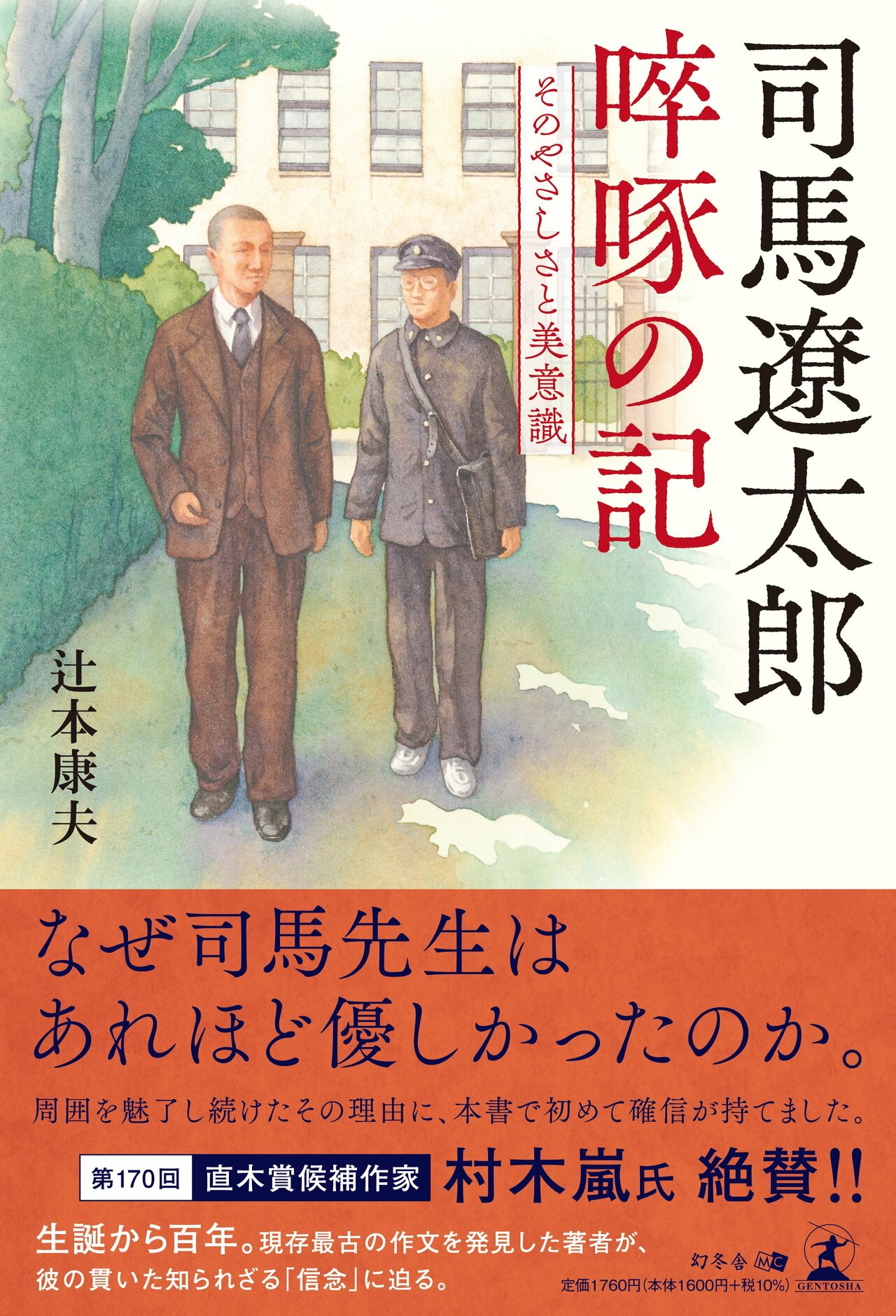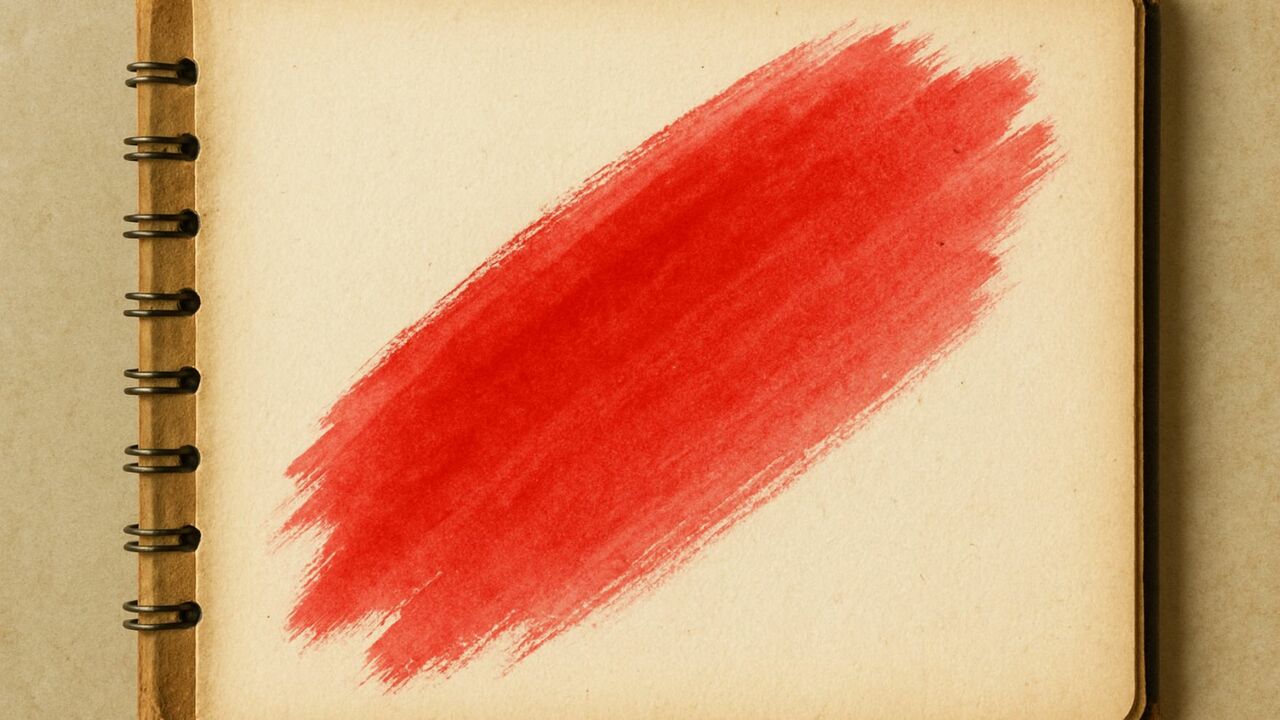だとすれば、教師経験が短かった可能性が浮かんできます。もしかすると、その教師経験の少なさが司馬さんへの対応のまずさにつながったのかもしれません。
私の教師経験からしても、教壇から教室内を見ると授業に集中できていない生徒はよくわかるものです。生徒の雰囲気や首の傾き、視線などでわかるのです。一度、注意して授業に集中してくれればよいですが、司馬さんはそうではなかったのでしょう。それどころか反論までしたので、先生の怒りに拍車をかけた可能性があります。
しかし、先生のこの対処の仕方は完全に間違っていました。たとえ、突発事故のように喧嘩状態になったとしても、その後の司馬さんへのフォローが絶対に必要だからです。なぜなら、結果的に先生の指導は逆効果になったわけですし、司馬さんの心に消えない大きな傷を残したからです。
こんな状況に司馬さんが陥ってしまったのは、ひとえにその先生に責任がありました。私の経験からいえば、ベテランになればなるほど、生徒がいくら挑発しても教師は逆に冷静になることが多いようです。戦前であっても、そのことは変わらなかったでしょう。
生徒にとって、学級担任は授業に来るだけの教科担任とはまったく違う特別な存在です。教科担任は週に三、四度の授業で顔を合わせるだけですが、学級担任は教科担任として授業をするだけでなく、朝礼、終礼で毎日学級の生徒と顔を合わさなければいけません。
現在とは違い、戦前の学級担任はその学級内における圧倒的な権力者でした。そんな担任と二年間も戦い、冷戦を続けながら、全蔵書読破と速読術の習得を継続した司馬さんには、驚くほかはありませんが、その反面、司馬さんのストレスは言葉に表せないほどだったことでしょう。
【前回の記事を読む】司馬遼太郎の人生を紐解く。小説家としての背骨を作った、御蔵跡図書館。
【イチオシ記事】「リンパへの転移が見つかりました」手術後三カ月で再発。五年生存率は十パーセント。涙を抑えることができなかった…