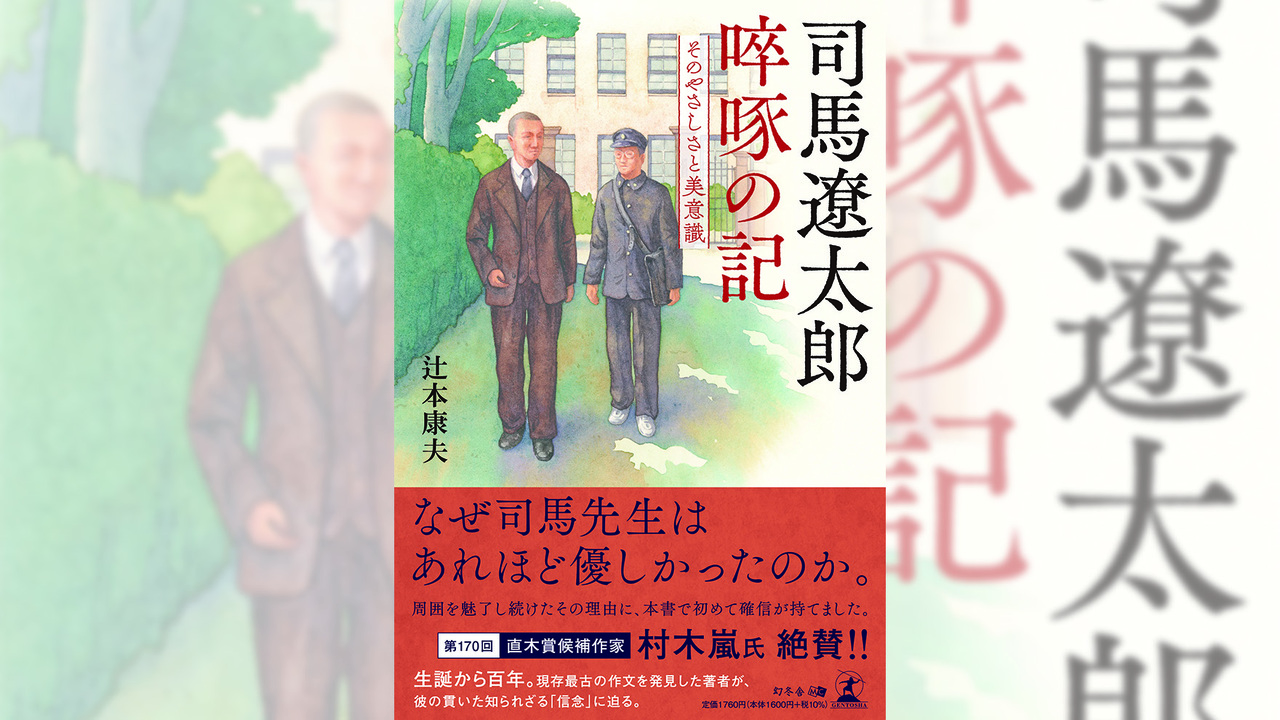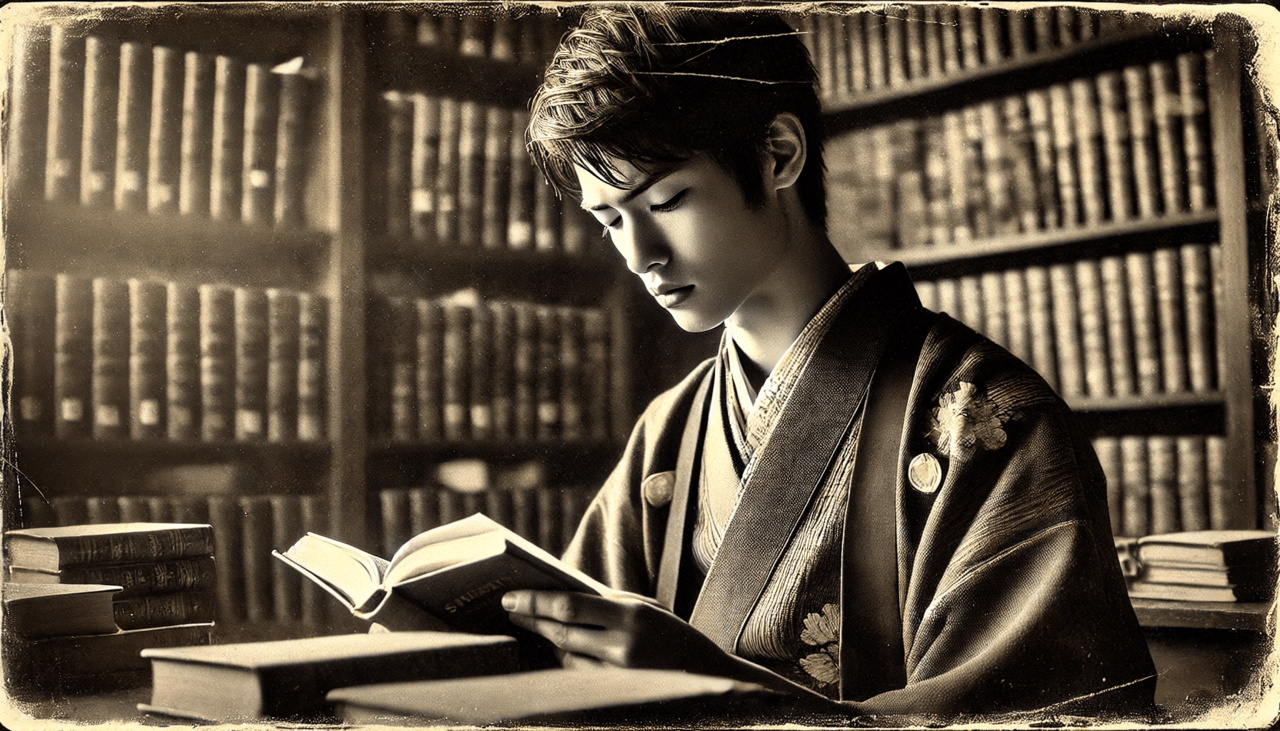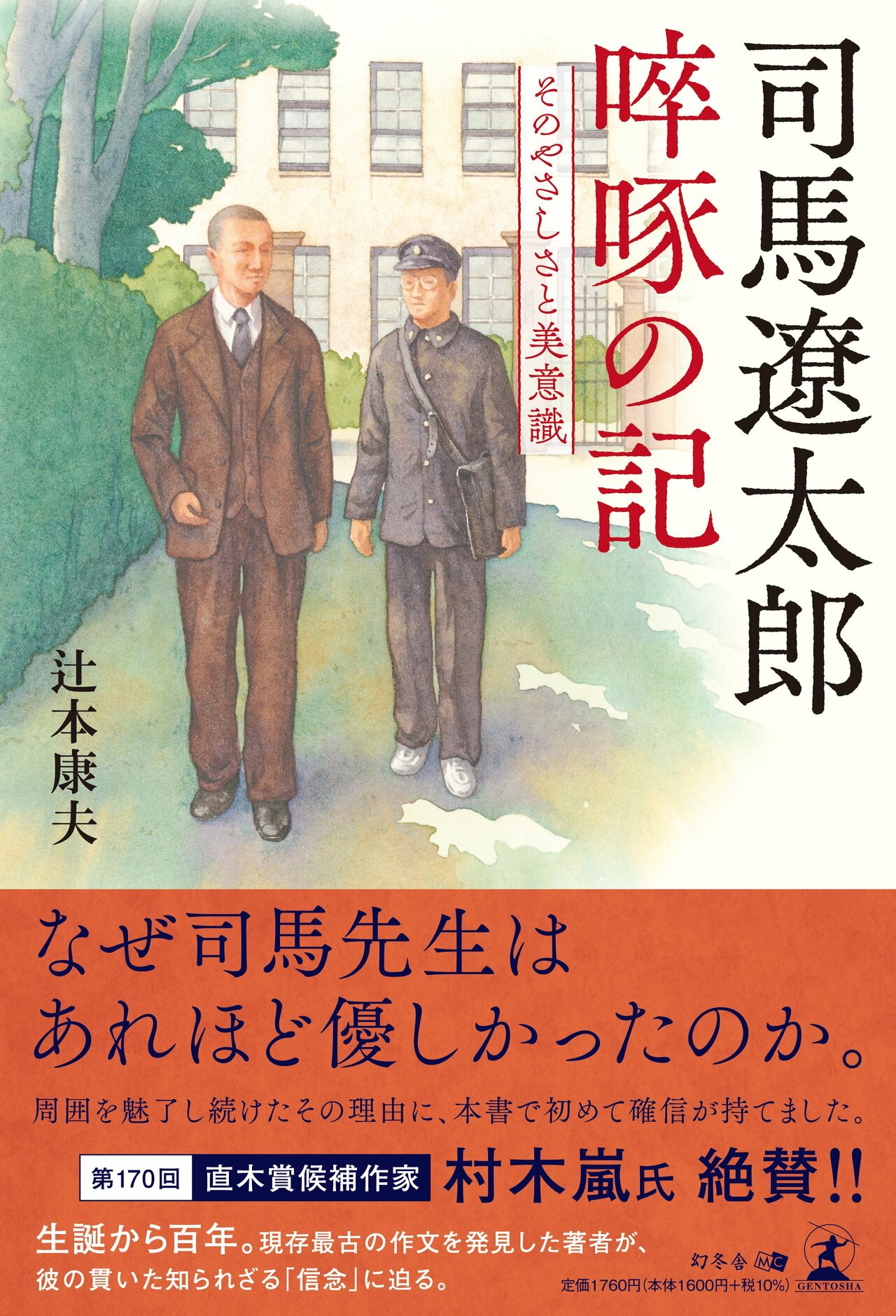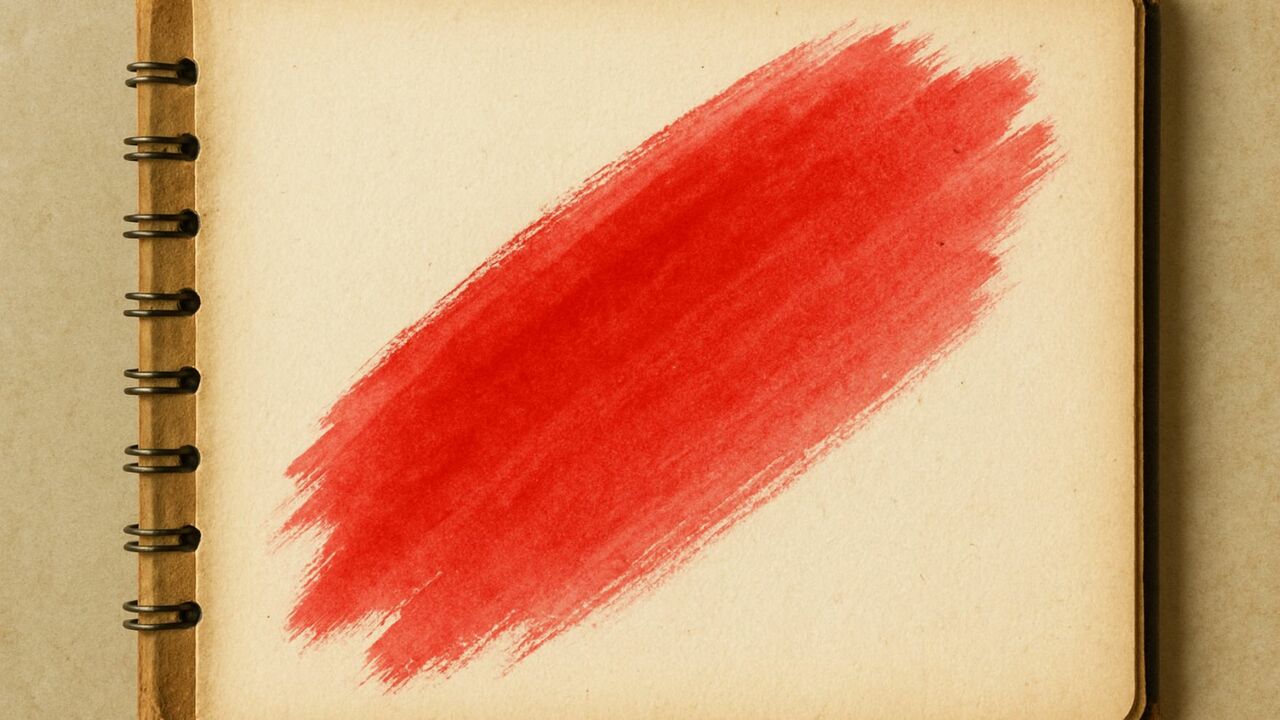第一章 司馬遼太郎の育った庭
一 上宮中学校
司馬さんは自分の美意識から両親には先生との軋轢は一切話さなかったと思われます。当然、親に泣きついたりもしなかったでしょう。そのため、ますますストレスを溜め込むことになった可能性があります。
先生には学級教師としての経験不足を感じます。もしベテランの先生だったら、二人の関係はそこまで悪化することもなく、司馬さんをうまく授業に誘導できたかもしれません。先生の過剰な叱責によって、司馬さんの学校嫌いはますます激しくなったと想像できます。
司馬さんが御蔵跡図書館の蔵書のすべてを読んだことはつとに有名ですが、実は司馬さんがこの全蔵書読破について書いたものはあまりありません。
最も有名なものが、『司馬遼太郎全集32』の年譜に付属した「足跡 自伝的断章集成6」の昭和十三年の項の「たいてい、夜の八時か九時ごろまでたてこもって、片っぱしから本を読んだものです。この図書館通いは大阪外語を出るまで続いたのですが、しまいには読む本がなくなってしまい、魚釣りの本まで読んでしまいました」というものです。
私は司馬さんが魚釣りの本まで読んでしまった背景には、先生との対立があったと想像します。私は司馬さんの御蔵跡図書館通いを、中学一年から二年の終わりまでを前期、三年から大学二年の仮卒業までを後期の二期に分けて考えています。
前期は先生のストレスから逃れるためのものであり、後期は全蔵書読破のための図書館通いです。この全蔵書読破というのは、司馬さんがある目的を持って、御蔵跡図書館の蔵書を読破しようとしたことを指すものです。
全蔵書読破の目標は中学一年の頃に作られたと想像されますが、正確なことはわかりません。ただ、わかっていることは、当時の司馬さんは「学校が終わったら図書館に行くことのみが楽しみでした。ベルが鳴るとワーッと走っていく感じ」だったということだけです。
しかし、ようやく、中学三年になって先生が担任から外れたことで、三年からの図書館通いは別の状況になりました。ストレスから逃げるための全蔵書読破ではなく、本来の目的の全蔵書読破に変わったと想像されるのです。
もっとも、四年からは旧制高校の受験勉強を始めなければいけませんから、全蔵書読破に集中できたのは、そう長くはありませんでした。
司馬さんは『風塵抄』の「“独学”のすすめ」で、「『ニューヨークという地名のおこりはね』と、その先生が物わかりよく教えてくれたとしたら、この“独学癖”はつかなかったかもしれない。その点、反面の大恩はある」と書いています。
この言葉は大人になった司馬さんだから言えた言葉であって、逆にいえば、司馬さんは独学癖がつくくらいに追いつめられていたということでもあります。
また、この「反面の大恩」は独学癖だけでなく、全蔵書読破や速読術の習得にもつながっていたと考えるべきでしょう。この先生が司馬さんの作家への道の最初の重要な部分を作ったといえる所以です。