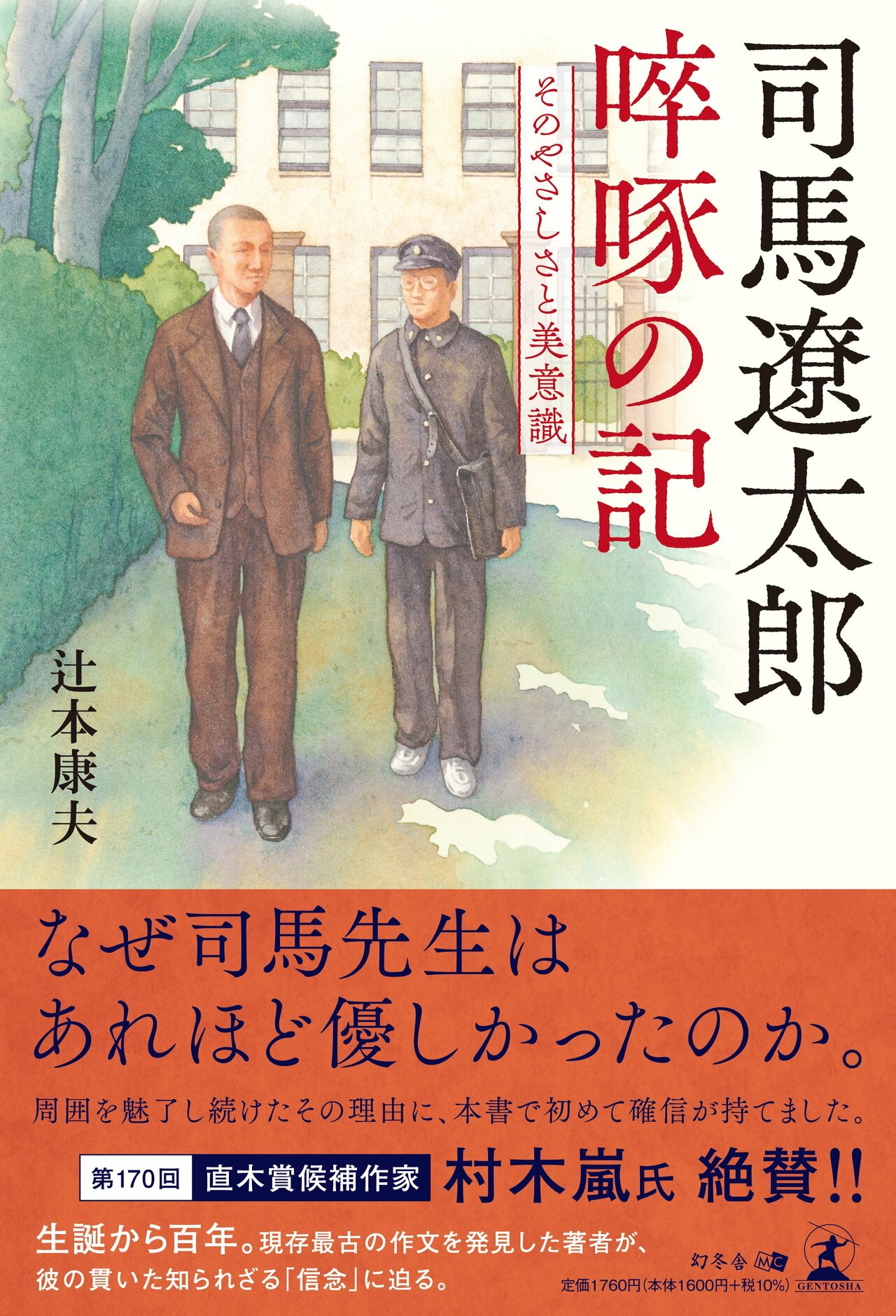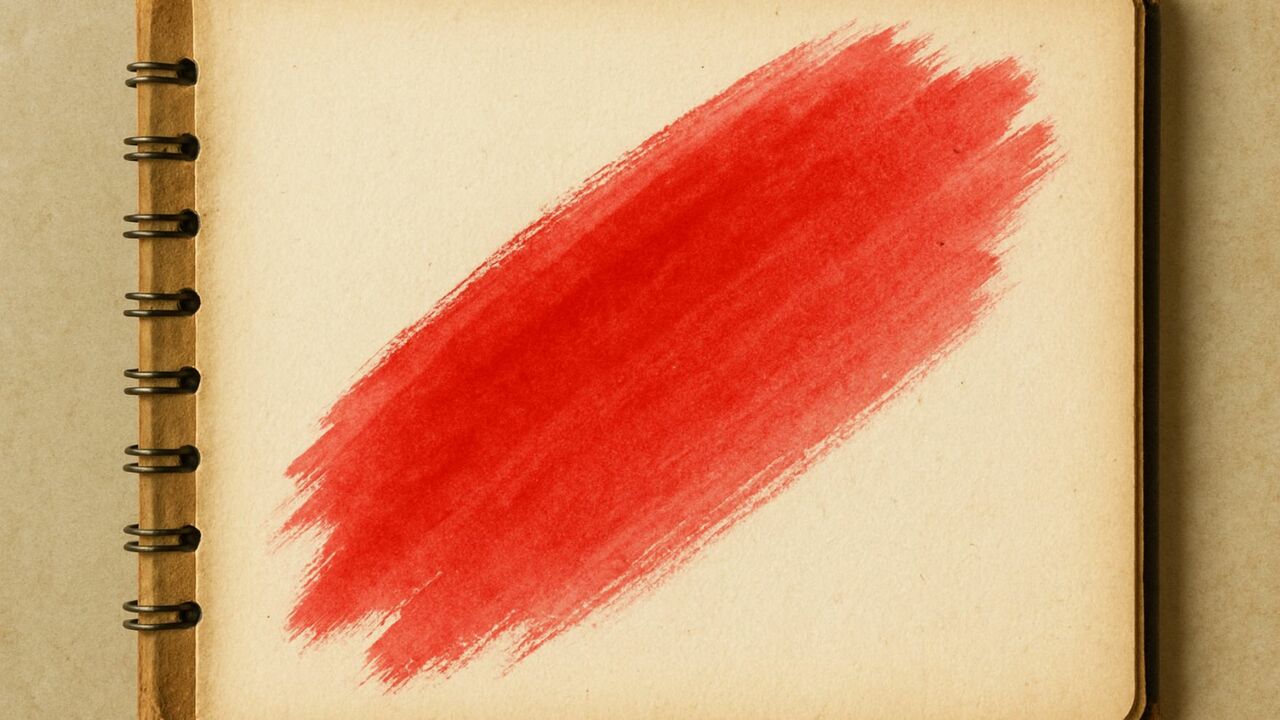しかし、ご遺族に迷惑がかかるかもしれないので、本名は公表しないでいただきたいとも書かれていました。そういったわけで、私は件の英語の先生を以降は英語の先生、その先生などと表したいと思います。
そもそも先生との対立の発端は、『風塵抄』によれば、一学期の英語のリーダー(読本)の授業中に、司馬さんがニューヨークの語源を質問したことでした。
想像ですが、先生は学級担任として、授業に集中しない司馬さんを前から腹に据えかねていて、今度何かあればと狙っていたのかもしれません。授業妨害だと思ったのか、司馬さんが質問した途端に「地名に意味があるか!」と怒鳴ったといいますから、チャンス到来といったところだったのかもしれません。
司馬さんは自分が学校に馴染めなかったことについて、「とにかく、一時間小さないすに座ってなきゃいけないというのは、もう無理です」と書いているくらいですから、授業に集中できない生徒だったと思われます。
また別の講演では、「大人になってからやっとわかったのですが、人間にはいろいろあり、人の話が聞けない奴がいて、どうやら自分もそうらしい」と話していますので、先生に誤解される要素はあったようです。
こうして先生の激怒にあった司馬さんでしたが、もともと授業妨害をするつもりなど毛頭ないのですから、謝らなかったようです。その後も司馬さんは先生に目のかたきにされたそうで最後は先生を黙殺するようになったといいます。この対立は三年になって先生が担任から外れるまで続きました。
当時の上宮中学校の教員は公立中学校を定年退職した再就職組の中高年の先生が多かったようですから、若いその先生はめずらしい存在でした。当時の上宮中学の教員の採用状況を考えると、三十過ぎの先生だったとしても、若くとも新卒ではなく、転職組だったのではないでしょうか。