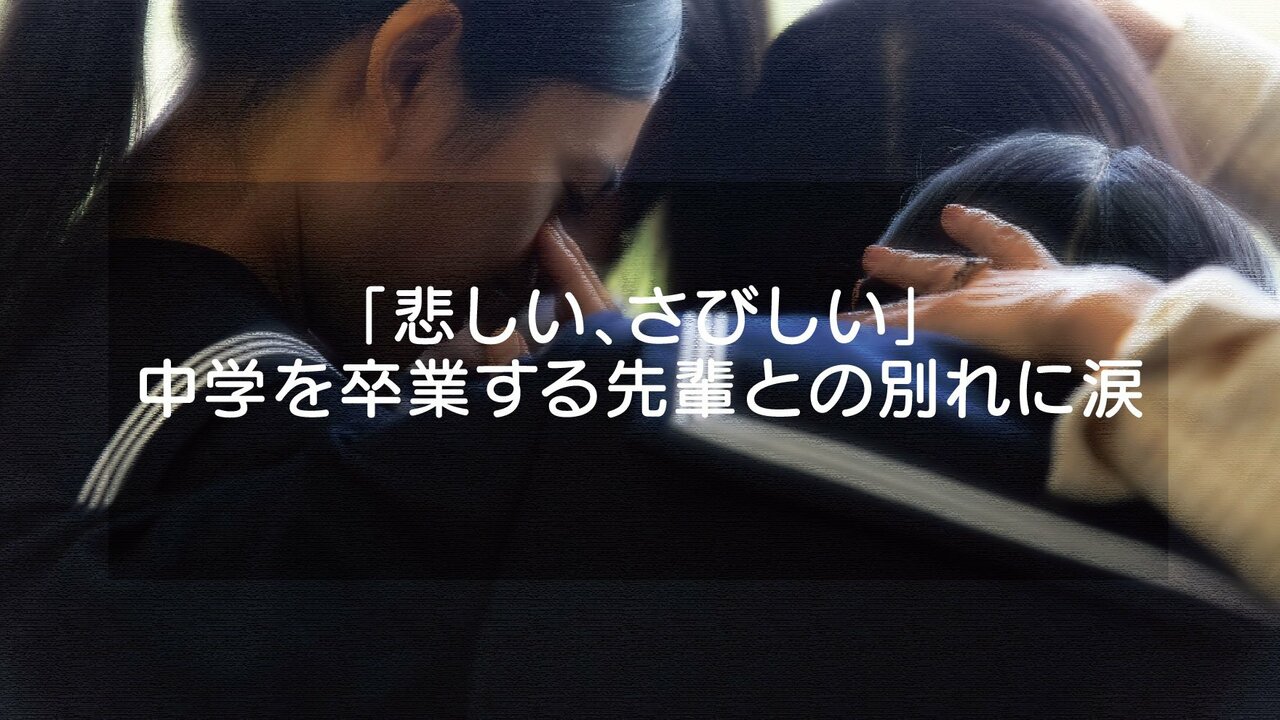二学期最初の会議
「皆さん、聞いてください」
そう、大上段にかまえる必要なんかないんだ。背伸びしたところで、身の丈以上のえらそうな発言がわたしにできるわけない。今のわたしにできる精いっぱいのこと――それって、なんだろう。
そう考えたとき、心にすっと浮かんだのは、
「今度は、きみたちにもこの学校のこと、話してもらえるとうれしいよ」
というあの日の先輩の言葉。ずっとかかえたままだった宿題に、ちゃんと答えを出そう。
わたしは、懸命に話した。わたしたちの学校祭を、わたしたち自身の手で、悔いの残らない楽しいものにしたい――ただ、その思いを言葉にして。みんなにちゃんと伝わったかどうかはわからない。
でも、この学校が好きだというわたしの気持ちを、うそじゃない自分の言葉で話せた―そう思ったとき、今度こそ、本当に頭の中が空っぽになった。
頭をさげたわたしは、そのまま椅子にぺたんと座りこんだ。そのとたん、足ががくがくと震えだしたのが、自分でもなんだかおかしかった。ぱちぱち、という音がして、はっとして顔をあげる。
先輩が、にっこり笑いながら拍手していた。それに続くように、隣で激しく手をたたく音がした。もちろん、マオだ。少し間を置いて、部屋のあちこちからいくつかの拍手が起こった。その音がまだ続く中で、先輩がすっと立ちあがった。
「本多さんの発言を全面的に支持します」
問題の三年生男子は、むすっと黙りこんで、もうそれ以上なにも言わなかった。クラス委員会議に出ていた一年間で、わたしがみんなの注目を浴びるほど目立ったのは、あとにも先にもこの学校祭の会議のときだけ。
というか、中学生活三年間で、わたしがもてる瞬発力のすべてを解放した、たった一度の晴れ舞台?がこのときだった。
考えてみると、わたしにとって、学校祭にまつわる最大の思い出も、本番のときより、この会議でみんなとたくさんの議論を交わしたことだったような気がする。
なにしろ、肝心の学校祭当日は、連絡要員やらトラブル対応やらで走りまわっているうちに終わってしまい、催しや展示物を楽しんだ記憶がない。
でも、わたしの中には、自分たちの手でこの学校祭をつくったんだ、という不思議な充実感が宝物のように残った。
もうひとつ、うれしかったのは、会議や学校祭の準備運営を通じて、先輩とのつながりが、よりいっそう深くて強いものになったということだ。
わたしたちは、チイカも誘って、先輩のバレーボールの試合を観に行ったりもした(マオとチイカはすぐに意気投合し、まるでずっと前からの知りあいみたいに仲良くなった)。
常に仲間に声をかけながら、コートの上で躍動する先輩からは、会議のときとはまたちがう、生き生きとした充実感があふれていた。
相手のブロックをものともせず、コートに突き刺さるようなスパイクをバンバン打ちこむ先輩は、ものすごくかっこよかった。
得点が決まるたび、わたしたちは、キャアキャア声をあげながら、たがいの手をとって喜んだ。
年が変わるころ、先輩のわたしに対する呼び名は、「ポンちゃん」から「ポンタ」になっていた。
同級生に「ポンタ」と呼ばれると、(親しみをこめた呼び名だとわかっていても)いつも少しだけ複雑な思いにおちいってしまうのだけど、先輩にそう呼ばれるのは、なんだかちょっとくすぐったくて、うれしかった。
でも、駆け足で進んでいくカレンダーは、サキ先輩との別れのときが、それと同じ早さで近づいていることを告げていた。思えば、先輩からは、いつも助けられたり、教えられたり――なにかをもらってばかりだった。
わたしたちからは、なにひとつ返せないままで、先輩は、もうすぐこの中学を卒業してしまう。わたしの知らない新しい世界へと旅立ってしまう。
ほんとは、ちゃんと感謝の気持ちを伝えて、お祝いを言わなきゃいけないのに。なんでわたし、こんなにうだうだしてるんだろう。胸の奥の小さなすきま。
悲しい、さびしい――いろいろな言葉をそこにあてはめてみるけれど、どれもぴったりとは収まらない。そんなパズルを心の中で繰りかえし、結局そのすきまのかたちに一番近いのは「怖い」という言葉だと気づいた。
楽しいはずの未来が、そのときのわたしには、ただ怖いものでしかなかったのだ。
二月――三年生が出席する最後の会議。わたしとマオは、先輩のところに駆け寄った。
「あの……先輩」
「ん? どうしたの。妙にあらたまって」
「今まで、本当にありがとうございました!」