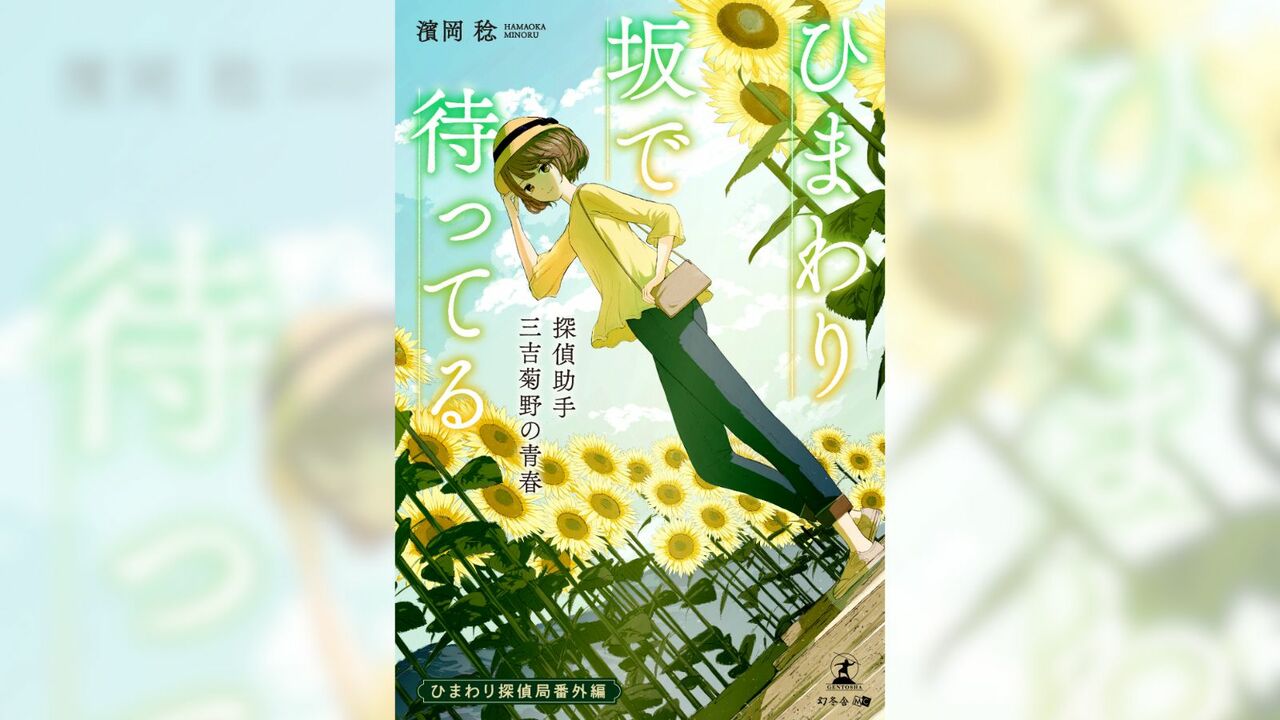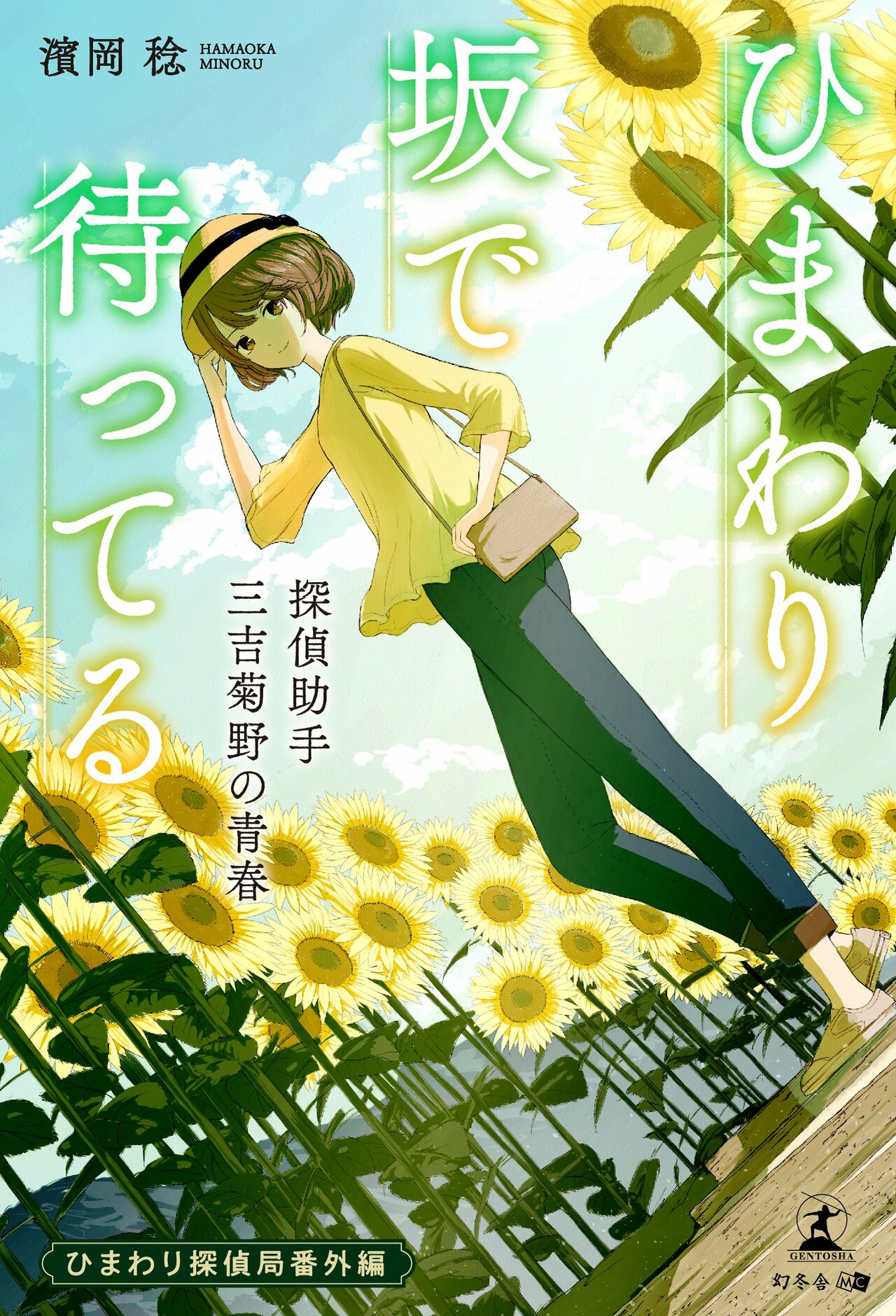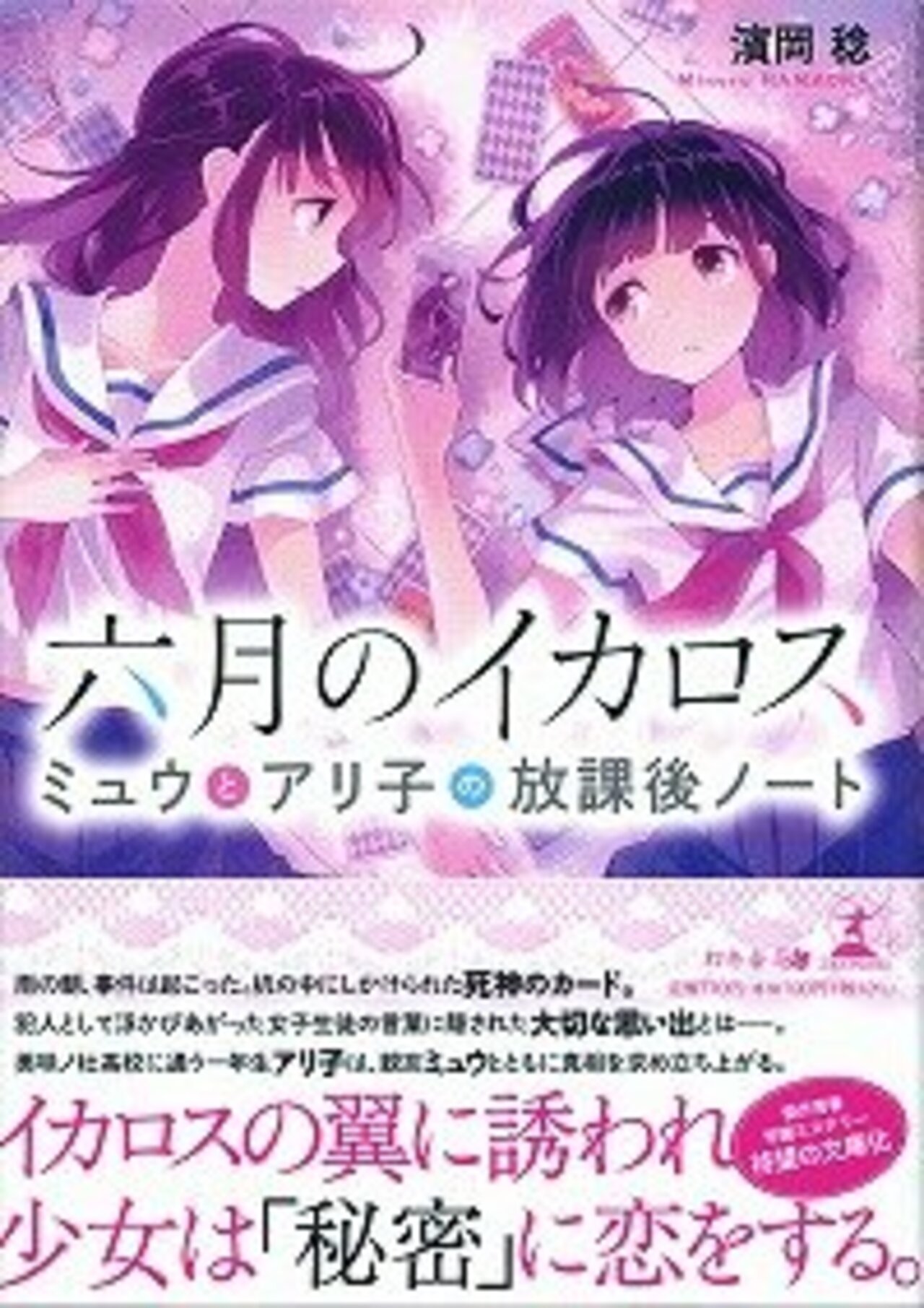【前回記事を読む】わたしという存在は、モザイクみたいなものなのだ。たくさんのわたしがこの世界にいて、その刻一刻と変わる断片を寄せ集めて…
プロローグ――二〇二×年、夏
2
「はい。ディケンズが明かさなかった事件の真相に答えを与えようという挑戦も、多くの論者によって試みられています。作中に『エドウィン・ドルードの謎』を取りこんだ創作上の試みも少なくありません。〝解決編のない未完のミステリイ〟というところにばかり読者の興味が集中してしまうことが、果たしてこの小説にとって幸福なのかどうかは、もっと論じられていいと思うのですが」
「でも、ディケンズの小説には、けっこう謎解き要素があるじゃないですか」
ろくに作品を読んでいるわけでもないのに、ちょっと知ったかぶってわたしはそうたずねた。それをしっかり見抜いているのか、先生はにこやかに「ええ」とうなずく。
「奇妙な謎をはらんだ殺人事件からはじまる『バーナビー・ラッジ』のような作品もありますし、一向に進まない訴訟事件にからんだ人間模様を軸に、探偵小説的な興味で物語を引っぱる『荒涼館』のような作品もありますね。
というより、初期の『ピクウィック・クラブ』のようなユーモアを主軸にした作品から晩年の大作に至るまで、ディケンズの作品には、必ずなにかしらの謎解き要素があります。それら、随所に散りばめられた魅力的な謎は、いずれの作品においても、読者の興味を引きつけ、物語を牽引する大きな役割を果たしていると言っていいでしょう。
エドガー・アラン・ポーが『バーナビー・ラッジ』の連載開始早々、ディケンズが作中にしかけた〝 トリック〟を見抜き、書評でそのトリックに言及した逸話はよく知られています。どうもポーは、ディケンズを生涯にわたってかなり意識していたフシがある。アメリカ旅行中のディケンズをわざわざ訪ねて、自身の売りこみまでしていますしね。
短編こそ最良の小説形式と考え、芸術としての小説の純粋性に執着したポーと、生涯にわたって長大な物語を書き続け、大衆のための小説にこだわり続けたディケンズは、まるで対極に位置する作家のようですが、その作品世界の芯の部分には、不思議と通いあうものがあるとぼくは感じています。
ポーとディケンズをともに愛読したドストエフスキーなら、そのへんをうまく説明してくれそうな気がするのですが……。