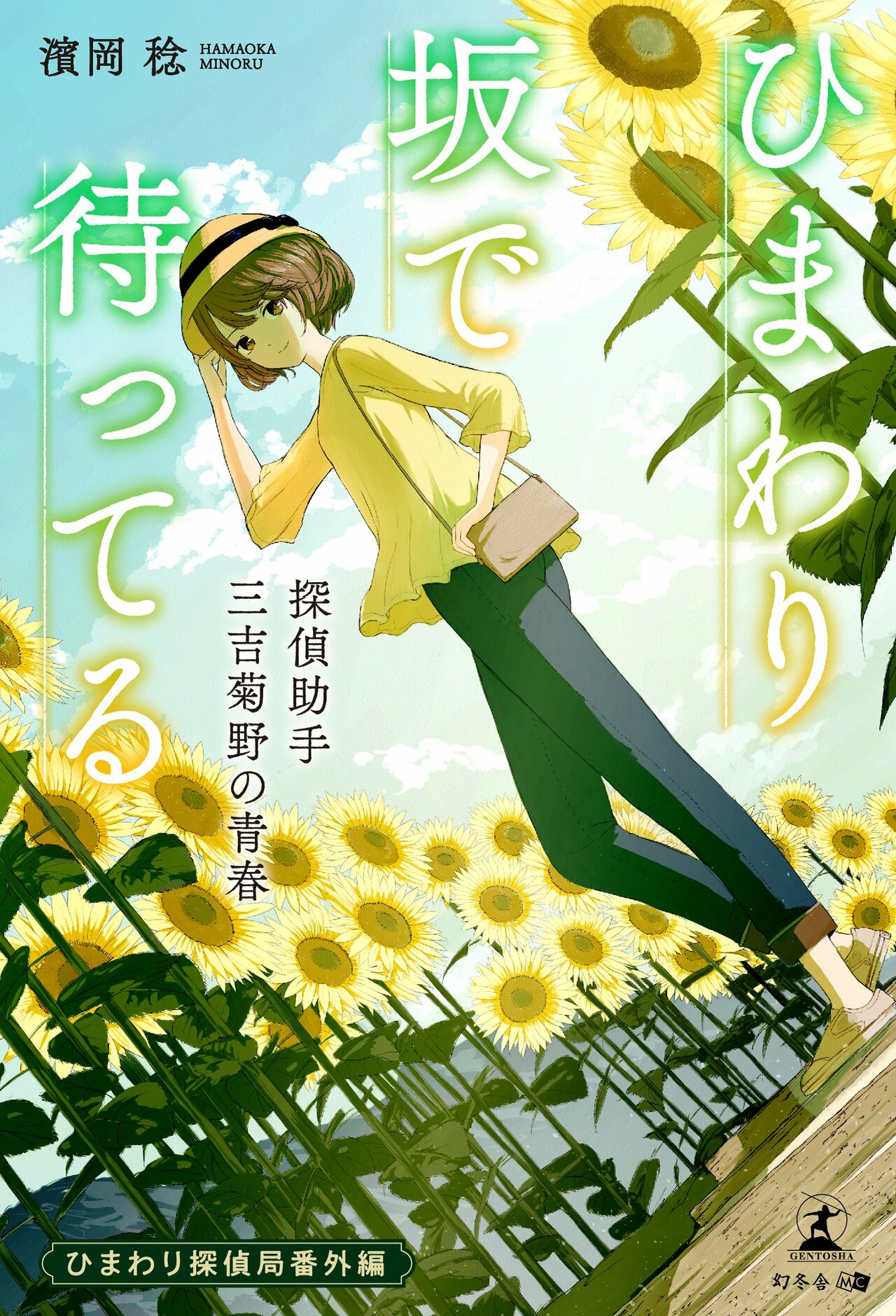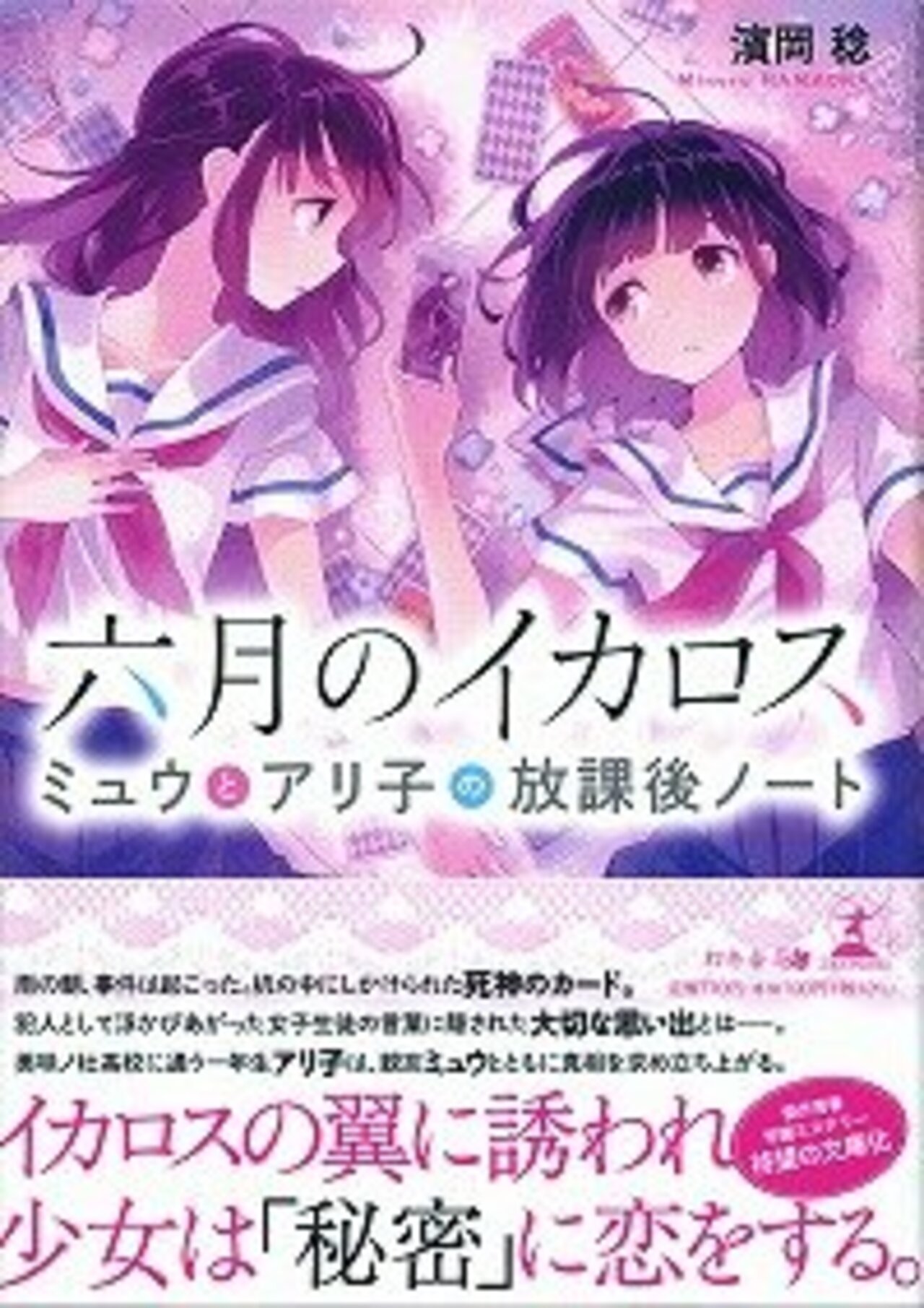とにかく、ポーのなかには、ディケンズの作品に対する共鳴と反発が同時に存在していて、そのアンビバレンスが『バーナビー・ラッジ』に対する辛口な評価にあらわれているとぼくは感じます。
特に、今ならルール違反と批判を浴びそうなトリックへの言及には、秀逸なトリックで先を越された悔しさとともに、そのトリックが冗長で緩慢なストーリーに埋没してしまっていることへの不満、俺ならこのトリックを使ってもっと見事な探偵小説を仕立ててみせるのに、というポーの歯がみするような思いがにじみでているように思います。
ただ、一方のディケンズはというと、謎解き要素にこだわりながらも、ポーが構築したような純粋な推理への奉仕をめざす小説への興味は最後まで希薄だった、というより、まさにその部分でポーとはめざすものがちがった、と言うべきではないか。
ディケンズにとっては、人間という存在こそが最も不可解な謎で、そこから切り離された純粋な知的遊戯としての謎解きは、そもそも彼のめざすものではなかったのだと思います。
ウィルキー・コリンズの『月長石』への対抗心から生まれたとされる『エドウィン・ドルードの謎』にしても、ディケンズが『月長石』ばりの本格的な長編ミステリイに挑んだ、というのとは、少しちがうのではないでしょうか。
ディケンズは、謎解き興味が先にあって物語がそこに付随する、というミステリイの構造を、小説的な〝転倒〟とみなしていたと思います。ディケンズの『月長石』への不満も、まさにそこにあったのではないか。
謎が物語に奉仕するのではなく、物語が謎に奉仕している――だからこそ『月長石』は、本格的な長編探偵小説の古典としての地位を得ているわけですが――そうした〝 転倒〟への抵抗――異議申したてを自身の作品で示すこと。それこそが、ディケンズを『エドウィン・ドルードの謎』執筆に駆り立てた思いの本質ではなかったのか。
人間とは何者なのか。わたしはだれなのか。あなたはだれなのか。なぜわたしたちは、この世界に囚(とら)われているのか――ディケンズの膨大な作品群がわたしたちに投げかける謎は、永遠に繰り返されるその問いとひとつのものなのだと常に感じます。
よけいな説明が長くなりました。いちいち本気にする必要はありません。
だいいち、他人(ひと)さまに自慢できるほどきちんと系統だててディケンズを読んできたわけではありません。研究家が聞いたら、たぶん鼻で笑う程度の戯(ざ)れ言です。
なにより、いちいち話が冗漫になるのは、老化を示す顕著な兆候ですね」
そう言って先生は笑った。
👉『〈ひまわり探偵局番外編〉 ひまわり坂で待ってる』連載記事一覧はこちら