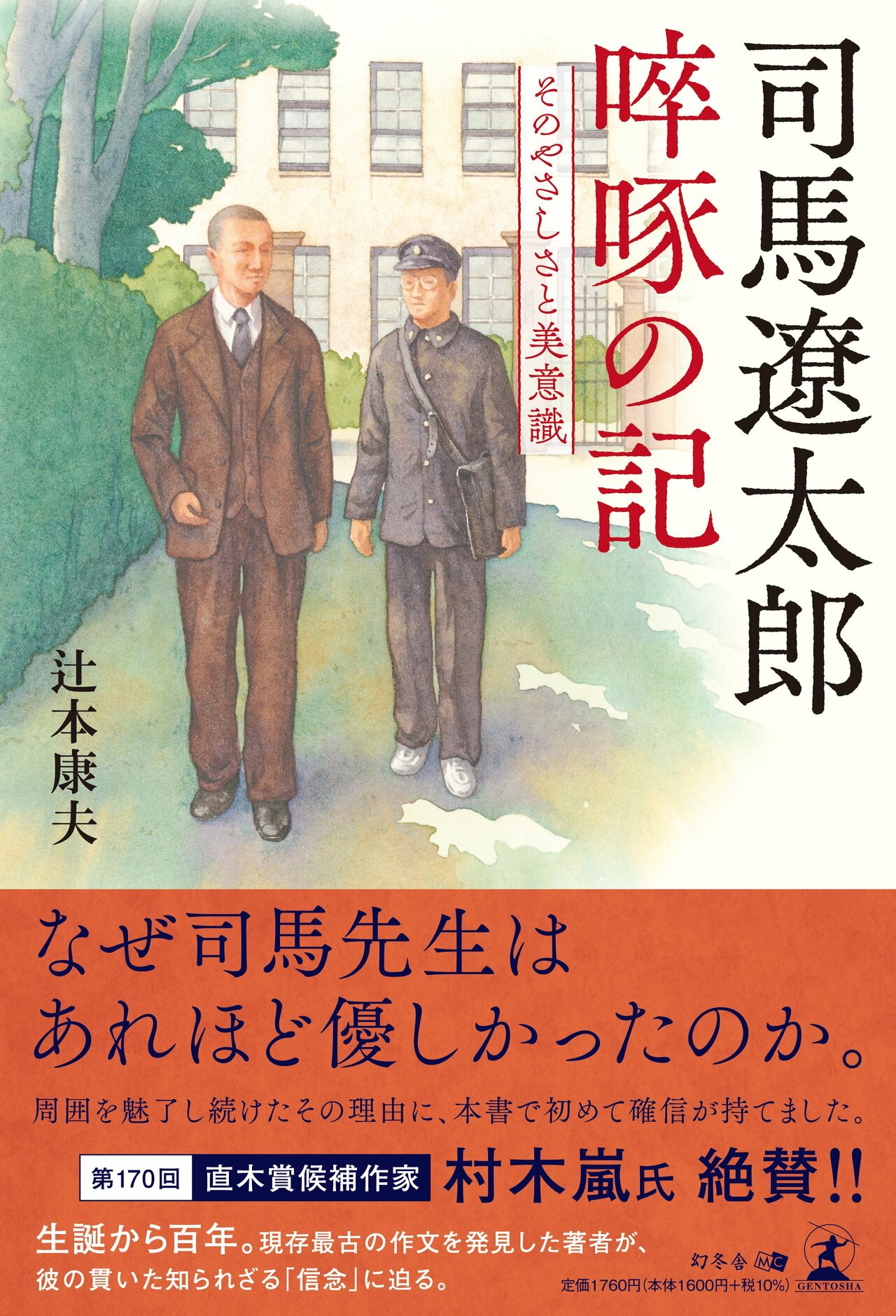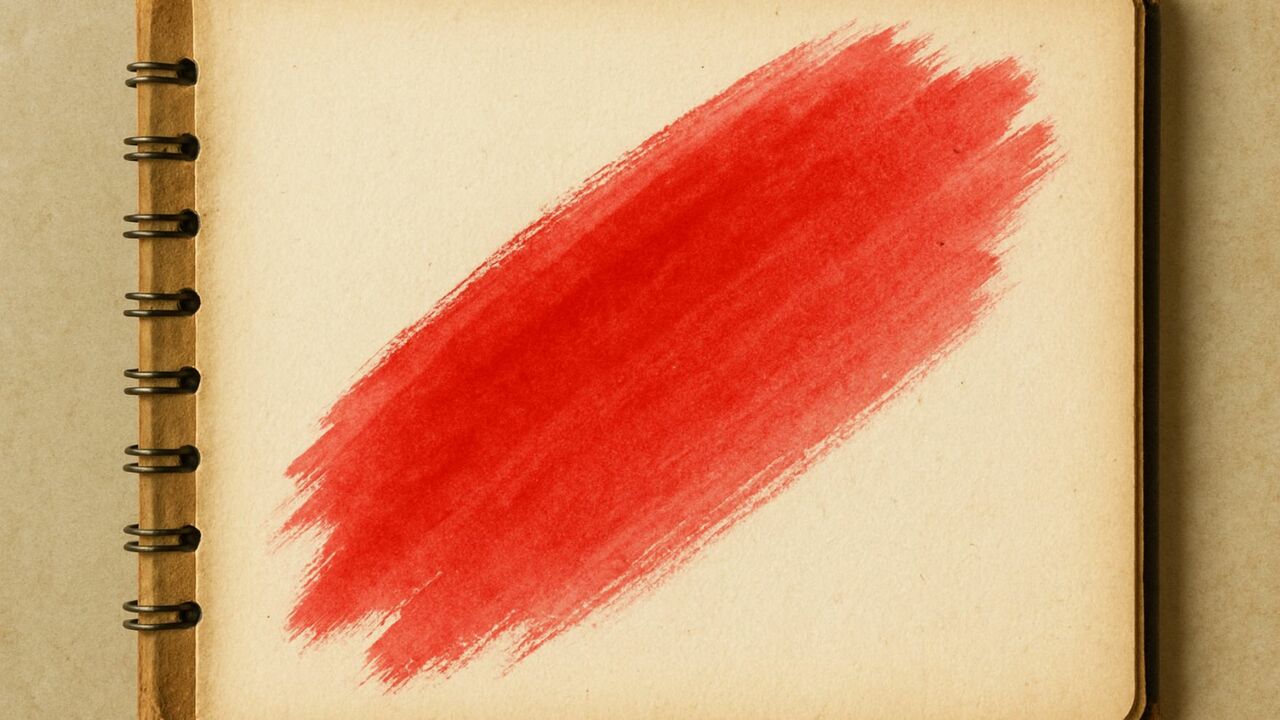四年以上古いはずの第30号がほとんど劣化が進んでいないことを考えると、この四年間に日本に何があったのかと思わざるを得ないような状態です。
考えられる理由はただ一つ。第30号と第36号の間の四年間の間に印刷用紙が非常に質の悪いものになっていたということです。
しかし、第36号が出版されたのは昭和十六年三月ですから敗戦直前ではなく、太平洋戦争が始まる九か月も前のことなのです。いくら物資を統制していたといっても、開戦前でこの紙の状態とは驚かざるを得ません。
紙の質でいえば、もう一つ忘れられないことがあります。上宮学園は敗戦から六年間、校舎をGHQに陸軍病院として接収されていた時期があることは先にも述べました。
その後、サンフランシスコ講和条約の締結によって、やっと返還されることになりましたが、一緒に米軍が寄贈していったものがありました。
EM(エデュケーション・マニュアル)というアメリカの国防総省が作った小冊子です。これが作られた当時はまだ戦争中でしたが、
やがて戦争が終わって母国に帰還するであろう若い兵士たちのために作られた、様々な職業を紹介する冊子でした。それらが上宮学園に寄贈されて、百冊ほど残されていました。
このEMは校友会雑誌とほぼ同じ体裁のものですが、まったくといってよいほど経年劣化していません。戦時中の経済レベルの差という以上に、戦時中であるにもかかわらず、戦後を想定したこんなものまで作っていたことに驚いた記憶があります。