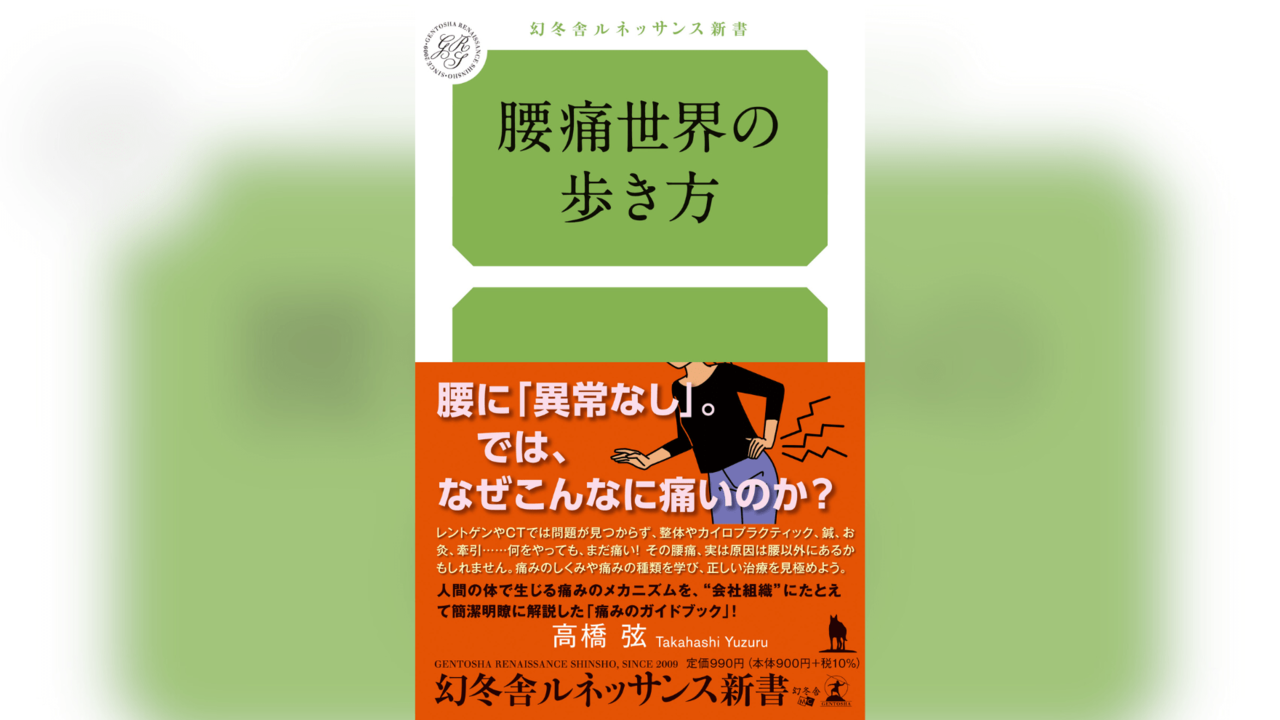【前回の記事を読む】IASP(国際疼痛学会)の痛みの定義「実際の組織損傷」、「組織損傷が起こりうる状態」、「付随する」、「似た体験」とは?
第1章 痛みのしくみ
痛みとは? 〜専門家の定義〜
感情、気分などとの使い分けは明確ではありません。疼痛学ではやはり限定的に用いています。すなわち、恐れ、恐怖、不安などの「負の情動、不快情動」のことであり、動悸や血圧上昇などの自律神経系反応を伴う場合もあります。
「痛みの情動面」とは、痛みが「どのように」感じられているか、ということです。情動が脳でどのように生じるかについては、神経科学の研究が盛んに行われています。特に不快情動のひとつである恐怖については多くのことが解明されています。
〝純粋な情動〟である恐怖や不安は特定の身体部位に現れません。それに対して、痛みは体の特定の場所に限定して現れます1。つまり痛みは明らかに感覚としての要素があり、それゆえ痛みは「感覚であり、情動である」とされるわけです。
逆に情動を伴わない「痛みのような」感覚もあります。「違和感」などと言語表現される身体感覚の多くは情動を伴いません。「失感情症」という疾患が知られています。
この疾患の患者さんは「体が痛い」と訴えても、ふつうの人に認められるような、痛みに随伴する感情の表出が極めて乏しいかまったく見られません。まったく情動的な体験をしていないならば、定義上は痛みではないということになります。このように痛みは「感覚かつ情動である」のです。
「不快な」:
IASP定義では、痛みは常に不快であると宣言しています。一方、痛み体験を快感と感じる人や、宗教の戒律や儀式のなかには至福感を求めてわざと体を痛める場合もあります。そのような人々が体験しているものは痛みといえるのか?
「不快ではない」「治療が求められていない」という点で、臨床医学的には痛みとはいえません。苦しいけれども不快ではない。「苦行」といわれるゆえんです。
「体験」:
疼痛科学の研究により、痛みの原因となる感覚と情動が身体内部で生じていても、それに気づかない場合があることが明らかになりました。痛みを体験するためには意識があることが必要条件です。睡眠中や麻酔下には痛みは体験されません。この場合は「心は痛みに気がついていない」のではなく「痛みは存在しない」のです。
疼痛学では痛みをこのように定義し、この定義に該当する事象や症状だけを研究と医療の対象とします。これにより、「心の痛み」は精神医学の研究領域とされ、「社会的痛み」は社会学の領域になります。
ところで、とても興味深いことに最近の疼痛科学の研究から、傷ついて苦しんでいる他者を見たときに活動する脳の領域が、本人の体の痛みを知覚したときと同じであることが明らかになってきました。
共感により起こる「心の痛み」や「社会的痛み」も、脳からみれば同じなのかもしれません。そのような体験を「痛み」と表現するのは神経科学的に見れば理にかなっているといえるでしょう。