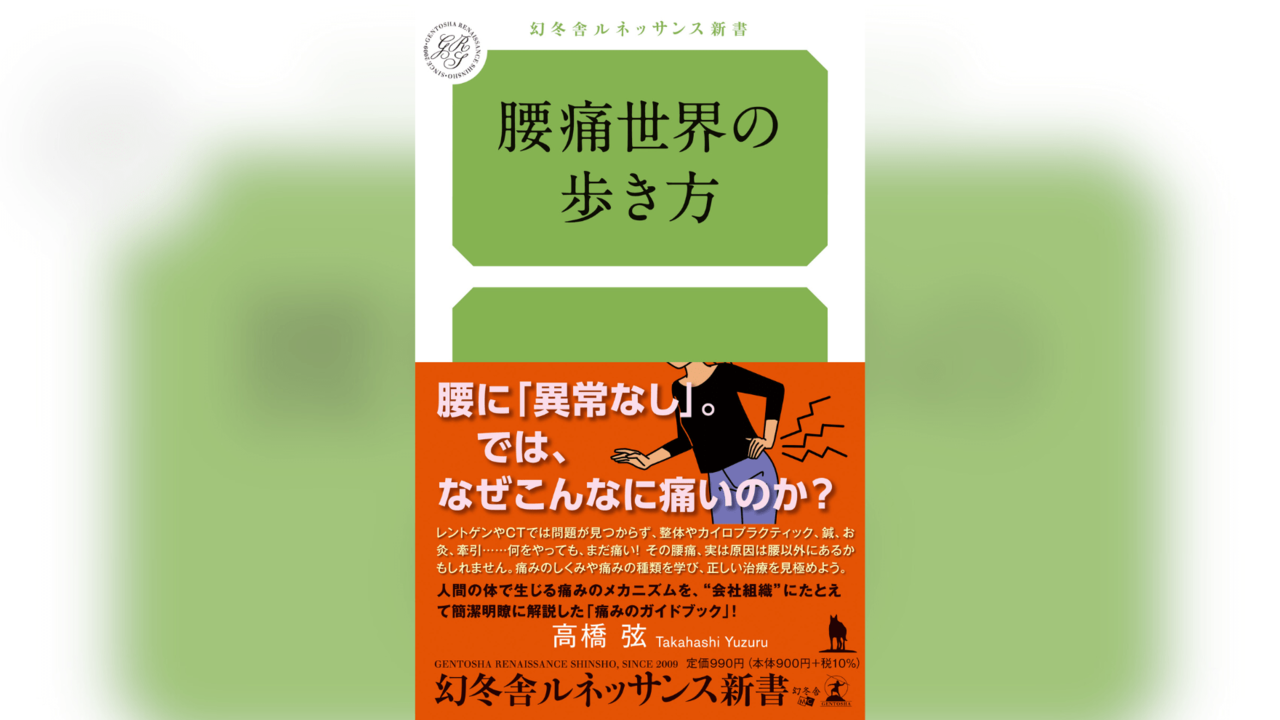【前回の記事を読む】興味深い近年の疼痛科学研究――共感により起こる「心、社会的痛み」は本人が体の痛みを知覚したときと同じ脳の領域で起こる
第1章 痛みのしくみ
研究史 〜むかし痛みは情動だった〜
神経が刺激をとらえることを「感覚受容」といい、感覚受容をする構造物を「感覚受容器」といいます。感覚受容器とは専門的には「レセプター」「センサー」といいます。人工的な光センサー、音センサー、タッチパネルセンサーと同じ機能です。
光の感覚受容器は目、音は耳、匂いは鼻、味は舌、というのは太古から自明でした。しかし、先にもあげたように触覚と痛みの感覚受容器は肉眼では見えないので、その構造と機能がほぼ解明されたのは、これも20世紀のことでした。
痛みとの関連では、次節にあげるように組織損傷を起こす可能性をもつ刺激を「侵害刺激」と呼びます。侵害刺激の感覚受容のしくみについて、かつては「強度説」と「特殊説」の両方がありました(2)。
強度説とは「どのような種類の感覚刺激であっても刺激の強度が一定以上になれば痛みとして感じられる。侵害感覚を受容する特別な感覚受容器は存在しない」という説です。
特殊説とは「侵害刺激専門の感覚受容器が存在している」という説です。結局、軍配はひとまず特殊説にあがりました。「侵害受容器」が発見されたからです。侵害受容器の研究は痛みの医学を大きく進歩させました。
こうして痛みは感覚の一種であることが明確になりました。しかし、痛みは常に不快な情動体験を伴うことから、IASPの定義にもあるように情動としての側面ももつことも、依然として認識されています。
むしろ現在の疼痛学と疼痛科学の研究は、どちらかというと神経系における痛みの情動面のメカニズムをテーマにしたものが主流となっています。