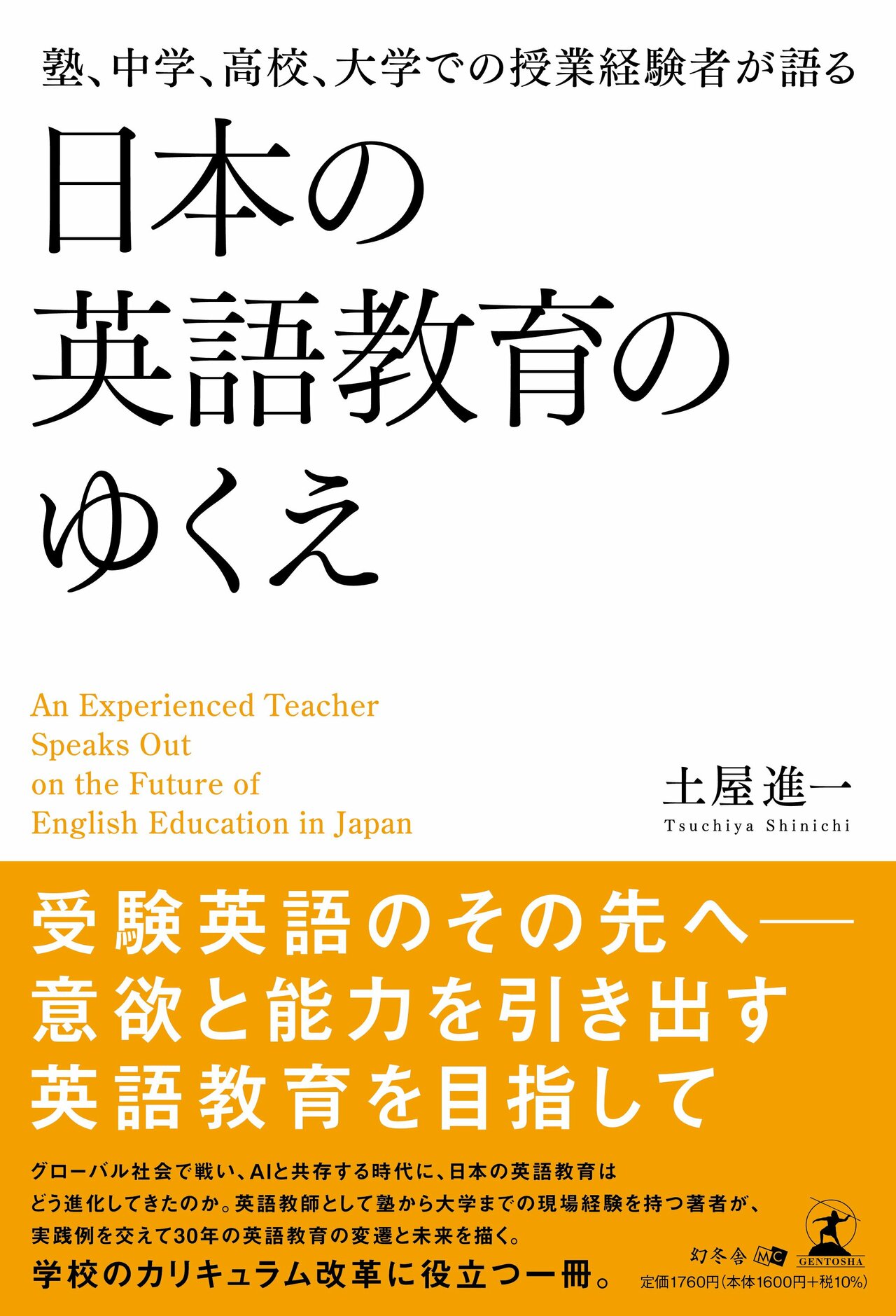この方法は、英語の文法や構文の理解を深めるためには有効でしたが、コミュニケーション能力の育成にはほとんど寄与しないという課題がありました。
この時代は、教師が一方的に知識を伝える形式が主流であり、生徒たちは英語を話すことはほとんどなく、静かに教師の解説を聞くことが常でした。
教師もほとんど英語を話さず、授業展開は、日本語で解説をするのが一般的で、教師が黒板に文章を書き、色チョークを用いて、名詞や形容詞、副詞などの品詞、句や節をカッコでくくり、色分けしながら、一つ一つ丁寧に解説し、生徒たちはそれをノートに書き写すという形が一般的でした。
教師の役割は、文法事項の解説や訳読の技術を教え、生徒たちが正確に訳すことができるように指導することでした。その点においては、英語の流暢さよりも日本語の「流暢さ」が、当時の英語教師に求められていたことかもしれません。
実際に、当第1章 「読んで訳して」文法訳読の1990年代時の教室では、「先生、もう一度訳を言ってください」という生徒の発言が多く、教師の一度目の訳と二度目の訳が少しでも異なると、生徒が教師をとがめる姿をよく目にしました。
このように、英語の授業でありながら、生徒は、英語よりも教師の言う和訳を書き取るのに躍起になって日本語を話したり書いたりすることが常である授業でした。
【イチオシ記事】一通のショートメール…45年前の初恋の人からだった。彼は私にとって初めての「男」で、そして、37年前に私を捨てた人だ
【注目記事】あの臭いは人間の腐った臭いで、自分は何日も死体の隣に寝ていた。隣家の換気口から異臭がし、管理会社に連絡すると...