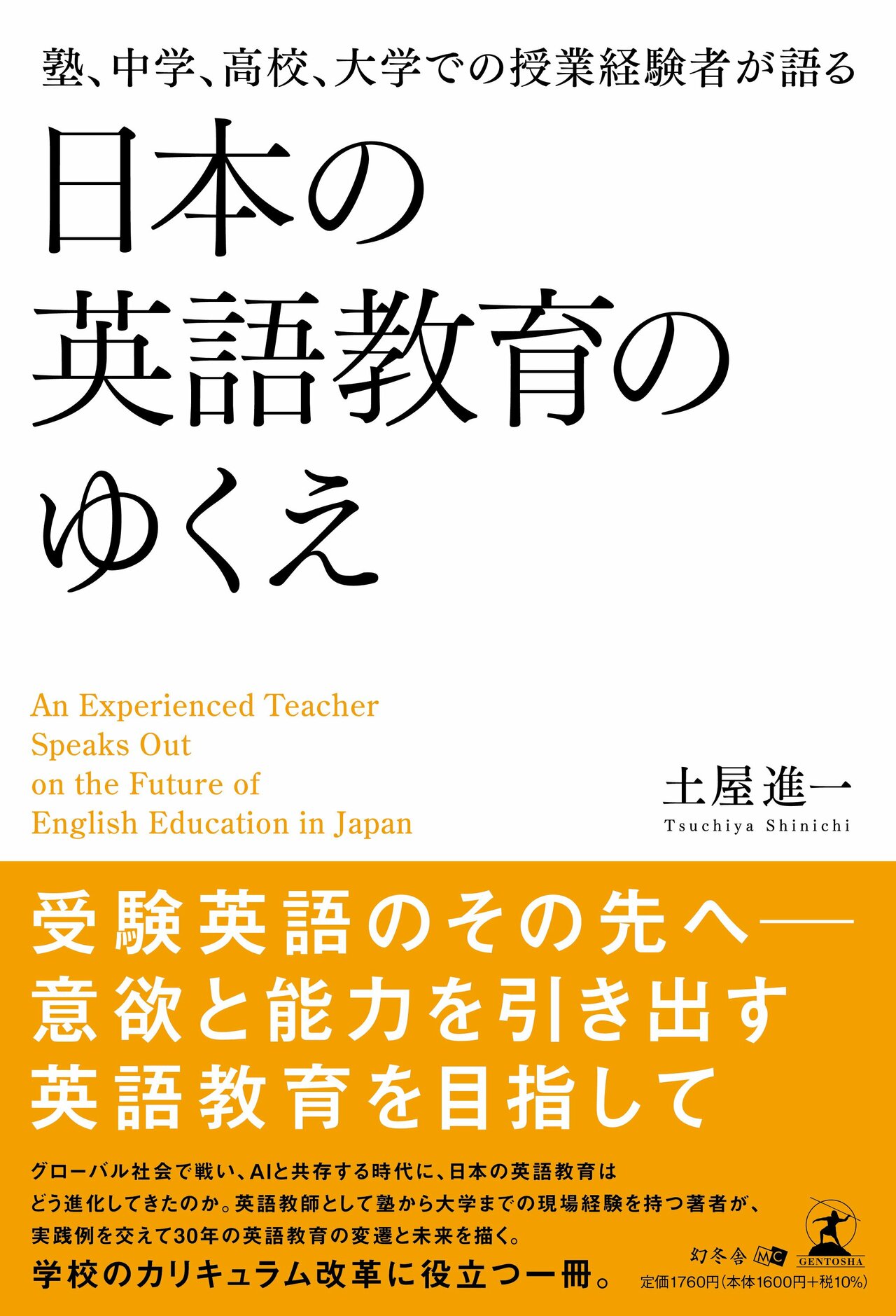第一部 英語教育 30年の変遷
第1章 「読んで訳して」文法訳読の 1990年代
日本における1990年代とそれ以前の英語教育は、特に高等学校において、文法訳読法が主流でした。
この教授法は、テキストの英文を読み、その内容を日本語に訳すことに主眼が置かれていました。教師は授業時間の大半を英文の構造分析と文法解説に割き、生徒は文法的に正しい和訳を通じて英文を解釈することが求められました。予習として、図1のようにノートの見開きの左側に教科書本文の英文を手書きで書き写し、右側に和訳を書いてくるのが一般的でした。
これは、英語の文章を構文・文法に基づいて正確に理解し、日本語に訳す能力が評価の基準となっていたためです。実際に、当時の大学入試問題もそのような英文和訳の形式の出題が圧倒的に多かったのも事実です。
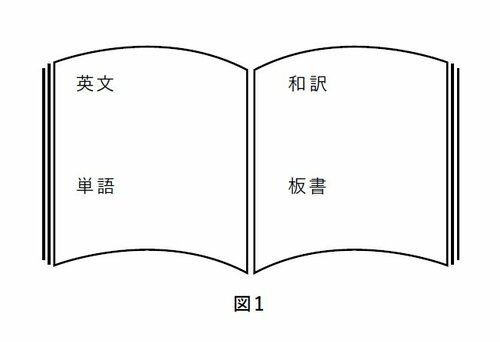
当時の教科書や教材は、難解な文法事項や語彙を含んだ抽象的な文章が多く、このような英文を徹底的に解析し、理解することが英語学習の中心でした。
生徒たちは授業中に教師の模範音読もないまま英文を「音読」させられ、事前に予習してきた和訳(試訳)を発表することが求められました。たいてい、机の並び順か出席番号順に指名されることが多く、きちんと予習してきた生徒が、予習してこなかった生徒に直前にノートを貸し、難を逃れるという悪行が横行していました(私はノートを貸す生徒でした)。