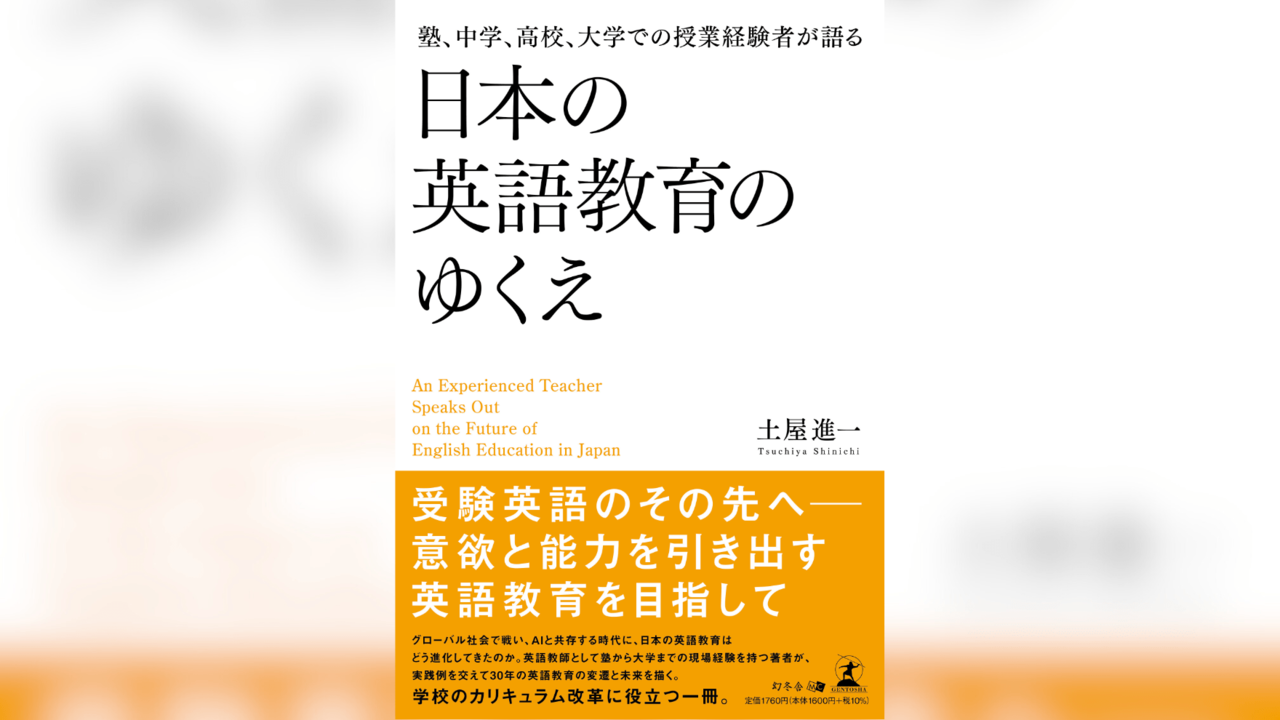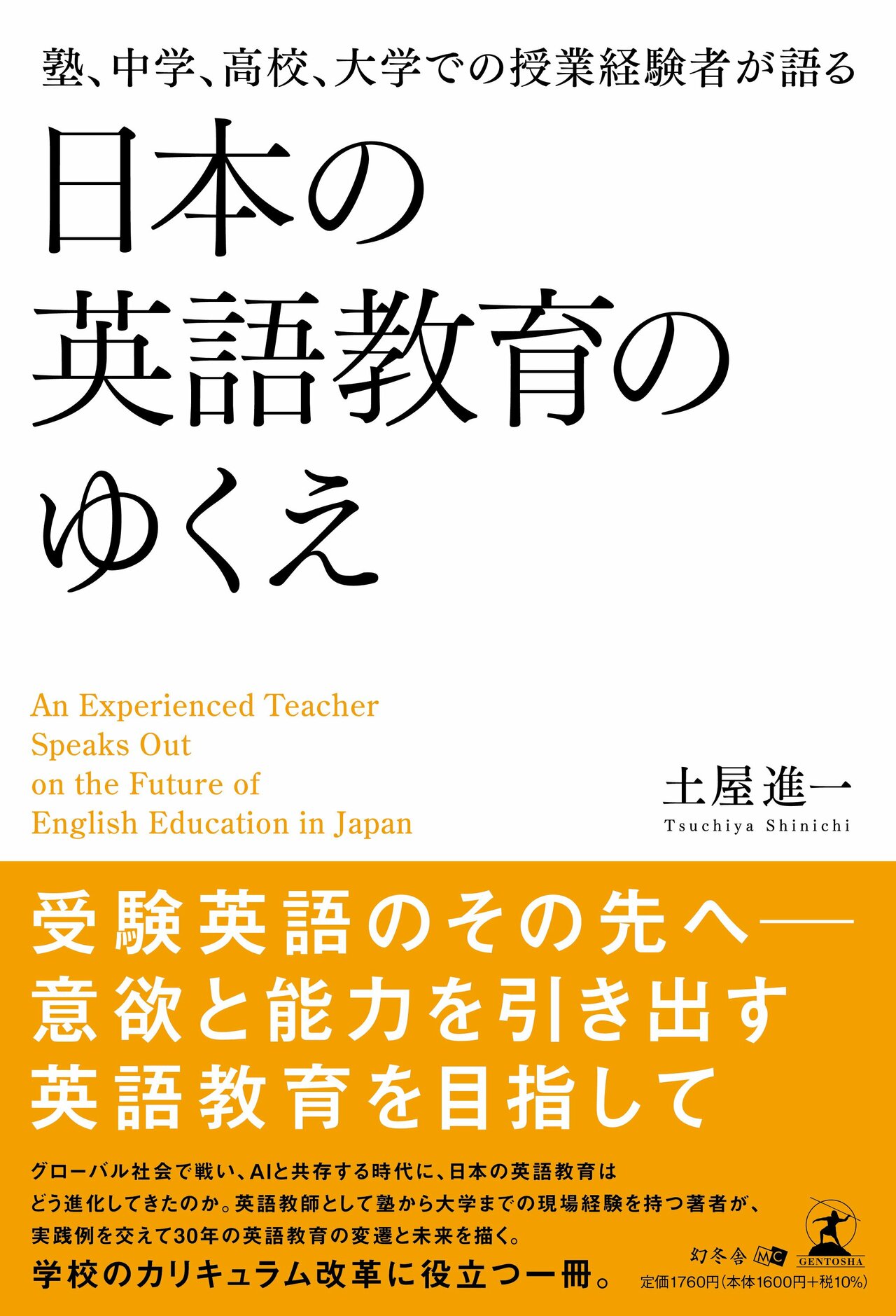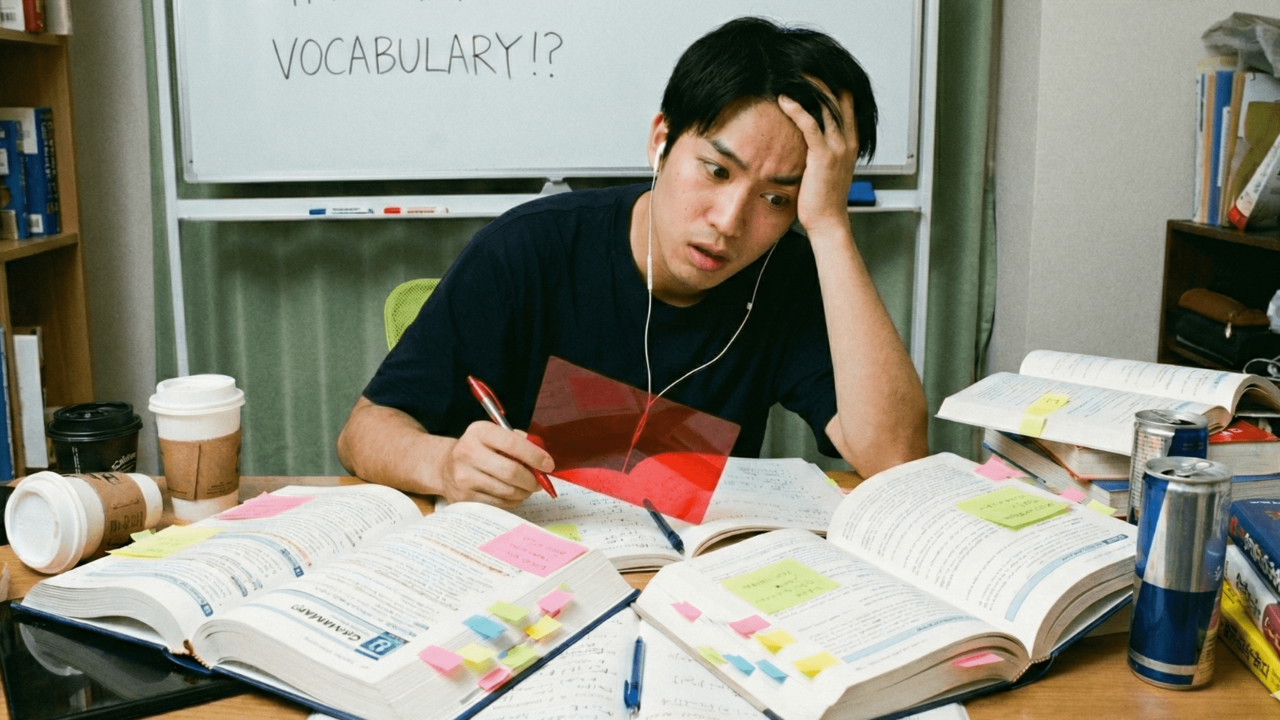【前回記事を読む】2000年代における英語教育の変化と進展。記憶の定着や音声の改善につながる「音読」重視の指導法とは?
第一部 英語教育 30年の変遷
第2章 「訳して読んで」音読重視の2000年代前半
第1節│Oral Approachの導入
日本では、Oral Approachは1950年代から1960年代に中学校で導入され、多くの英語教育現場で実践されましたが、第1章でも述べたように、高等学校では文法訳読法が中心であまり多くの実践は見られませんでした。
Oral Approachは、音声重視の教育法として、英語の発音やリズムを重視することが求められ、初級者が口頭でのコミュニケーション能力を身につけるための土台を形成しました。Oral Approachの主な特徴には、音声的側面に重点を置き、リピーティングやオーバーラッピングなど、音を通じて言語を学ぶことを促進する点が挙げられます。これにより、学習者は自然な発音やイントネーションを身につけることができます。
また、特定の文法構造を反射的に使えるようにする目的もあり、実生活に即したタスクやシチュエーションを用いて、学習者が英語を使う機会を多く提供することで、教室内での学びを日常生活に応用しやすくします。
Oral Approachは特に初級者向けの授業で効果的です。教師は簡単なフレーズを繰り返し、学習者に音読させることで、音声の流れやリズムを身につけさせます。さらに、グループ活動やペアワークを通じて、学習者同士が自由に会話を交わす時間を設けることで、実践的な言語運用能力を高めます。
このように、Oral Approachは言語学習の初期段階において、言葉を生きたものとして捉え、実際に使うことを重視するアプローチです。この方法を取り入れることで、学習者は言語をより自然に、そして効果的に習得できるようになります。次節では、このアプローチが音読重視の教育方法とどのように関連しているかについて詳しく見ていきます。