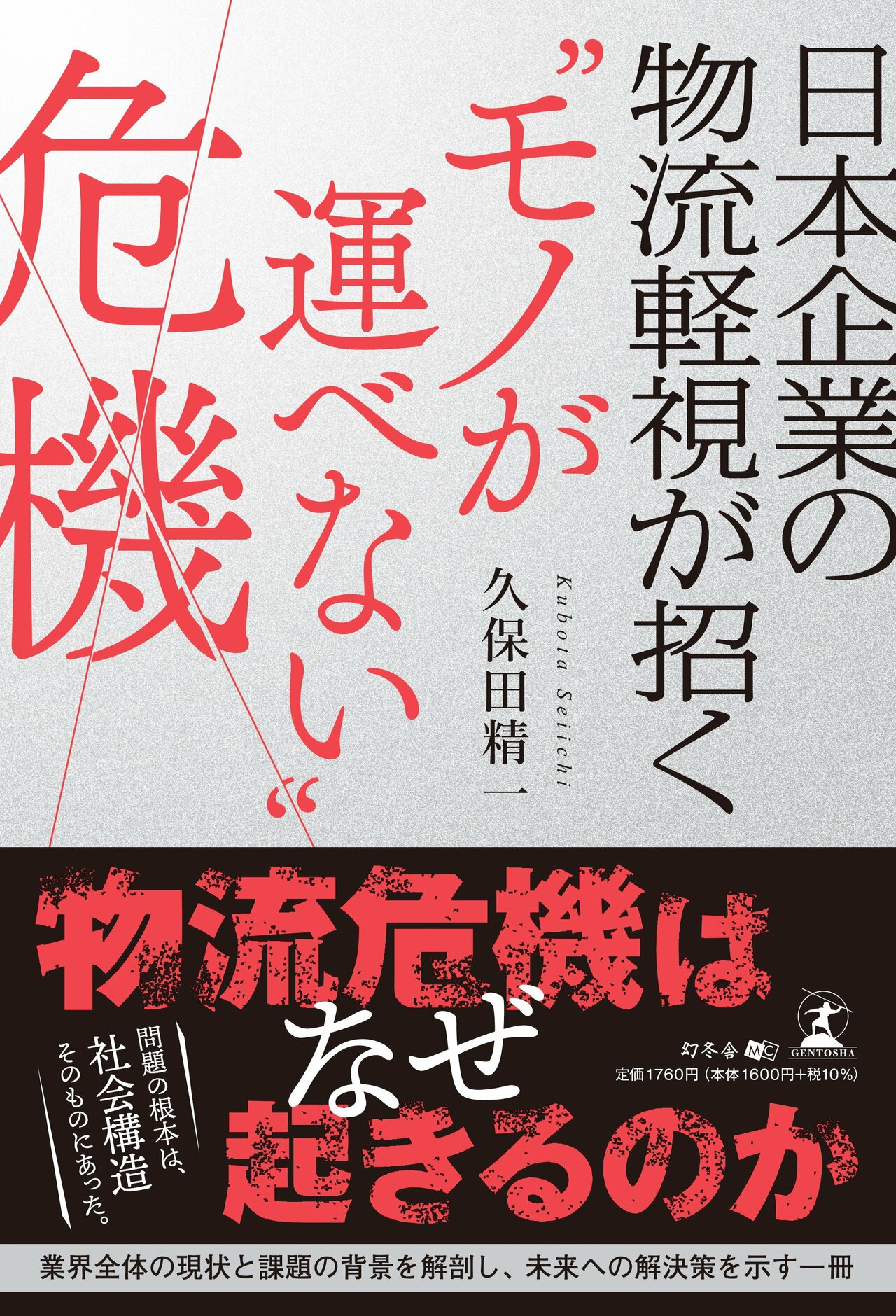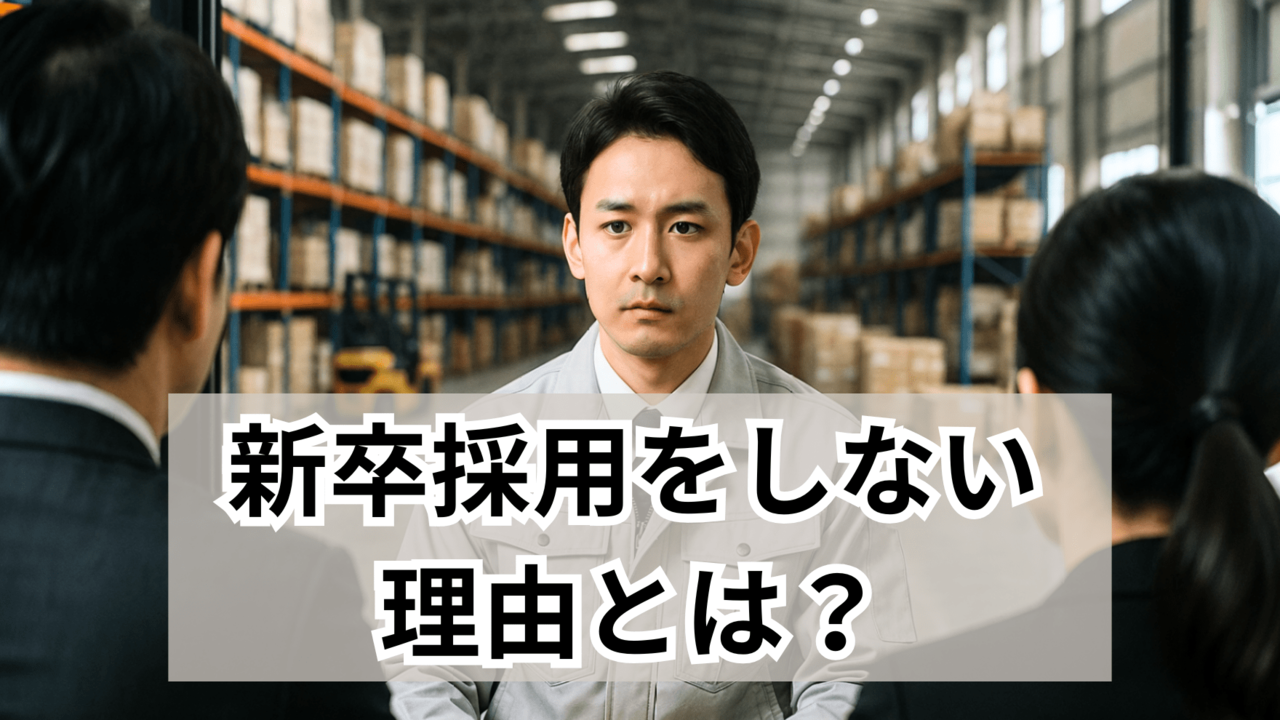2‐4 リストラ対象と見なされる物流
バブル崩壊後から続いた「失われた30年」は、日本経済が苦境に見舞われ、企業がリストラを繰り返した期間であった。リストラの対象は、現場の非正規雇用の雇い止めから始まり、後に間接部門を含む正社員の解雇へと拡大した。
リストラが拡大する過程では、残念ながら物流部門もその例外ではなく、むしろ格好のターゲットになったようにも見える。
企業にとってリストラは、「コア領域」と「ノン・コア領域」との選別を迫られる作業でもあるが、この間に物流部門が経験した経緯は、企業の経営判断における物流軽視の傾向を浮き彫りにしているように思える。
なお、物流を含む間接部門のリストラは、企業が公表しない限り外部からは実態を把握しにくい。しかし物流部門については、特に大手製造業を中心に子会社化しているケースが非常に多い。
その「物流子会社」の変動を見ていくことで、この間のリストラの実態を浮かび上がらせることができる。
そこでここでは物流子会社を中心として、不況期における企業の対応の経緯を振り返ってみることとしたい。
元々は物流管理高度化が目的だった物流子会社の設立
物流子会社とは、メーカー等の荷主企業が、主として自社の物流を担わせることを目的に新設したり、または自社の物流部門を分社化したりして設立する子会社である。
物流子会社の例は数え切れないほど挙げられるが、例えば日本製鉄子会社の「日鉄物流」、日本製紙子会社の「日本製紙物流」のように、親会社の社名に「物流」や「ロジスティクス」を加えた企業は、基本的に物流子会社である。
物流子会社の設立は、1970年代の高度成長期前後に急速に広がり始め、概ね80年代にピークを迎えるが、この時期は、物流管理の普及期とも重なる。
アメリカからもたらされた「物流」の概念は、70年代に日本国内に急速に普及していく。それまで企業は、「輸送」「倉庫保管」などをバラバラに管理していたが、これらを「物流」として統合的に管理する必要性が、広く共有されるようになったのである。
物流子会社の設立も、そのような文脈に位置づけられる。大手製造業では、輸送や倉庫保管などの物流関連業務を多くの事業部で抱えていた。
トラックの手配などもかつてはバラバラに実施していたのだが、このように分散していた物流関連業務を、新たに設立した物流子会社に統合することで、物流効率化を図ることができた。
物流には経済学で言うところの「ネットワーク効果」によるスケールメリットが働く。そのため、物流管理を統合化することで、物流効率化とコスト削減が実現できたのである。
これに加えて、物流品質やサービスレベルが高まる効果も生じた。物流を専門とする子会社に管理を統合化することで、誤出荷を無くすなど管理レベルの高度化も実現できたのである。
このように当時の経緯を振り返ると、物流管理を高度化・効率化するためにはその母体組織として物流子会社を設立する必要があったことが分かるだろう。