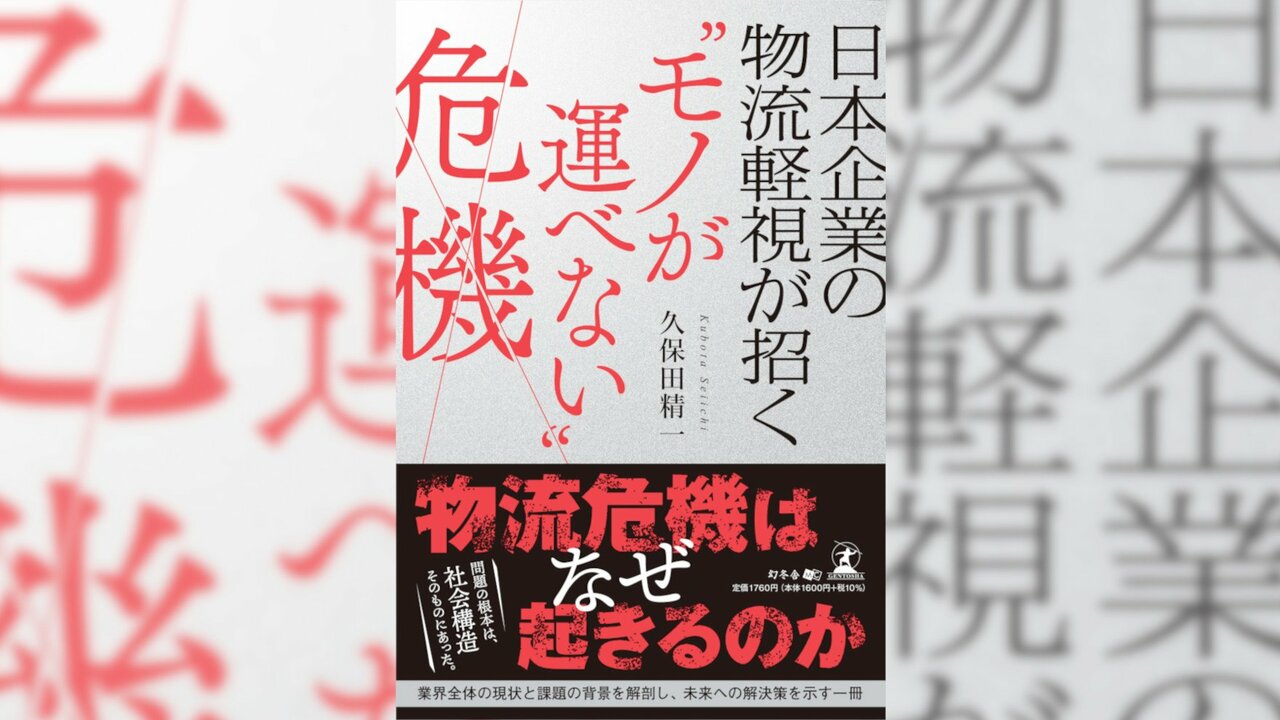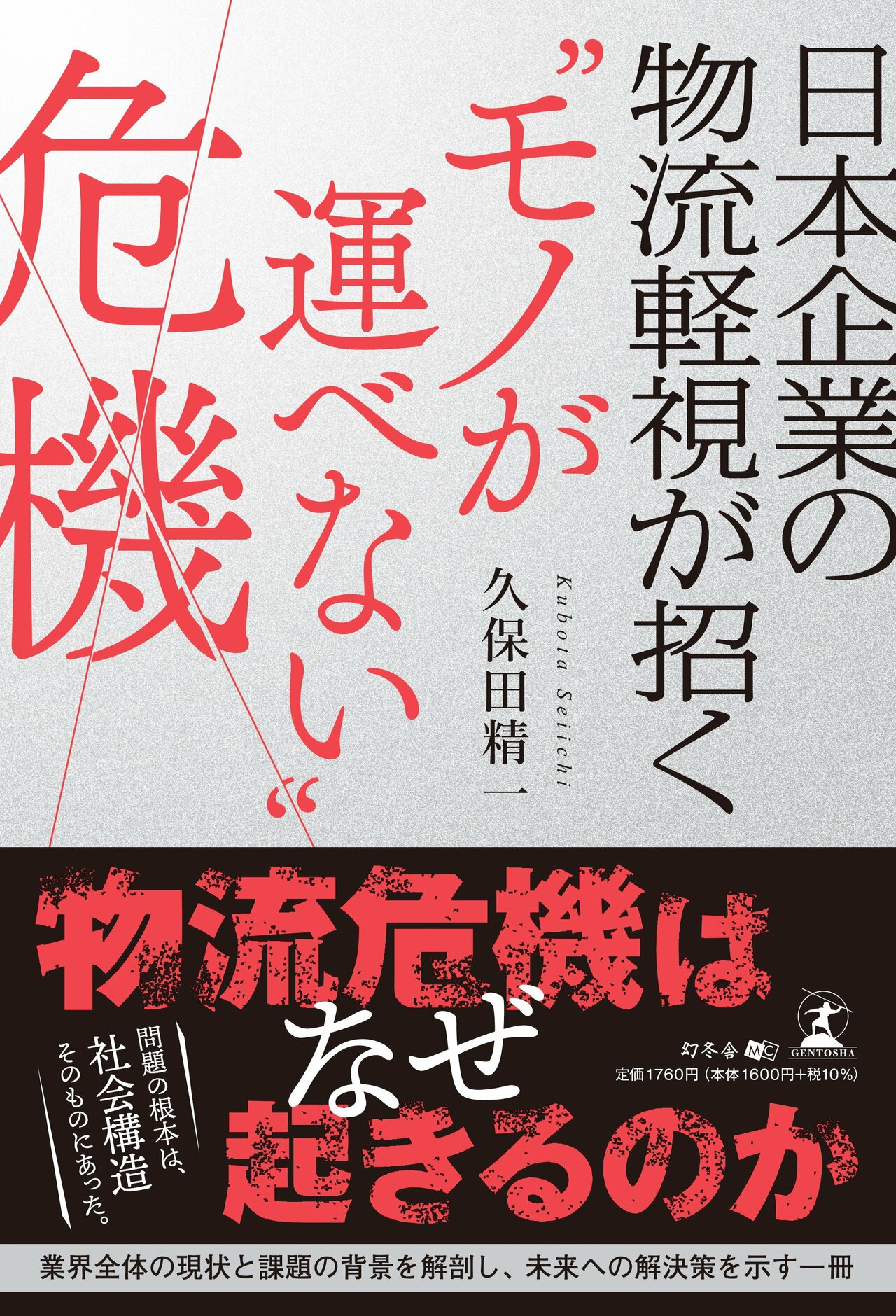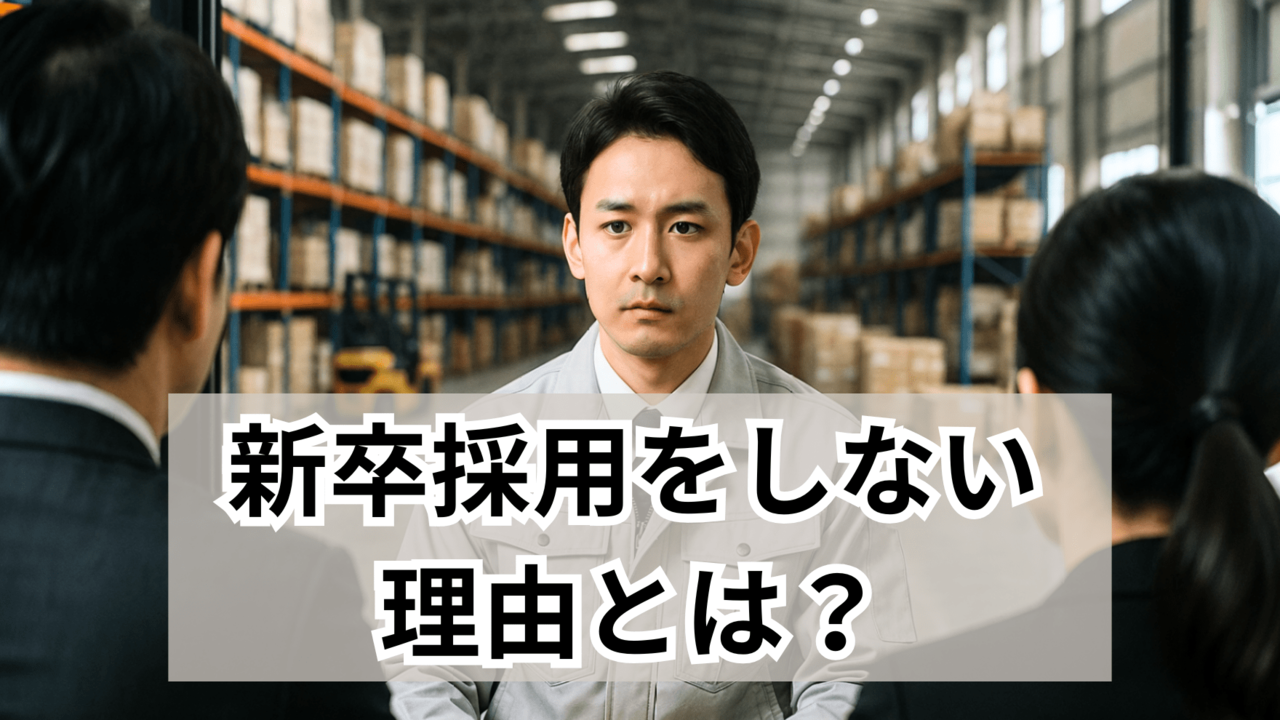【前回の記事を読む】【切られた富士通ロジスティクス】物流子会社売却の動きは、モノづくり縮小に伴う必要性の低下だけで読み解けるか
第2章 物流・SCM軽視の実態
2‐4 リストラ対象と見なされる物流
物流を「ノン・コア」と見なす傾向がリストラの背景に
さて、これまで企業が経済的な苦境に陥るたびに、物流はリストラのターゲットとなってきたわけだが、その背景にあるのが、「物流はコアではない」あるいは「本業とのシナジー効果が薄い」といった、偏見である。
企業にとってリストラは、「コア領域」と「ノン・コア領域」との選別を迫られる作業であるが、「物流はコアではない」という見方は、日本企業の中に驚くほど深く根付いている。
コアではない物流を縮小し、場合によっては切り捨てるのは、ある意味では当然のことである。
ただし、物流を当たり前のように「ノン・コア」と見なす傾向は、日本に特有な現象のようにも見受けられる。
グローバル企業の多くが、CSCOを設置していることを紹介したが、それは企業が物流・SCMを競争優位を生む重要な機能であると認識しているからである。
そして、競争優位を生むような重要な機能であれば、外部の物流会社に委ねるのは不適当である。なぜなら、外部委託先に依存する機能によって、戦略的優位性を維持するのは難しいからである。
実際、グローバル企業を見渡すと、物流機能を「自前」に転換する動きが静かに進んでいる。
その最も顕著な例が、アマゾンである。アマゾンは物流拠点を自社管理下で運営し、「アマゾンフレックス」といったマッチングシステムによって軽貨物ドライバーと契約するなどにより、輸送手段の相当量を自社で確保している。
また、物流ロボット企業を買収して傘下に置くなど、物流テクノロジーの囲い込みにも意識的に取り組んでいる。
アマゾン以外の例としては、世界最大の小売業であるウォルマートも、自社流の高度な物流管理で有名である。
ウォルマートは段ボールへの製品の梱包方法から輸送手段に至るまで、様々な物流条件を自社で標準化することで、効率的な物流網を築いていることで知られる。製造業で言えば、コカ・コーラ、ペプシ社等も「自前化」で有名である。