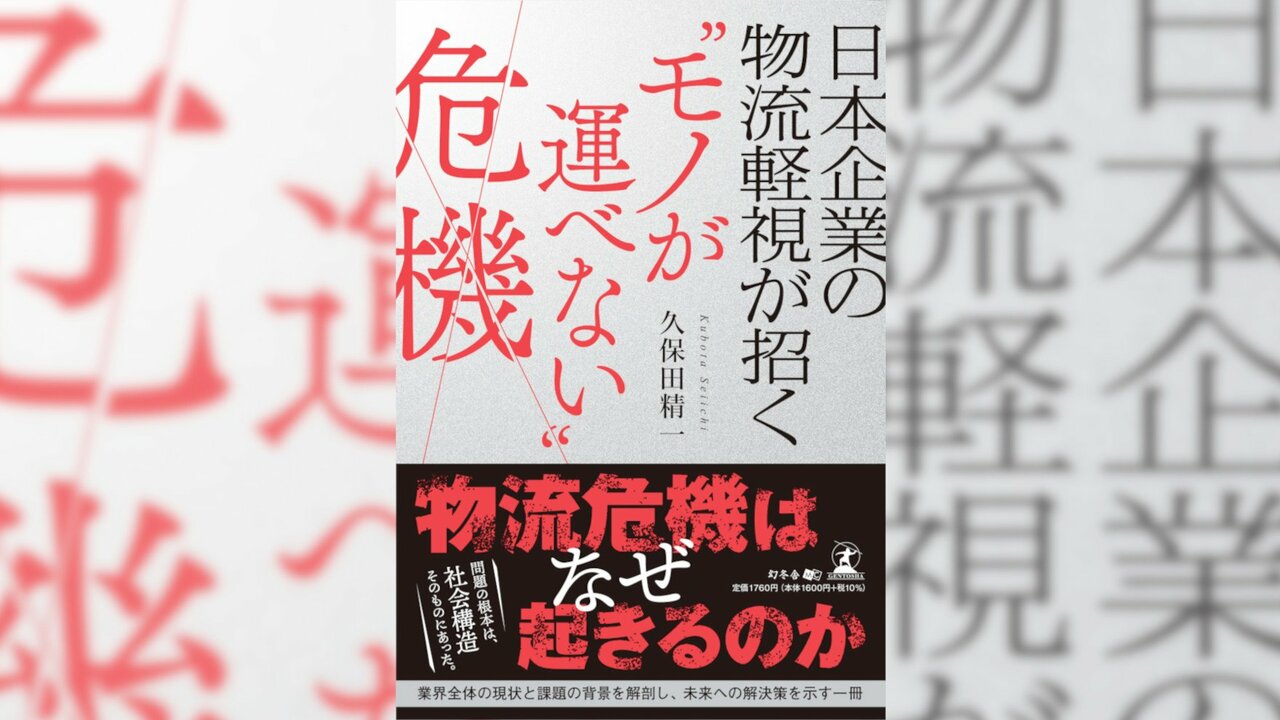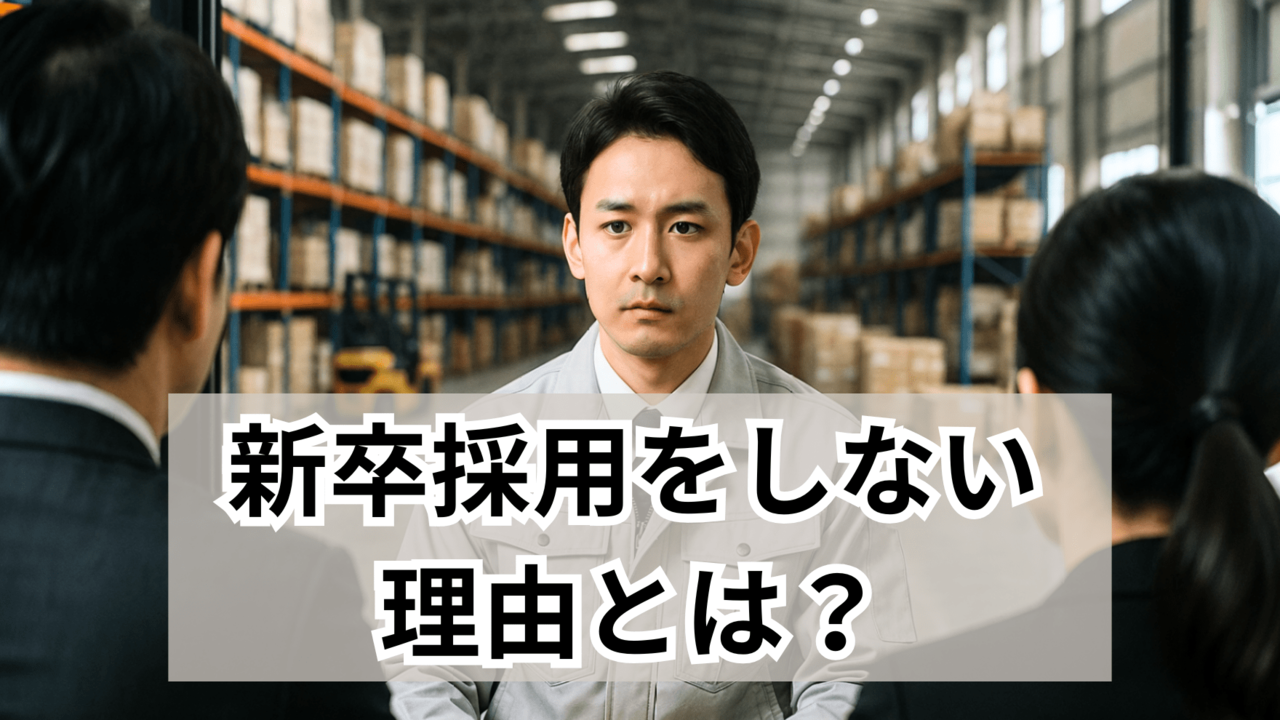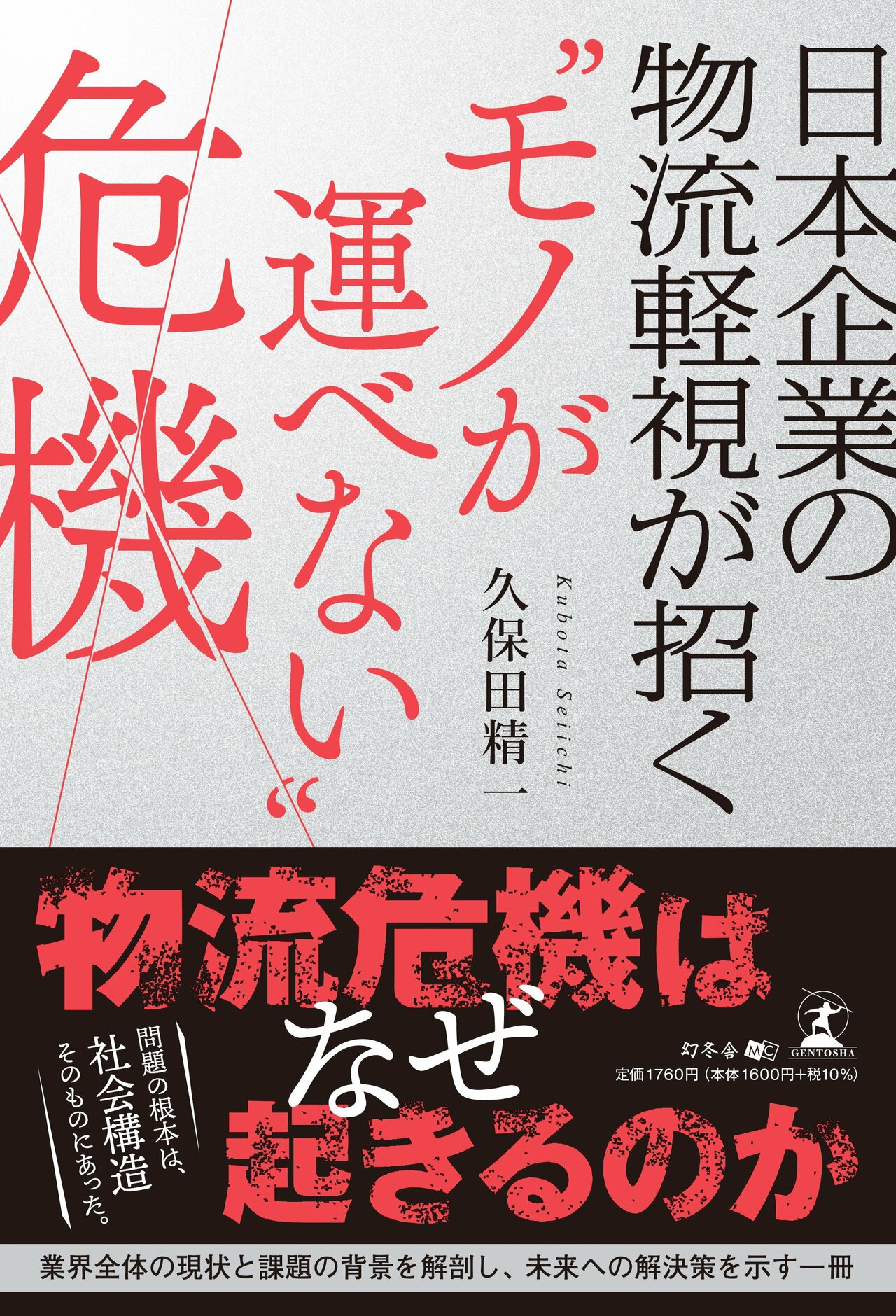【前回の記事を読む】物流は「ノン・コア」ではない! アマゾン・ウォルマート・ユニクロに学ぶ“自前化”と日本企業に迫る構造変化の波
第2章 物流・SCM軽視の実態
2‐4 リストラ対象と見なされる物流
日本国内でも徐々に広がりつつある物流重視への転換
アパレルの売れ行きは流行に左右されるため、在庫管理が難しい。また、他の製品と比べて不良在庫化するスピードが極端に速いため、製品の企画から市場投入までのリードタイムを極限まで短くする必要がある。
それと同時に、工場から店頭までのグローバルな在庫を最適に管理することも求められるのである。
このような高度な管理は、自社内に高度な物流管理機能を持つことでしか実現できない。
ただし、ユニクロも当初から物流が上手く機能していたわけではない。ファーストリテイリング グループ執行役員 神保拓也氏(当時)によると、「(2015年の段階では)物流領域についてはパートナーに丸投げしている状況で、そもそもグループ内で何が起こっているのか把握できていなかった」状況だったというす(注1)。
そのような反省を踏まえて、物流に関する経営管理チームを立ち上げるなどの物流改革に取り組んだ結果、現在のような先進的な物流システムを実現したのである。
このような物流重視への戦略転換は、他のアパレル企業でも進んでいる。三陽商会、レナウン、オンワードといった有名アパレル企業の多くは、かつて物流子会社を保有しており、自社管理下で物流を運営していたのだが、電機各社が子会社を売却したのと同様の時期に、その多くが子会社を売却・廃止してしまった。
その影響もあってアパレル業界では物流は専門会社に任せる流れが主流であったのだが、近年ではユニクロ等の動きに触発されて、物流重視へ転換する企業が増えているのである。
物流重視への転換は、その他の業界でも生じている。その一例は化粧品業界である。化粧品業界では近年、メーカー通販の増大、アジアへの輸出拡大や、医薬品関連の規制強化を背景に、物流の重要性が増している。
一言で言えば、流通ルート・チャネルや商品カテゴリーの多様化が進み、メーカー物流の役割が高まっているのである。
そのため、ファンケルやオルビス、花王などを筆頭に化粧品業界では、高度に自動化された物流システムを構築する動きが進んでいる。また、化粧品最大手の資生堂も、最近、大規模な物流拠点を整備したことで話題になっている。
資生堂はかつて「資生堂物流サービス」という大規模な物流子会社を抱え、先駆的な自社物流を行っていた企業でもある。
その物流子会社も2000年代に売却され、一時は物流アウトソーシングの流れを推し進めていたのだが、昨今の動きからは同社の戦略が転換期に差し掛かっていることをうかがわせる。
これまで見てきたように、日本企業の多くは物流をノン・コアと位置づけ、物流子会社の売却に代表されるように物流機能の外部化を進めてきた。
しかし上記の各社の動向を見ても、「物流はノン・コア」というこれまでの日本企業の常識は、転換点に差し掛かっていると言えるのかもしれない。