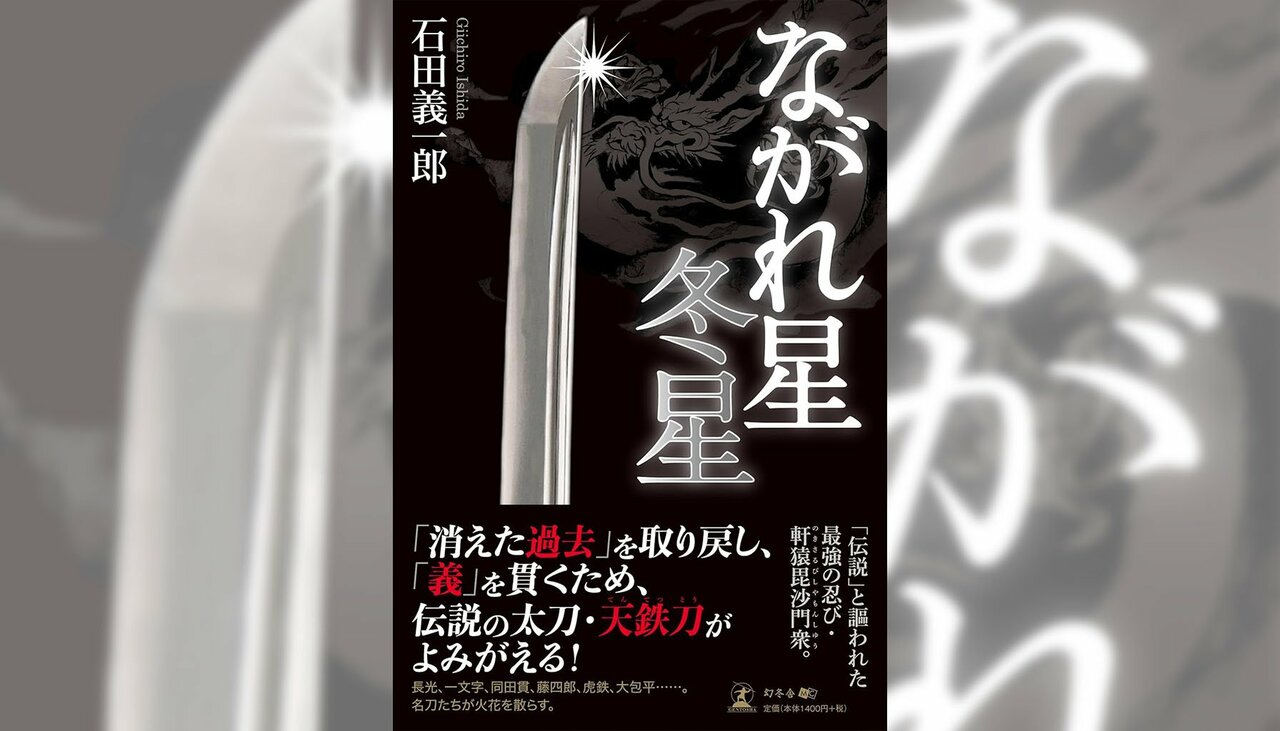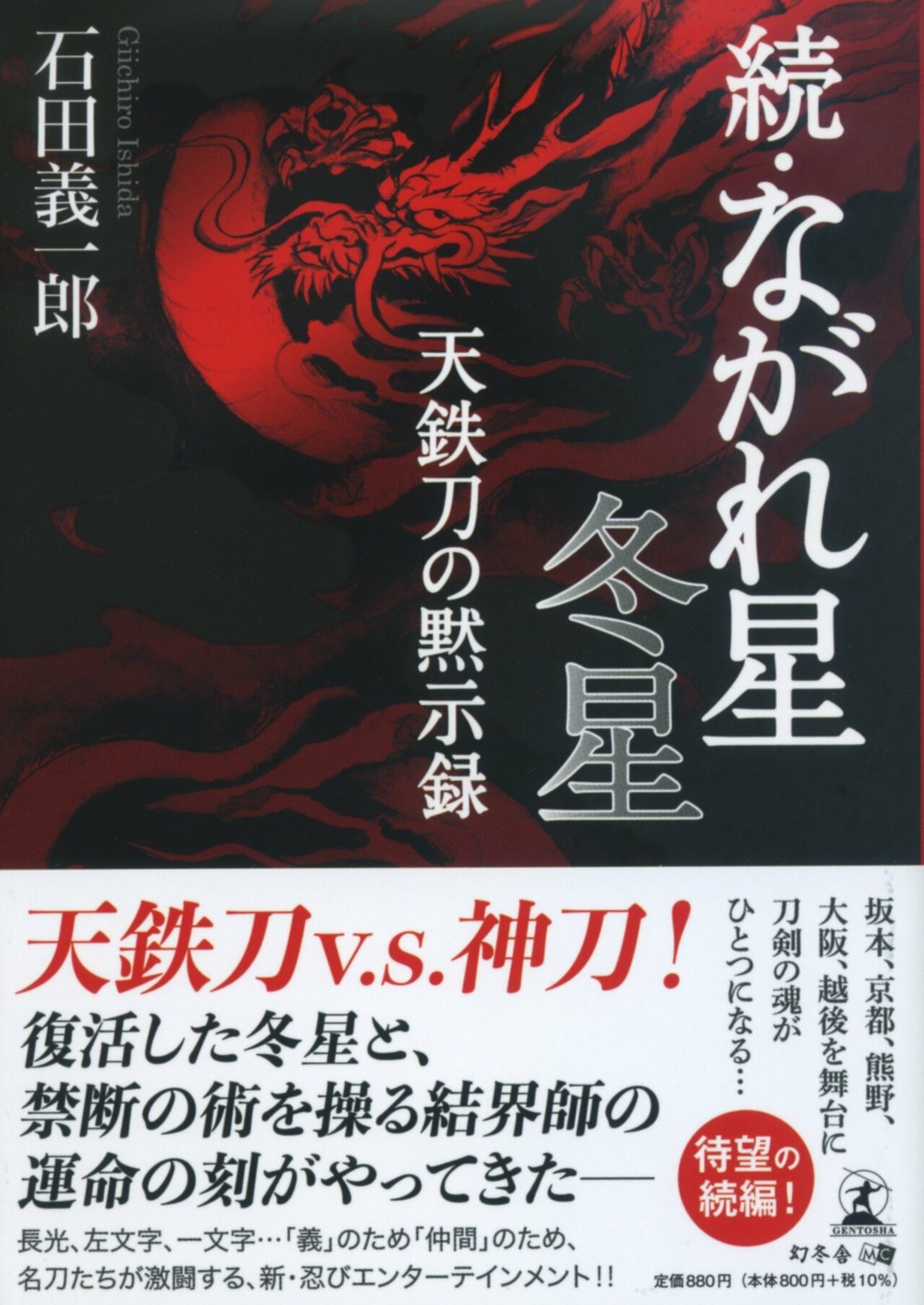【前回の記事を読む】風変わりな雰囲気を醸し出している渡世人風の男はどこから来て、どこへ行こうとしているのか……
第一章 帰巣(きそう)
─応化橋(おうげのはし)─
橋の袂の(たもと)ささくれた板に書かれた名が消えかけている。橋の入り口には、数人の男がいて橋番として橋銭(はしぜに)(通行料)を徴収しているようである。
ただ、橋番の男にしては柄(がら)が悪い。ひとりは手に徳利を持ち一人は行商人らの荷袋に手を入れている。
橋の入り口で何人かが言い争っている。柄の悪い連中のなかの目のつり上がったねずみのような顔の男が腕組みをして、「おい、橋銭賃は六銭だぜ。文句ある奴は、別に通らねぇでもいいんだぜ」と、目を細め吐き捨てるように言った。
「なんだって! 六銭とは高すぎるでねぇか。今までは二銭だったじゃねっか。あまりにもふっかけすぎだ!」商人(あきんど)の男が怒鳴った。
「ほう、文句があるんなら橋の上を通らねぇで、下の川を通るってもんだぜ。昨日も馬鹿な奴がいて、冷てえ川の中を通ったなあ~。おい、安」
ねずみ目の男の後ろから、背が低く背中の丸い小男が顔を出した。
「へい、辰吉(たつきち)兄い。おれらの言うことを聞けねえんなら、すぐ放り投げまっせ。それとも、背中に背負(しょ)ってる積み荷を渡すかだ」
安という小男は、素早く走ったかと思うと後方にいた大男の背中に、ひょいと飛び乗った。
大男は髭(ひげ)づらで身の丈六尺(約一八〇センチ)はあろうかとおぼしき体軀(たいく)に、三十貫(約一一三キロ)以上の目方もあろうかという、まるで熊のような風体である。熊男はぎろりと商人の男を見下ろした。
商人の男は連中が堅気(かたぎ)の者ではないことを察し、渋々と橋銭を払い不満げな表情で橋を渡っていった。
後ろで見ていた百姓風の連れ合いは、「あいつら、権藤一味(ごんどういちみ)の三下(さんした)だ。間違いねえべ。