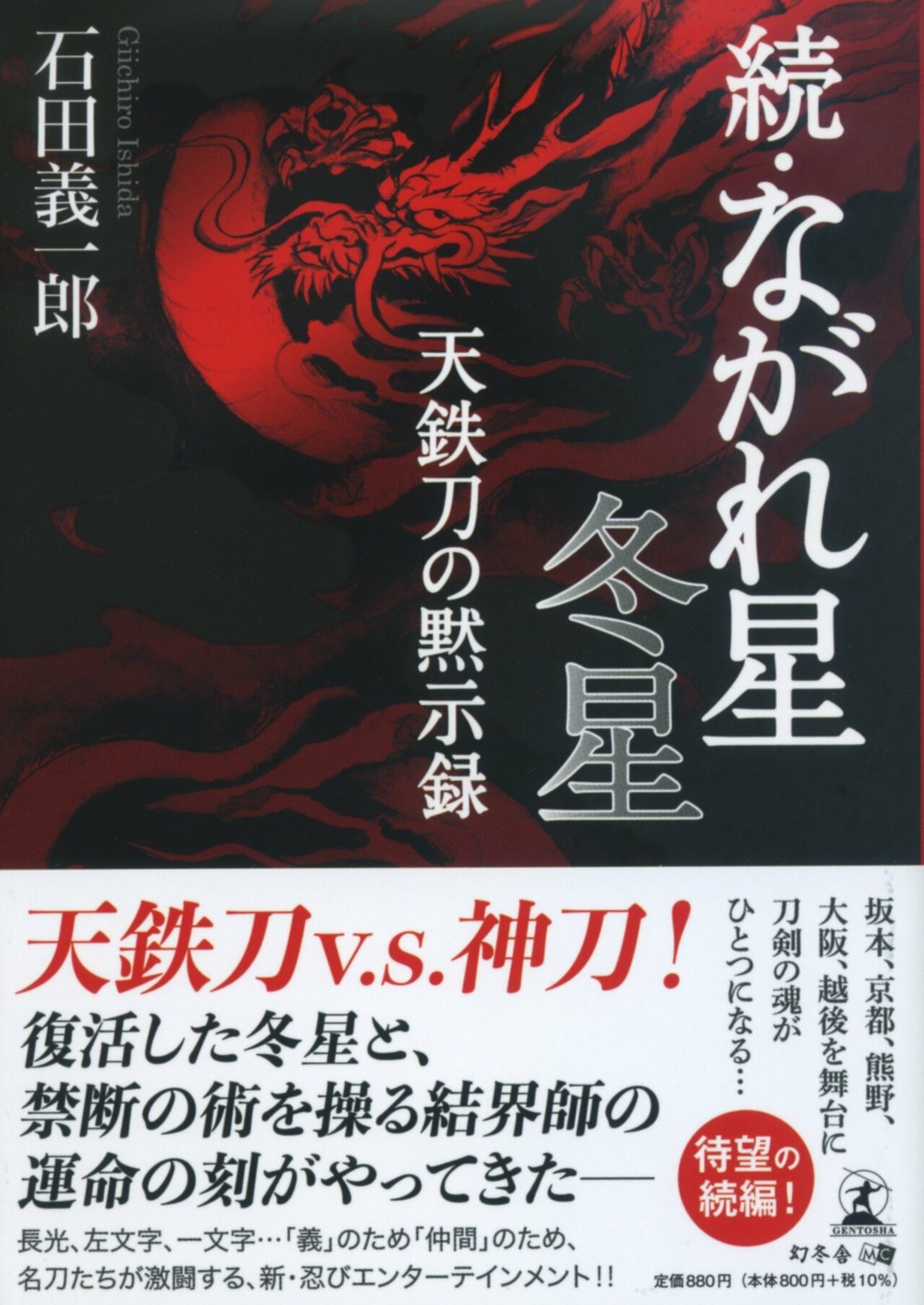あの細い男は『どぶねずみの辰吉』ってえ奴だ。意地汚えと評判の男だすけなあ。『田甕(たがめ)の安』もいっしょだ。
最近、日増しに幅を利かせてきてるわな。悔しいけども、関わらん方がええこて」ボソボソと眉をひそめて耳打ちをした。
ここ直江の津・今町の方言は一種独特である。東日本文化と西日本文化がぶつかりあい融合した稀有な地域だからである。「こて」とは「そうに決まっている」という断定の意味である。
京言葉の「おまはん(あなた)」が「おまん」になるなど、北前船(きたまえぶね)文化の影響で、関西・九州方面の方言が入り混じっているが、それにもまして不思議なのは、直江の津・今町の人間は地元言葉と標準語を使い分けて話すことができるという器用な一面を有していたことだ。
通行を待っていた人々が、橋銭を払い無言で橋を渡りだした。
そのとき、若い女の声で「さくらぁー!」と、甲高い声が響き渡った。
「かあちゃーん!」
すぐに幼い女児の声が返ってきた。どうも母と子で橋の上で離れ離れになったようである。
若い母親はすでに橋を渡りきろうとしているところで、女児が途中で引き返していたのに気づいていなかったようである。
さくらという女児は右手に椿の花を持ったまま、また橋を渡ろうとしていた。するとすかさず、
「おおっと、待ちな! 童子といっても、一人なら橋銭は払ってもらうぜ」どぶねずみの辰吉の目が光り、くるりと母親の方を向き直した。
「何を言ってんだい! さっき六銭も払ったじゃないか。しかも、童子からは橋銭は取らないのが常だろう」