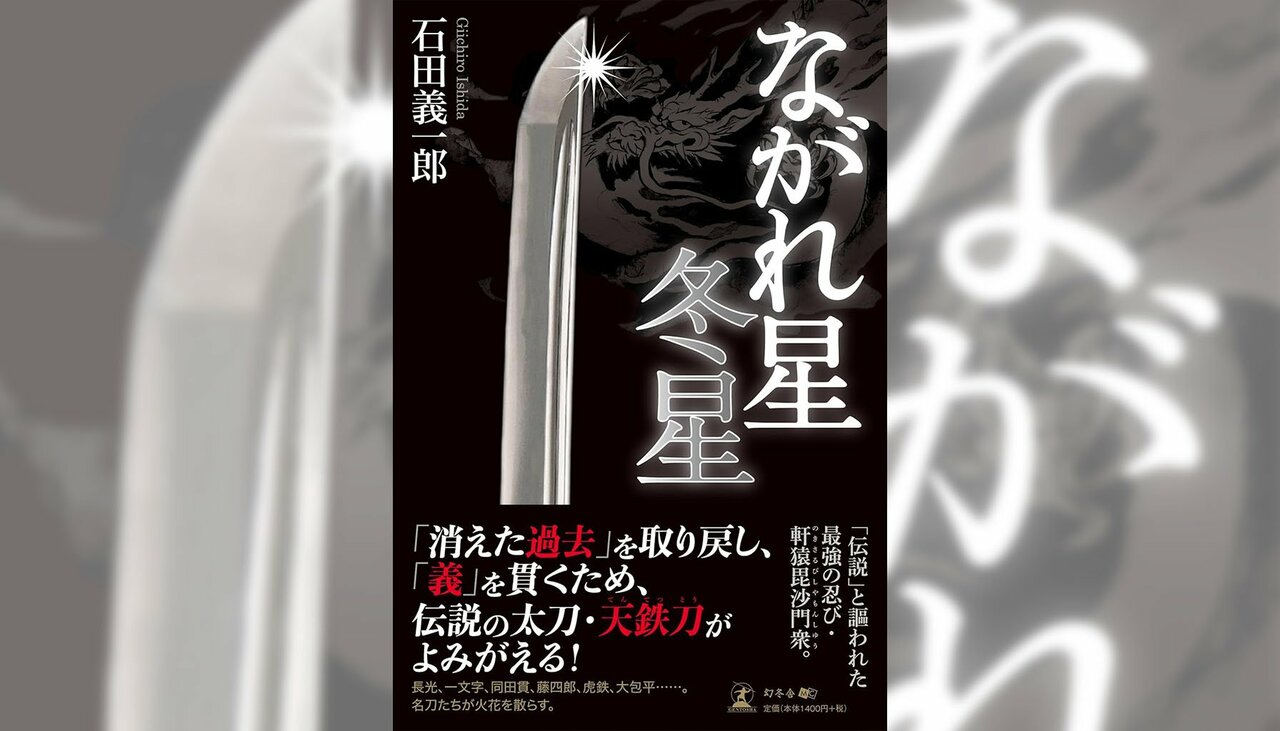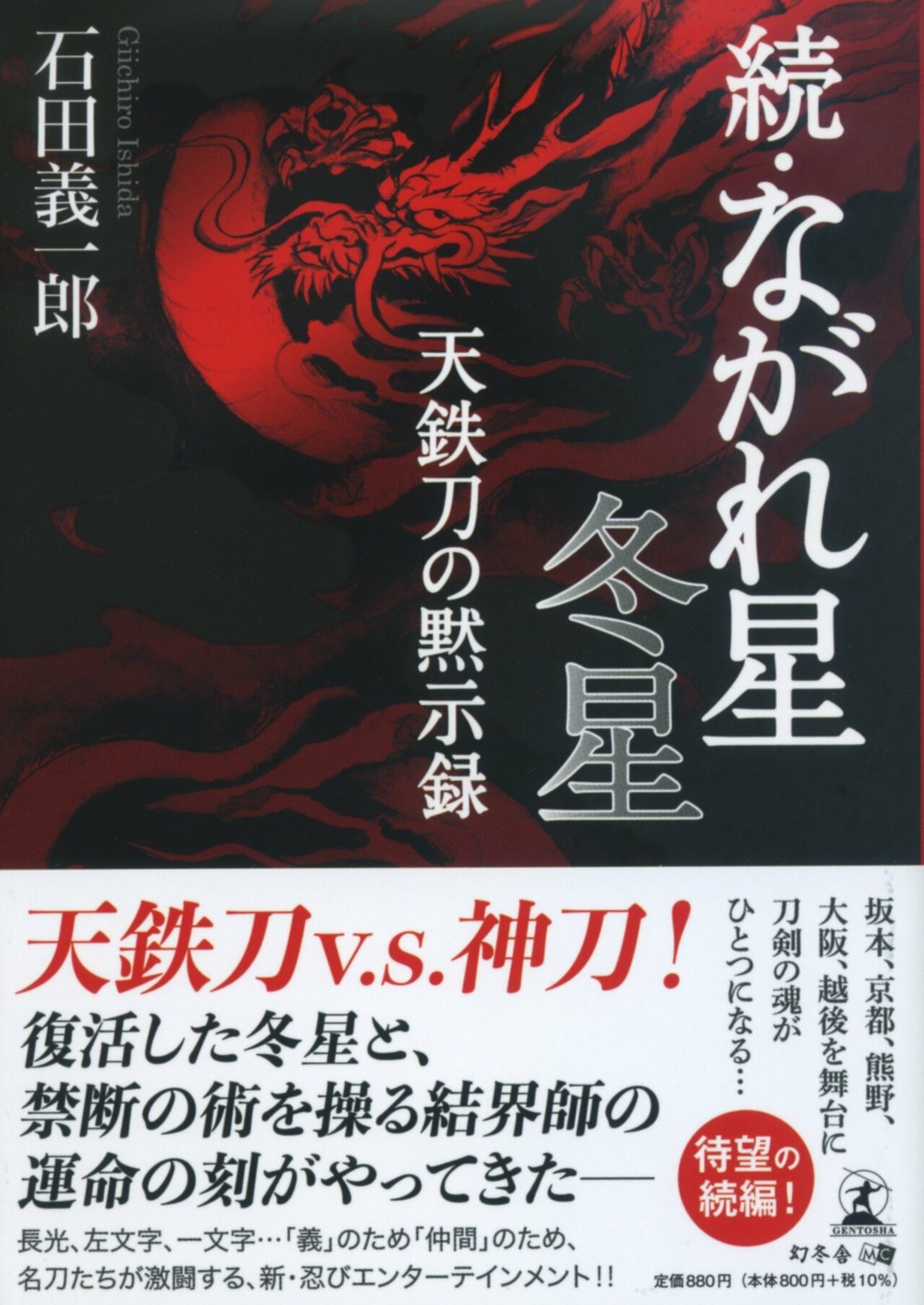第一章 帰巣(きそう)
波(なみ)の花が、天高く舞い上がっている。
日本海から吹きつける風は冷たかった。白い泡沫状の波の花は下からえぐられるような強い風に吹き上げられ、雪もろとも岸辺に叩きつけられている。
時折り吹いてくる強い突風は息も出来ないほど強く、心の底まで凍えるようだった。空は鉛色を呈し、海の色は緑がかった灰色で、その合間を白波が縫うように走っている。海猫の切ない鳴き声がいっそうこの海岸沿いを寂しいものにしていた。
天保(てんぽう)十五年(一八四四)の二月は雪こそ少なかったが、厳しい寒さであった。
二月如月の中旬とはいえ、この越後直江(なおえ)の津(つ)・今町(いままち)は冬である。真っ白な雪と泡に敷きつめられた岸辺を真っ黒な人影がひとり、こちらへ向かって歩いてくる。真っ黒な人影は、一見、渡世人風(とせいにんふう)にみえた。
渡世人風と言ったのは、煤(すす)けた深めの三度笠に、ずいぶんと草臥(くたび)れた道中合羽(どうちゅうかつぱ)を身につけていたからである。かなり年季の入った薄汚れた手甲(てっこう)・足甲(そっこう)脚絆から長旅を経てきたことがうかがえた。
しかし渡世人にしては、なにか風変わりな雰囲気を醸し出していた。よくみると、商売道具でもある長脇差(ドス)を差していないのである。
脇差はおろか、短刀すら差していない。かといって道中支度をした旅人特有の蓑風呂敷(みのふろしき)なども持ち合わせていないようであるため渡世人風に映ったのであろう。
またこの男のいでたちの独特なところは上から下まで黒ずくめであり、まるで〝雨に濡れた鴉(からす)〟のような風貌である。
身の丈は六尺(約一八〇センチ)もあろうか。歳は二十代後半。その風貌とは相反し、顔つきは凜(りん)とした引き締まった端正な顔立ちをしている。
そして印象的な特徴として、青白い顔の額に小さな赤い痣(あざ)なのか傷なのか一見しただけではわからないものがあった。
男がどこから来て、どこへ行こうとしているのか、行きかう人もいない厳寒の海岸で訝 (いぶか) る者はいなかった。