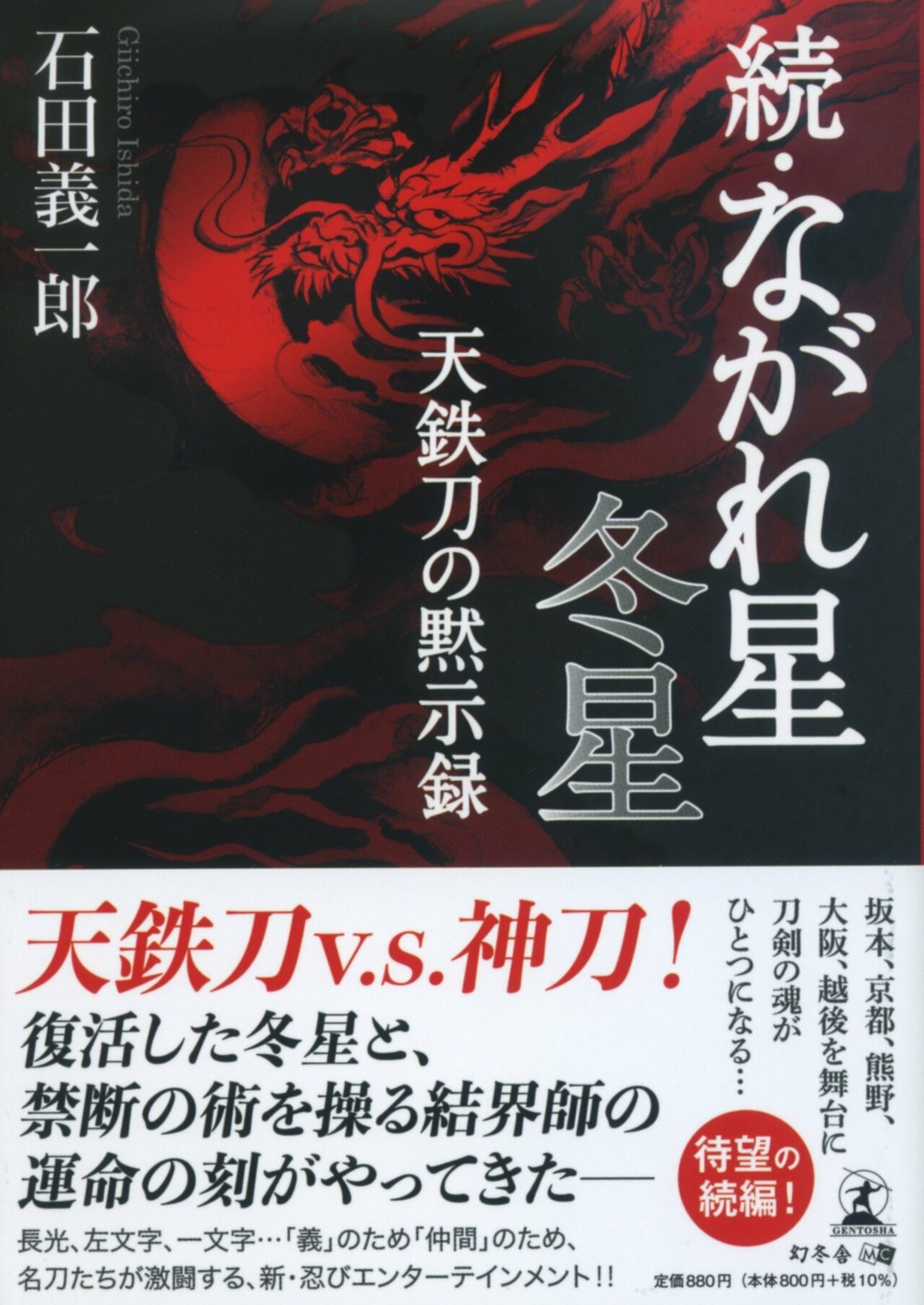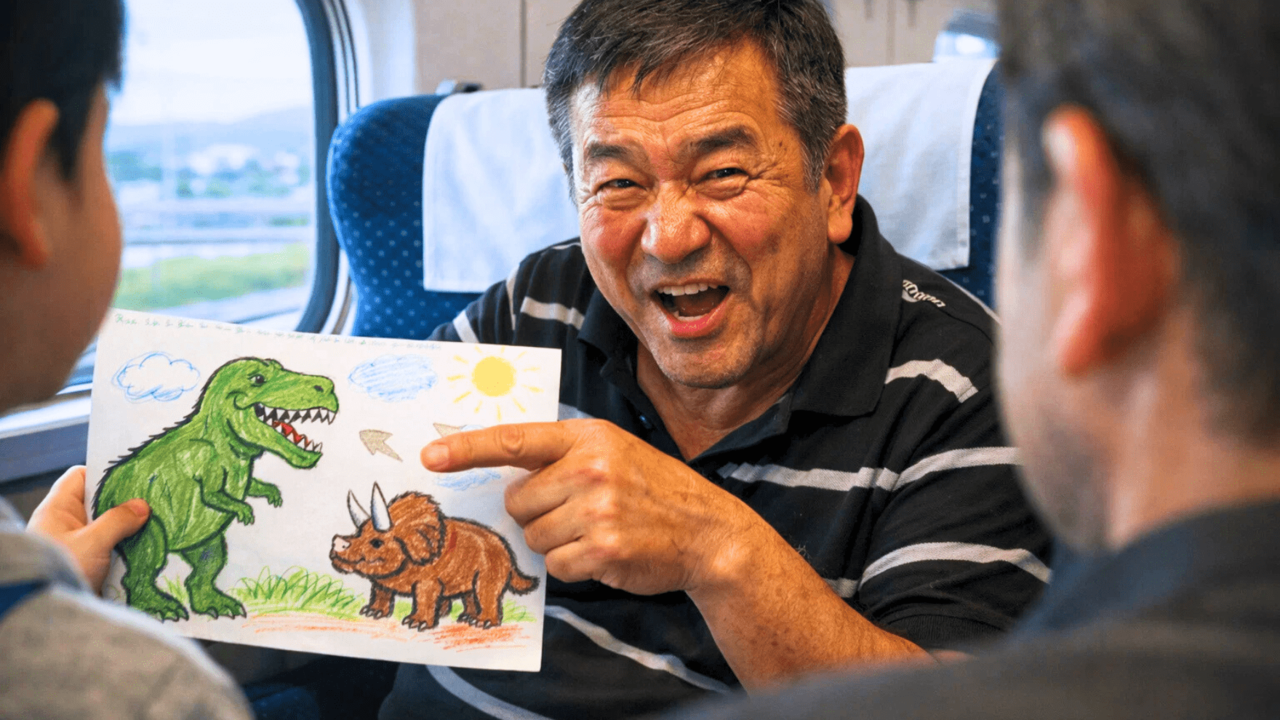濡れ鴉の男は、とぼとぼとおぼつかない足どりで道中合羽の襟を立て、雪氷吹きすさぶ小高い海岸の土手を上っていった。
小高い丘を過ぎると、直江の津・今町の全体が見下ろせた。
日本海から滔々(とうとう)と流れ込む荒川の上に、何本かの大きな橋が架かっている。その橋を渡った先には商(あきない)問屋・旅籠(はたご)など多くの町の賑わいが見えた。

この直江の津・今町は中山道追分宿(なかせんどうおいわけやど)から分岐し、小諸・上田・信濃を経て信越国境を越えてつづいている北国街道最大の分岐点である。
かつてこの地に国府が置かれ、京都に次ぐ大都市として六万もの人口を有していた。港町・宿場町でもあり、全国七港にも数えられた。この天保の時代でも人々の往来は多く、加賀街道から越後高田藩への登城も盛んであった。
砂丘の上に築かれた町である。大小の坂が多数点在し、その坂に覆いかぶさるように小さな民家がひしめきあっている。どの坂の上からも海が見えた。またそこかしこに、古い神社や寺・祠 (ほこら) があった。越後で一番歴史が古い町ならではの特徴ともいえた。
戦国時代、織田信長や武田信玄が「利(り)」によって国を治世したなか、全国でも唯一「義」(ぎ)という不文律で越後国を治めた上杉不識庵謙信(うえすぎふしきあんけんしん)。
その不識庵謙信のお膝元がここ、今町である。しかし天保の飢饉(ききん)の余波はこの時代になっても暗い影を落としていた。人々の心は荒(すさ)び、「義」の力を信じるものは誰ひとりいなかった。
濡れ鴉の男は海岸沿いの強い風を避け、丘を下っていった。ほどなくして港からの賑やかな街道に出た。
先ほどまで吹雪(ふぶ)いていた風もあがり薄日が差し込んできた。街道には海産物を大八車に載せた四十物(あいもの)(魚介類)・行商人らが行きかい、交通の要衝地であることを感じさせた。
直江の津・今町の町に入る手前で濡れ鴉の男は立ち止まった。大きな橋の入り口に差しかかったのである。
【イチオシ記事】何故、妹の夫に体を許してしまったのだろう。もう誰のことも好きになれないはずの私は、ただあなたとの日々を想って…
【注目記事】娘の葬儀代は1円も払わない、と宣言する元夫。それに加え、娘が生前に一生懸命貯めた命のお金を相続させろと言ってきて...