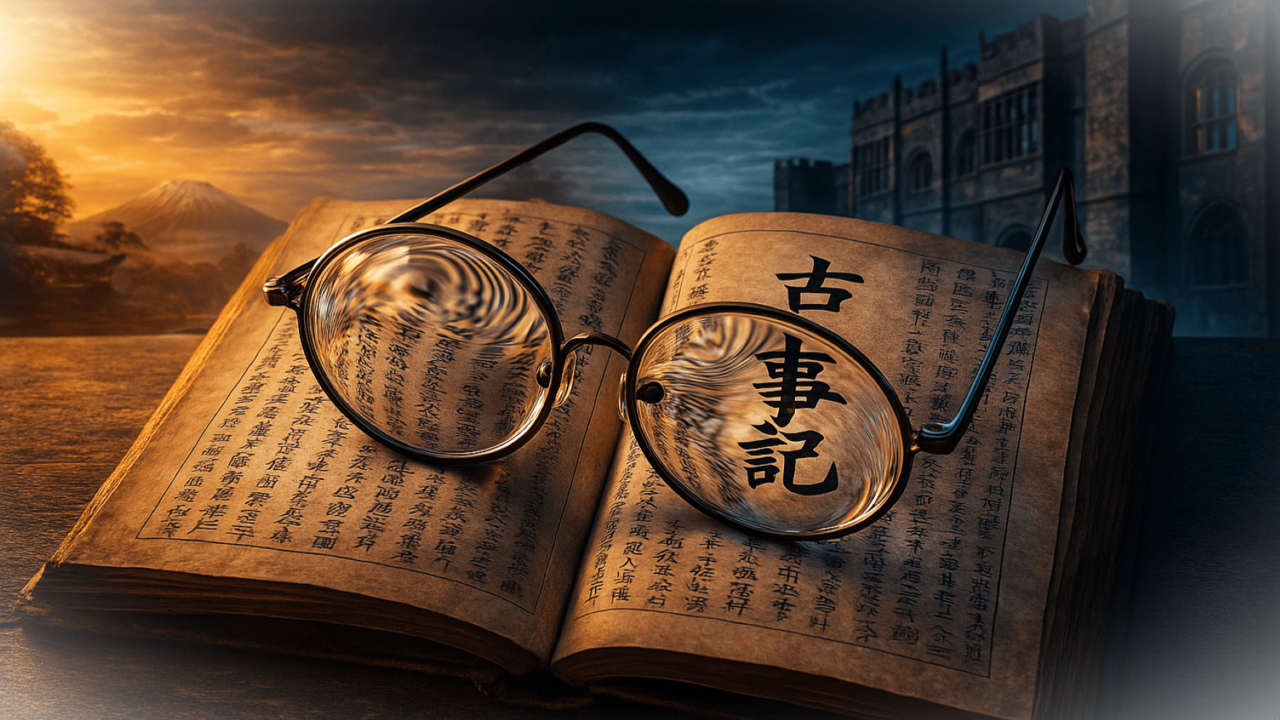六五三年に中大兄は都を難波から再び前の大和に戻している。自分の身辺に不穏な動きがあると感じたためであるが、大和は四方の山が自然の要害となっていて防衛しやすいからであろう。遷都に孝徳天皇は反対したために、彼は難波に残ることになる。そういった彼らの行動を見ると、中大兄と孝徳天皇の不仲が分かるし、天皇には権力がなかったことも分かる。
しばらくして孝徳天皇が崩御し、斉明天皇が即位する。この天皇は中大兄の実母であり、実は二度目の即位である(一度目は皇極天皇)。六十二歳の母を天皇としたのは、自分の思った通りの政治をすることができると考えたからであろう。こういった姿を天武は間近で見ているはずである。
孝徳を残したまま都を飛鳥に戻した時や百済救援の部隊を派遣するための本営を筑紫に置く際に、天武(大海人)は兄の中大兄に同行しているからである。
天武が十代の半ば頃から見ていた孝徳と斉明の二人の天皇は権力者として振る舞っていない。中大兄は天智天皇として即位をしてからも、権力者として振る舞っている。この経験が天皇像を考える上で後々大きなヒントになったと思われる。
天武天皇の深遠な問題意識
天武にとって大きな転機となったのが、壬申の乱である。『日本書紀』によれば、天智天皇が病に伏せるようになり、その病床に大海人を呼んで皇位継承の話をするが、彼は辞退をし、出家をして吉野宮(奈良県吉野町)に向かう。天智の気持ちは嫡男の大友皇子を即位させることであった。そのため、即位の意志を示すと命が危ないので、身を守るために辞去したと言われている。
『日本書紀』では、それを「虎を南に放つ」と表現している。天武は背が高く、幼少の頃から利発聡明で、天文学や忍術に優れていたという記録が残っている。天智も能力が高かったと思われるが、その彼が用心していた形跡があるので、人望が高く優れた人物なのであろう。
天智天皇の死後、天武は自身討伐の動きが朝廷にあるとの情報を得て開戦を決意する。大友側に蘇我氏や中臣氏といった中央の有力豪族がつき、天武に地方の中小の豪族がつく。古代の天下分け目の合戦が関ケ原を舞台に繰り広げられた。戦乱は約一か月続き、最終決戦となった瀬田川の戦いに勝ち、大友皇子を自害に追い込む。
【イチオシ記事】3ヶ月前に失踪した女性は死後数日経っていた――いつ殺害され、いつこの場所に遺棄されたのか?