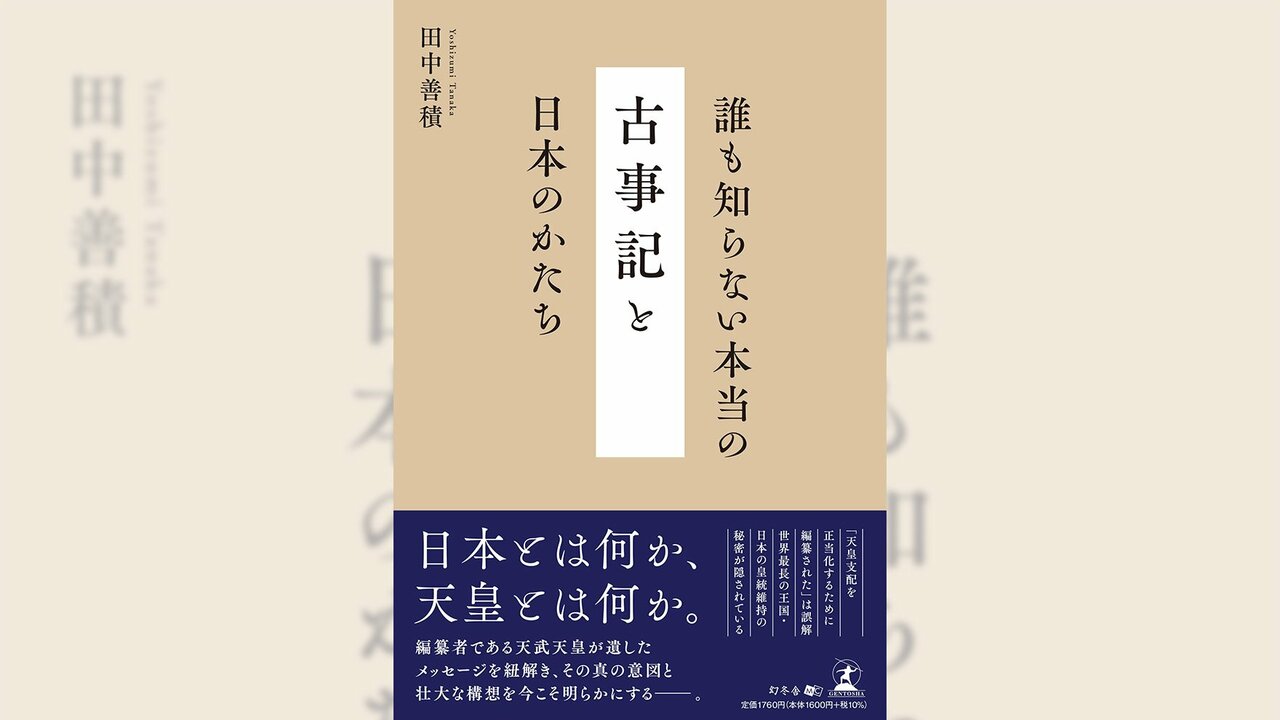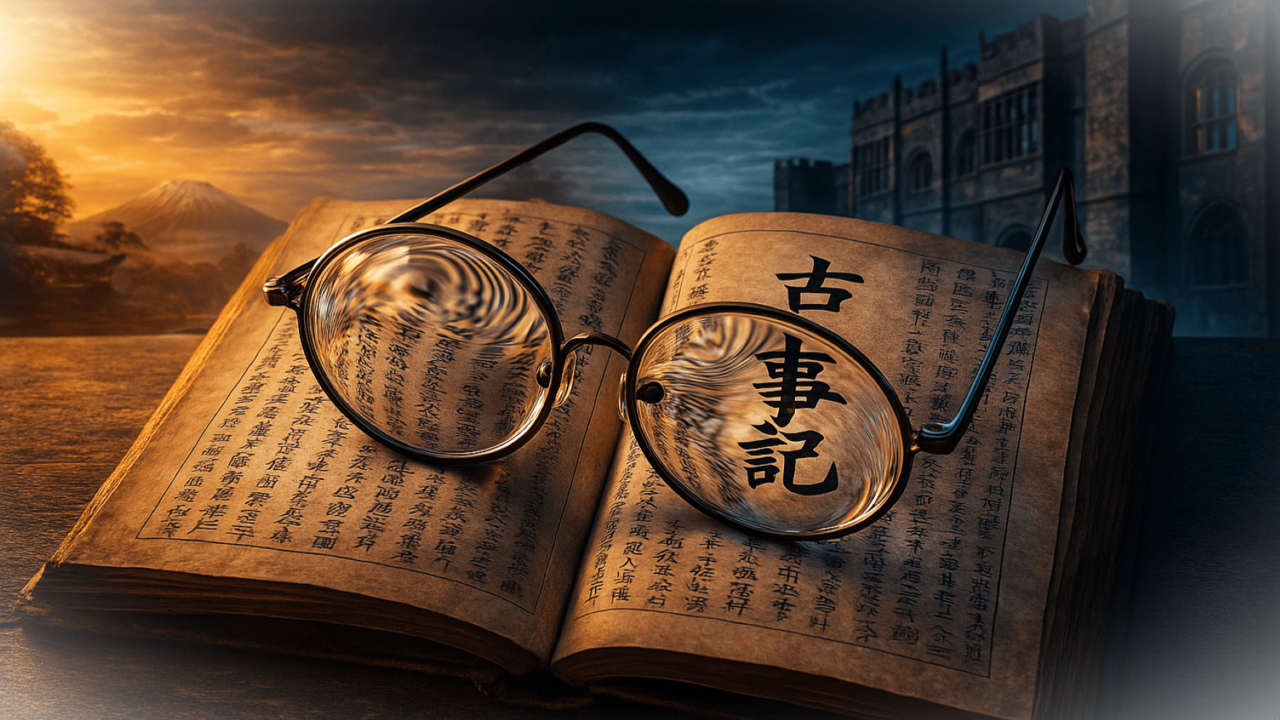【前回の記事を読む】巻き添えで死ぬ人を減らすため、自ら犠牲になった。だが、犠牲は彼一人では済まなかった。妻と子供たち全員が殺害され…
第一章 『古事記』の時代背景を探る
改新政治に対して反発・反乱
十七条の「民」を新政の綱領では「臣」としたのは、そこに中大兄の問題意識があるからである。
臣である豪族たちが仕えるのは、ただ独りと言っている。臣下であることを忘れ、聖徳太子の上宮王家を滅亡させ、「国に二君」たらしめんとした蘇我氏の行動を念頭に置いての言葉であることがよく分かる。その時々の権力欲で主を忘れたり、力の強弱で仕える人を変えたりするなという意味が「臣」に込められているのである。
やがては天武天皇として即位する大海人は、兄である中大兄が懸命に皇統を確立しようとしている姿やそれらに対する豪族たちの反応などを間近で見ているはずである。そういったことが、彼の天皇観に影響を与えていくことになる。
天智の時から元号が採用されることとなり、それを取って大化改新と呼んでいる。その中身だが日本式礼法から中国式礼法(立礼)に換え、冠位を十二階から十三階、そしてすぐに十九階とした。
さらに、これまでの臣(おみ)・連(むらじ)・伴造(とものみやっこ)・造国(くにのみやっこ)の職を廃して、新しい官職制度を導入することを宣言する。中国の制度を採り入れたのは鎌足の入れ知恵であろう。豪族たちに大きな衝撃が走ったと思われる。
朝廷との結びつきを示すのが姓(かばね)であり、その中でも臣と連は由緒のある高い位である。その世襲が一族にとってもプライドだったからである。
半ば強引な改革の進め方もあり、「新政府のめざす方向への不満や不安は、豪族層のなかに、鬱積していった可能性が強い」(吉田孝『体系日本の歴史 ③』小学館、一九九二年)。それが様々な事件を生むことになる。
すぐに古人大兄の反乱計画が起き、六四九年には蘇我石川麻呂の反乱計画が発覚する。この時には、関係者二十三人が殺され、十五人が島流しになっている。さらに、有間皇子の変と言われる謀反も発覚している。中大兄の宮から不審火もあり、大化の改新以降も、朝廷周辺で多くの血が流されている。