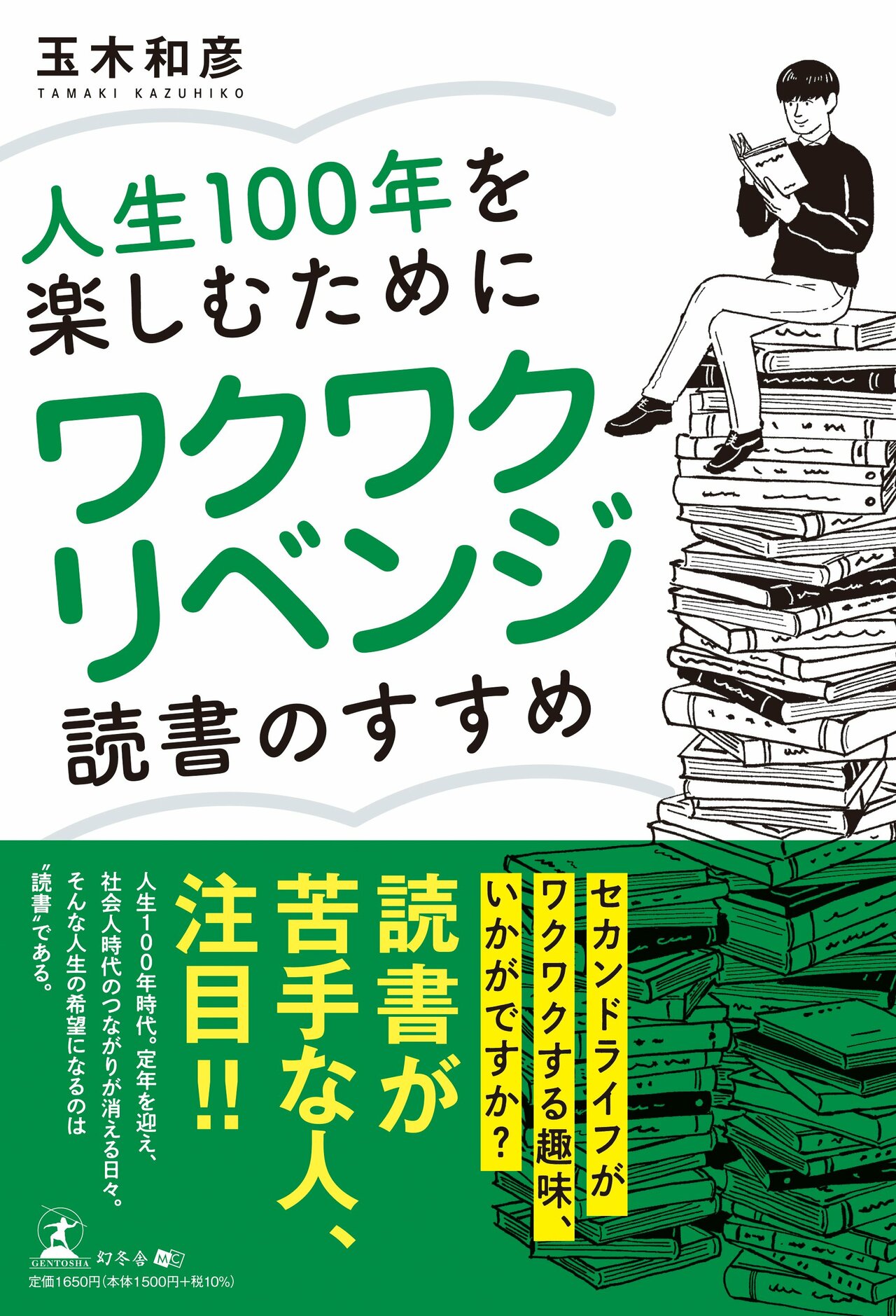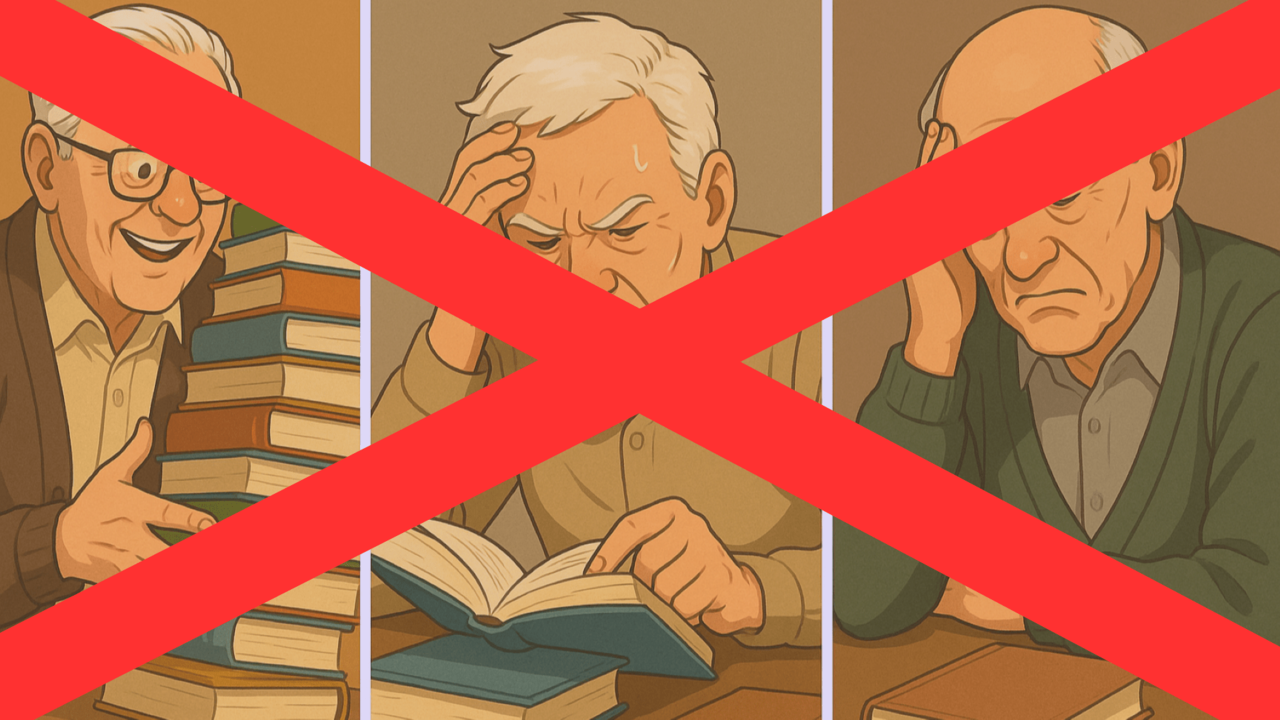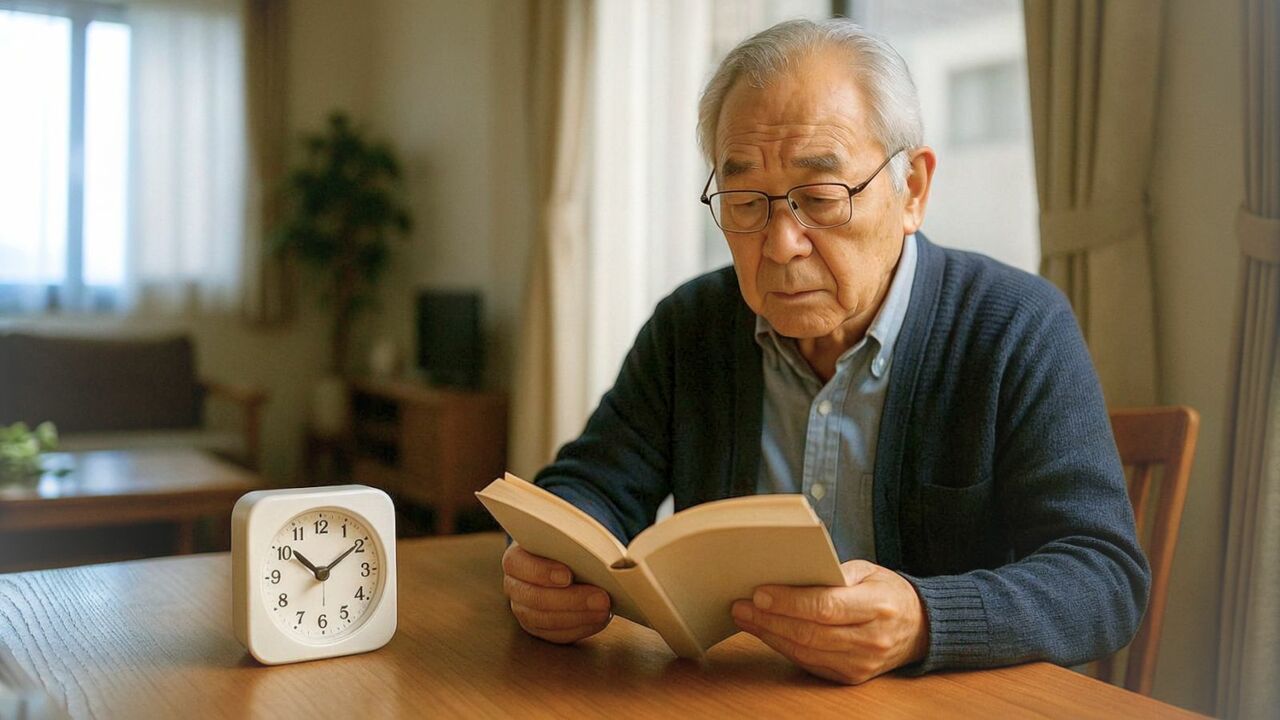またドイツの哲学者ショウペンハウエルは自著『読書について』(岩波書店 1960年)で思索する読書をアピールしている。「熟慮を重ねることによってのみ、読まれたものは真に読者のものになる」としている。つまり「考える」という行為をしなければ、知識として蓄積もしなければ、それを智慧に変えて生活の充実をはかることができないということなのだろう。
さらにショウペンハウエルは、蓄積された知識によってもたらされるものを「会話の才」としている。
「会話の才を決定する要素は、第一に知性、判断力、活発な機知というようなもので(中略)第二には時には会話の素材、相手と話を交える時の話題、つまりその人の知識も要素として重視される」としている。
「知的である」とか「話題が豊富である」ということは、一方で「熟慮した読書」の結果としてもたらされるということなのだろう。
自分の考えを持ちながら読んだ本は記憶に残りやすい。
「自分の考えを持ちながら読む」とは、仮説を持って読むことである。特に小説の場合は、単に物語の筋を追いかけるのではなく、作者の生きざまを考えながら「ここでこういう表現になるのは、作者のこういう背景が関係しているのではないか」などを意識しながら読み進めると、さらに味わい深い読書を楽しむことができる。それが読書の醍醐味でもあるのだろう。
このことは読書会などで読書を学んできた私自身が実感していることである。
そして、知人・友人との会話の中でも関連した内容になった時には、読書によって取得した「知識の引き出し」から引き出すようにしている。
これが、前にも語った「ちょっと賢くなったかな」とうぬぼれる瞬間でもある。
【前回の記事を読む】妻は返事もしてくれず、元部下にも断られ疎遠に…退職後、寂しく悲観的になっているあなたへオススメする「リベンジ」
【イチオシ記事】喧嘩を売った相手は、本物のヤンキーだった。それでも、メンツを保つために逃げ出すことなんてできない。そう思い前を見た瞬間...