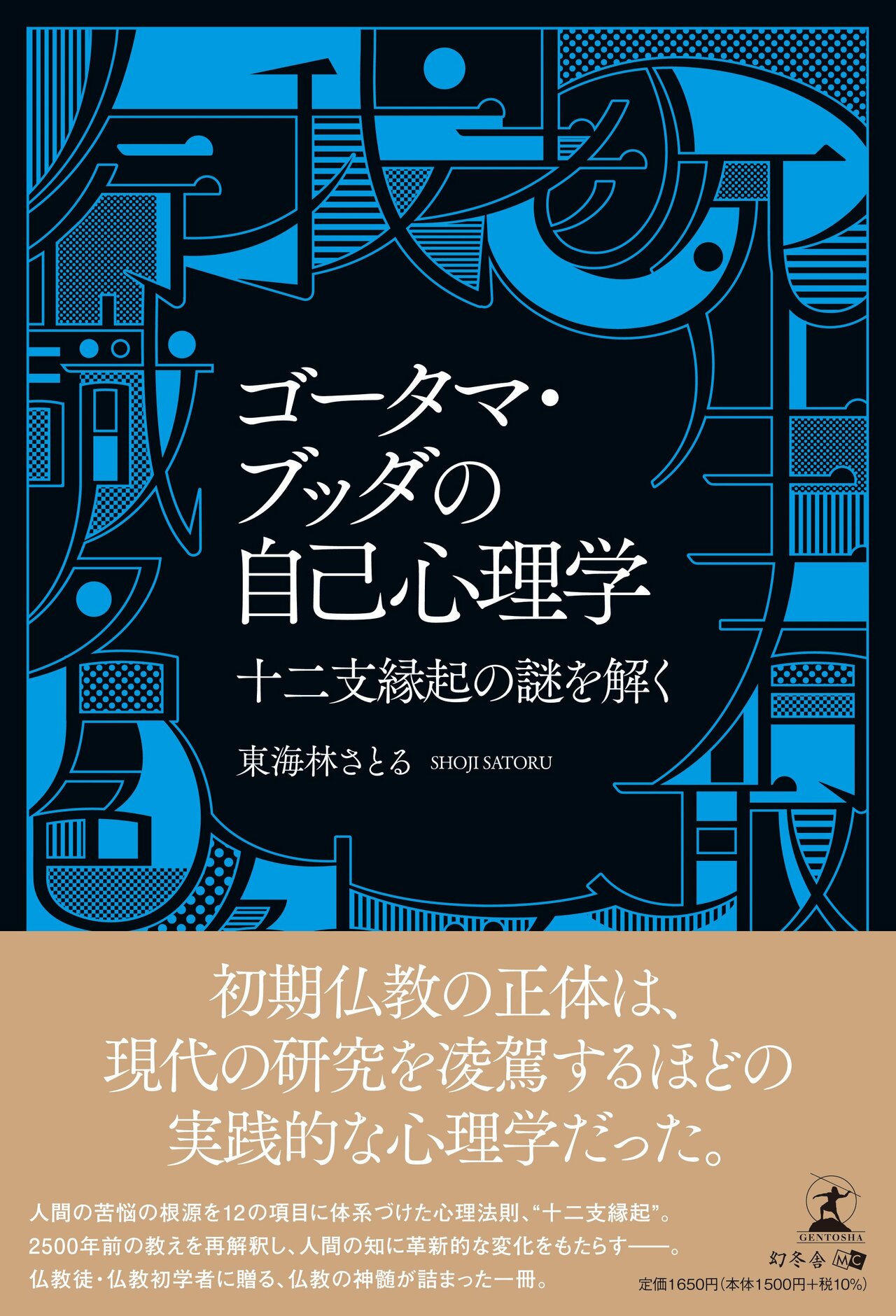「取」とは、「自我への執着」のこと
「取」は一般に「執着」のこととされます。人にとっての最大の執着とは、「自分という存在」(自我)に対する執着です。
ここでの「取」は形成された自我に執着すること、つまり「我執」を意味します。何ごとも自分が大事と思うことです。
死の不安が強ければ強いほど、「自分という存在」に執着することになります。また、「自分という存在」にしがみつけばしがみつくほど、そこからあらゆる執着が生まれてくるともいえます。「自分という存在のためならばどんなことでもする」となります。
そのような執着は、昔から人が不老不死の薬を探し求めてきたという物語にもうかがうことができます。「自分という存在」にしがみつけばしがみつくほど、自分の思い通りにならず(苦であり)、逆に自由を失ってしまうのではないでしょうか。
『自我に固執する見解をうち破って、世界を空(くう)なりと観ぜよ。そうすれば死を乗り越えることができるであろう。』(スッタニパータ 1119)
自我に固執する見解を、我見といいます。自我に固執しないで、世界が空となる心的体験をすれば、死の苦悩を乗り越えることができると言っています。
初期の仏典においては、「取」(執着)という言葉の多くが五蘊(自我を構成する五つの要素)への執着として語られています。
『世間には種々なる苦しみがあるが、それらは生存の素因にもとづいて生起する。実に愚者は知らないで生存の素因をつくり、繰り返し苦しみを受ける。それ故に、知り明らめて、苦しみの生ずる原因を観察し、再生の素因をつくるな。』(スッタニパータ 728 )
中村氏は、同じことを別な箇所で言葉を変えて次のように訳しています。
『世の中にある種々様々な苦しみは執着を縁として生起する。実に知ることなくして執着をつくる人は愚鈍であり、繰り返し苦しみに近づく。だから、知ることあり、苦しみの生起のもとを観じた人は、再生の素因(執着)を作ってはならない。』(スッタニパータ 1050-1051)
「知ることなくして、執着をつくる人は、繰り返し苦しみに近づく」とは、「執着によって苦しみが生まれるということを知らずに五蘊に執着する人は、繰り返し苦しみを受ける」ということであります。
ここでは、先の「生存の素因」(upadhi)に当たるところは、「執着」と訳されています。また「再生の素因」にも執着という訳をつけています。
ちなみに、並川孝儀氏は、「生存の素因」(upadhi)は、「生存のよりどころとなる根源的執着」と訳しています。
『執着の条件(upadhi)によって苦しみが起こる。』(ウダーナヴァルガ 32章37 )
先の「生存の素因」と今度の「執着」または「執着の条件」は、五蘊への執着を意味するものと思われます。つまり、ここでの「生存の素因」(upadhi)は生存のよりどころである五蘊への執着(五取蘊)を意味する言葉であると考えられます。
また、ここに出てくる「再生の素因」という言葉は、「再びの生存の素因」のことですが、付加的に「執着」とも訳されています。
【前回の記事を読む】誰かに「君はどう生きるのか」と問われているようだ。――人は、老いや死という概念を覚えると、「死にたくない、生きたい」と…
【イチオシ記事】喧嘩を売った相手は、本物のヤンキーだった。それでも、メンツを保つために逃げ出すことなんてできない。そう思い前を見た瞬間...