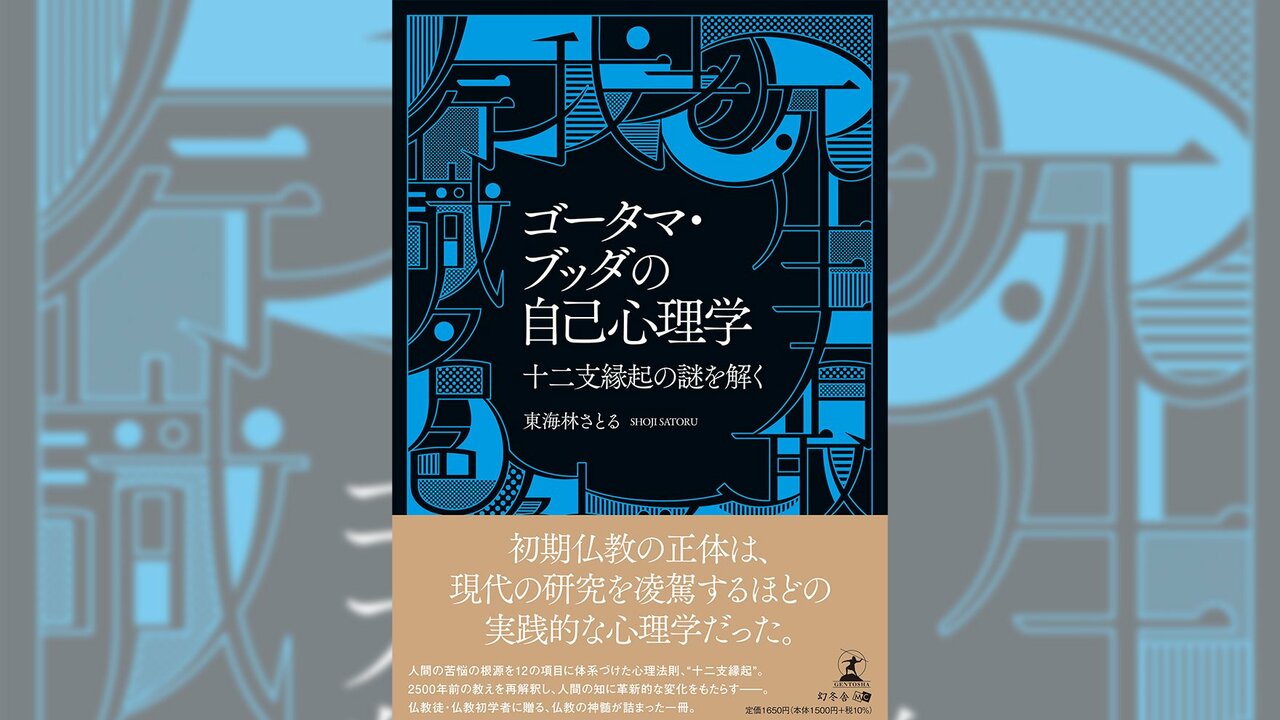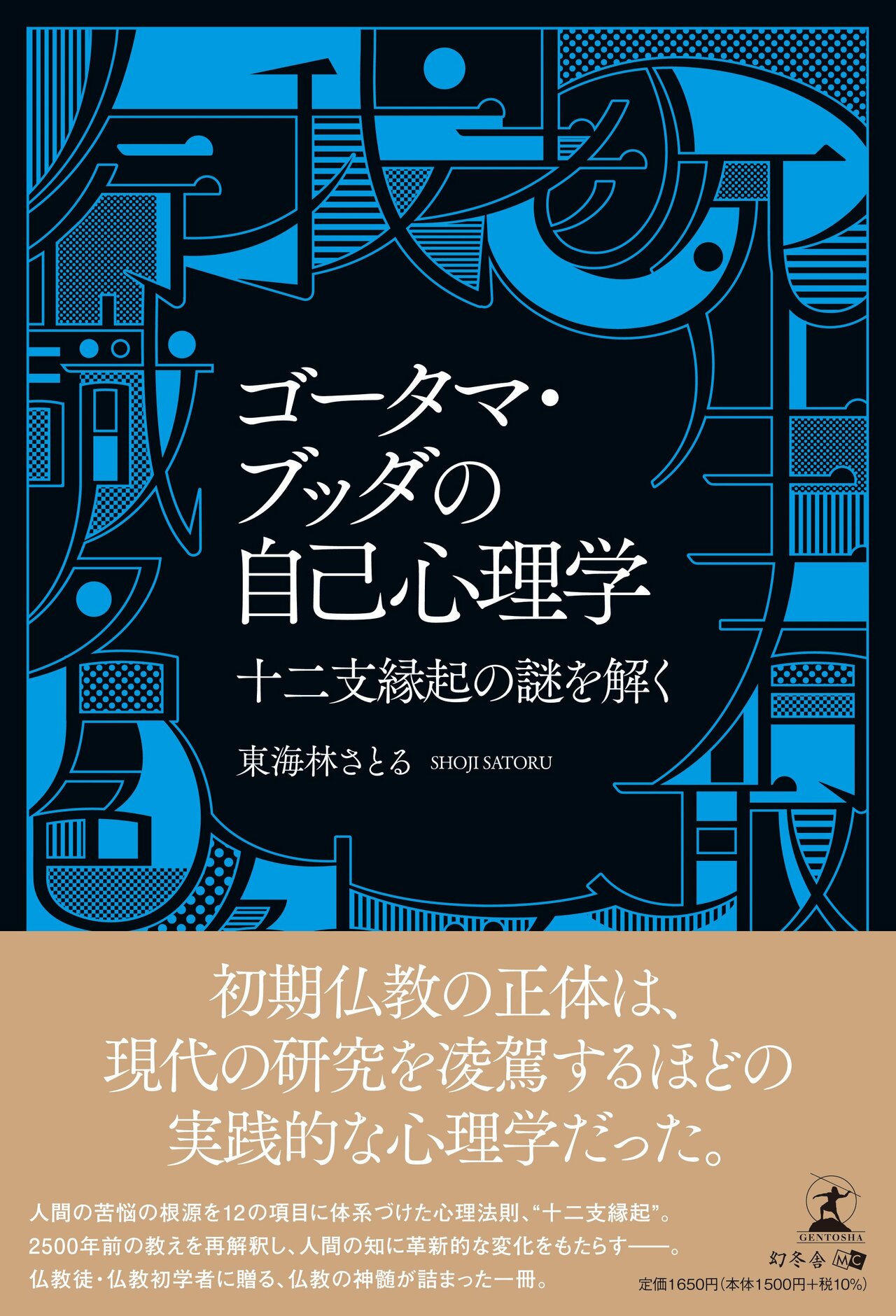【前回の記事を読む】「自分という存在」にしがみつけばしがみつくほど、あらゆる執着が生まれ「自分という存在のためならばどんなことでもする」となり…
第二章 自己心理学から見た各支の意味
「取」とは、「自我への執着」のこと
つまり再度「五蘊に執着すること」(五取蘊)の繰り返しを意味しています。それは、「再び迷いの生存に生まれること」であり、「自分というものが存在する」と思っていること「無明」(迷い)の繰り返しを意味していると思われます。
『いかなる常住なる生存も存在しない。またもろもろの形成されたものも常住ではない。個人存在を構成する五つの要素(五蘊)は、次から次へと生じては滅びる。これは危ない患いであると知って、わたくしは迷いの生存を求めることがなかった。』(テーラガーター 121、122)
ここでの「常住なる生存」とは、ウパニシャッド哲学におけるアートマン(我)のことを意味していると思われます。
「もろもろの(心に)形成されたものも常住ではない」ということは、心の中に常住不変なるもの、アートマン(我)は存在しないということを意味しています。
「迷いの生存」は、「錯覚としての自我」にとらわれた「無知なる生存」のことで、十二支縁起の「無明」を暗に示しています。自我を構成する五つの要素(五蘊)に執着することによって、「錯覚としての自我」(無明)が生まれます。
その「自我に執着すること」で我欲が生まれ、それによって再び自我を構成する五つの要素(五蘊)に執着して、自我(無明)が再生されることになります。
けれど、同じ執着でも、「五蘊に執着すること」(五取蘊)と形成された「自我に執着すること」(我執)とは、意味が異なります。
十二支縁起の一支分「取」は、自我を構成する五蘊への執着ではなく、五蘊への執着によって形成された「自我そのものへの執着」「我執」を意味しています。