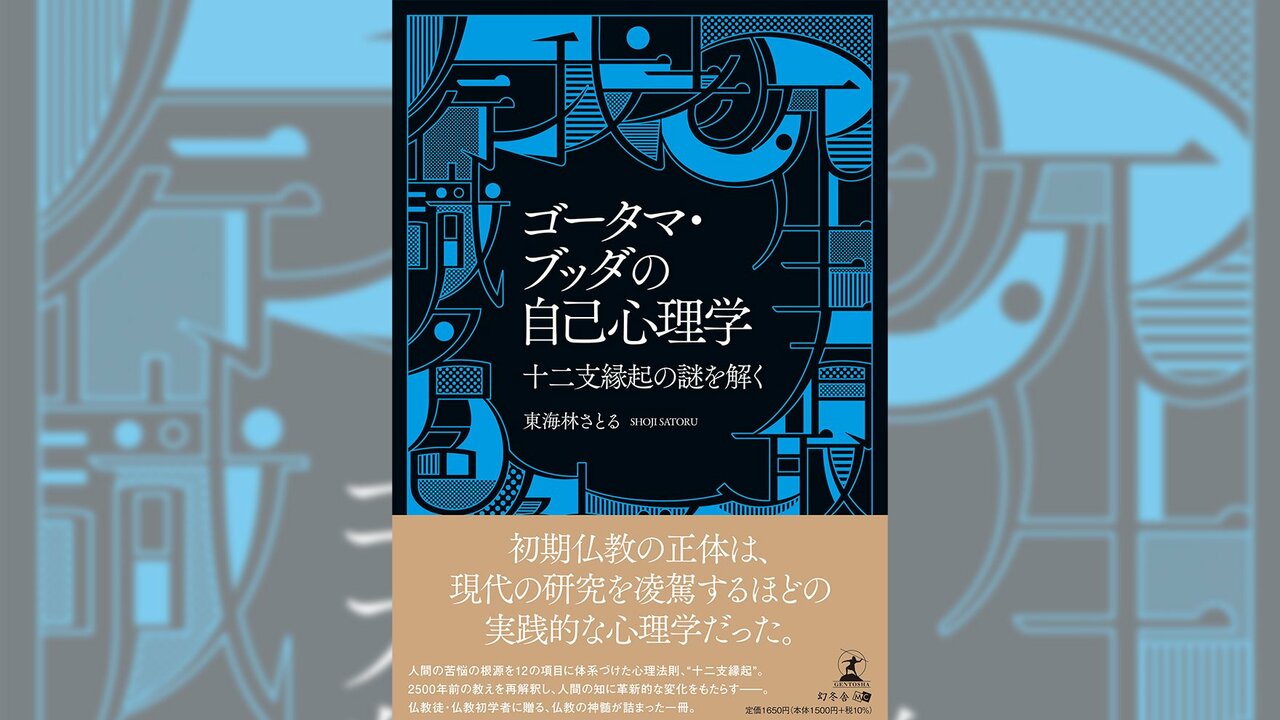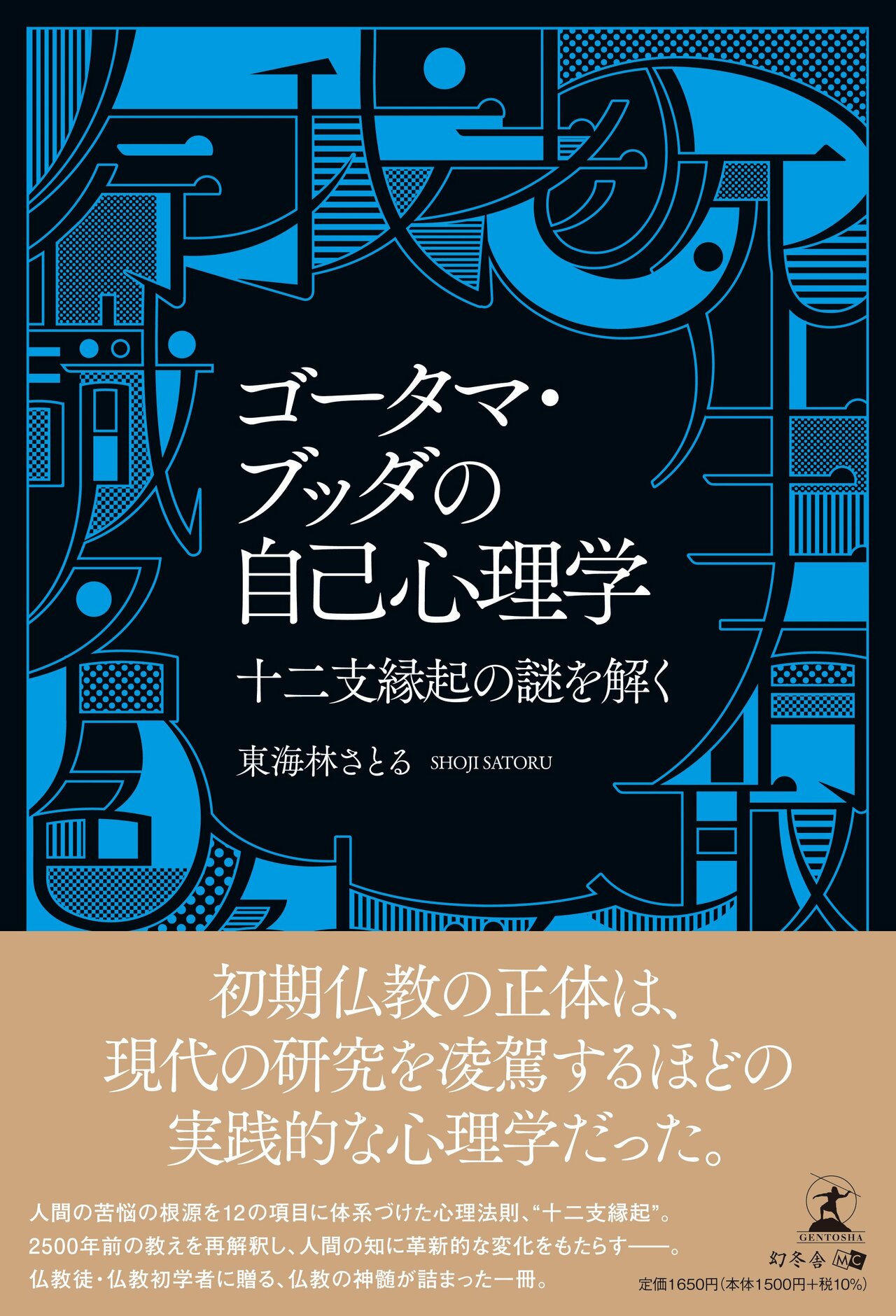【前回の記事を読む】【仏教】愛とは、自分の生存への執着欲? 生存に執着するからこそ、際限のない欲望が生まれ、そのこだわりが所有欲へ…
第二章 自己心理学から見た各支の意味
「受」とは、「身体に起こる情動や感情」のこと
もしも不快になれば、そこから怒り、憎しみ、妬み、恨み、悔しさ、憂い、悲しみなどのマイナス感情が生まれてきます。
『欲望をかなえたいと望んでいる人が、もしもうまくゆくならば、かれは実に人間の欲するものを得て、心に喜ぶ。欲望をかなえたいと望み、貪欲の生じた人が、もしも欲望を果たすことが出来なくなるならば、彼は矢に射られたかのように悩み苦しむ。』(スッタニパータ 766、767)
貪欲(とんよく)とは、好ましい対象への執着を意味します。
「矢」は、初期の仏教経典では一般に煩悩の比喩として語られます。
つまり、自分が存在すると思うからこそ、自分の欲望が満たせない、自分のものにならない場合には、対象となるものに対して、怒りの感情や嫌悪感など否定的な感情が引き起こされることになります。
そして、その欲求不満の原因を他人のせいにしたりします。また、他人に怒りや憎しみをぶつけることによって、生じた欲求不満を解消しようとさえします。
さらには、その怒りの感情や自己否定的感情にとらわれて、結局、感情に振り回されることになります。