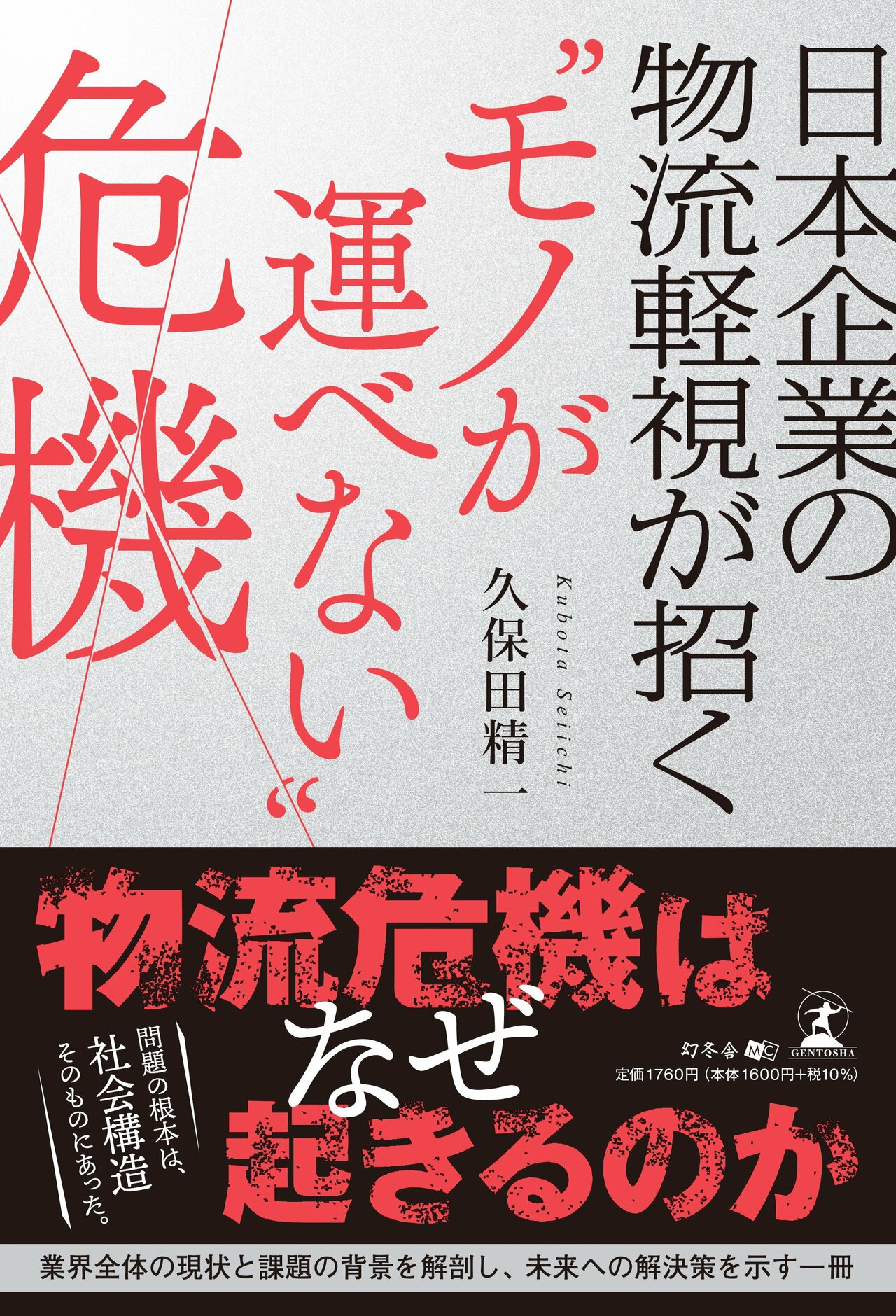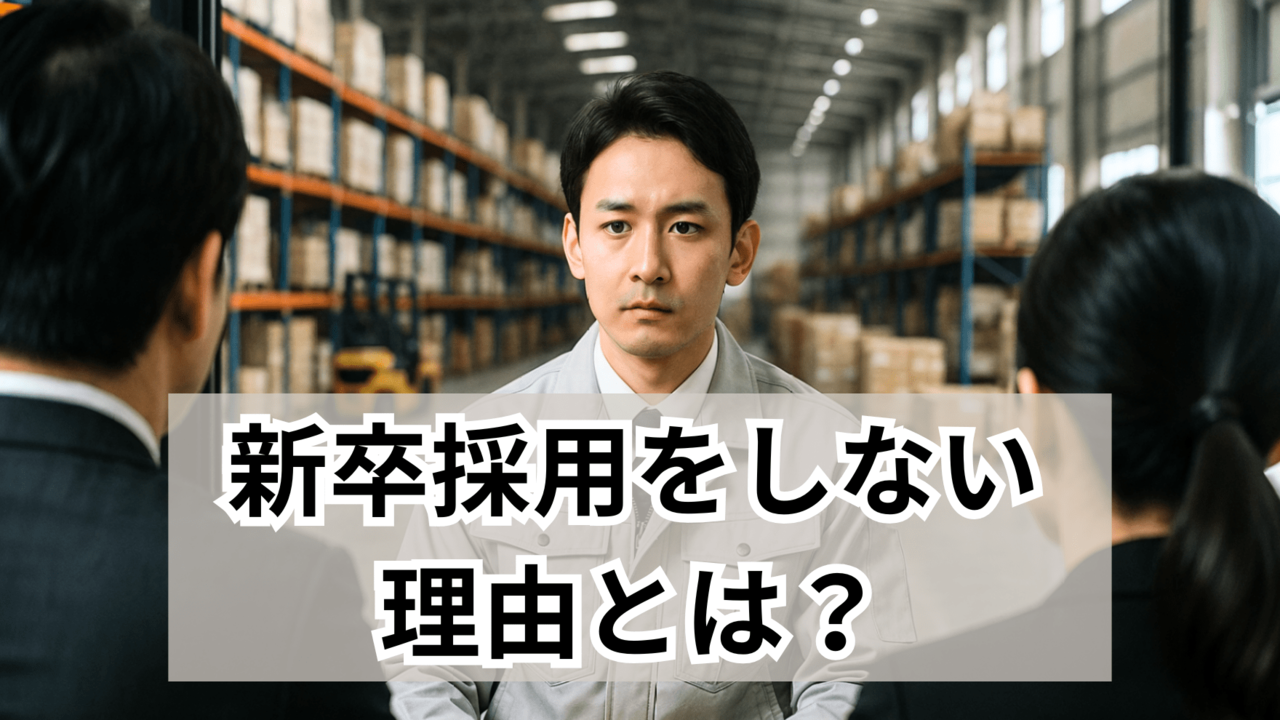ところで、CSCOとCLOとはその指し示すイメージに違いがある。CLOが管理対象とするのは「ロジスティクス」だが、ロジスティクスという言葉には、トラック輸送や倉庫保管といった「物流実務」の印象が伴う。
一方で、CSCOの所掌である「SCM」には、上記のような物流実務に加えて、製造業・流通業における重要な経営課題である需給管理、在庫管理や調達管理等まで含まれる。
よって言葉から受ける印象としては、CLOよりもCSCOのほうがより広い領域をカバーするイメージである。日本語でも、「物流部長」より「SCM部長」のほうが所掌範囲が広い印象を受けると思うが、これと同様である。
この点を踏まえると、重役レベルの役職としては「CLO」は如何にも領域が狭い印象を受ける。現代の企業実務を踏まえると、「CSCO」のほうが妥当に感じられる。
実際、後述するとおりグローバル企業では、CLOではなくCSCOを設置しているケースが大半である。よって以下では役職名を「CSCO」に統一して説明を行う。
グローバル企業ではCSCOの設置が広がっているグローバル企業におけるCSCOの設置率はかなり高い。
次ページの図表7は、消費財メーカーのグローバルトップ30社におけるCSCO等の状況を整理したものである。
上位30社のうち実に13社(割合で言えば43%)がCSCO等を設置しているのである。また、フォーチュン500企業をもとに調査した報告によれば、抽出サンプルのうち68%の企業がCSCOを設置していたというデータもある注1)。
フォーチュン500に掲載されるような巨大なグローバル企業の場合には、北米・アジア等の地域ごとに分社化して管理している場合がかなり多く、その場合、「北米担当」などのエリアトップが役員として任命されるケースが多い。