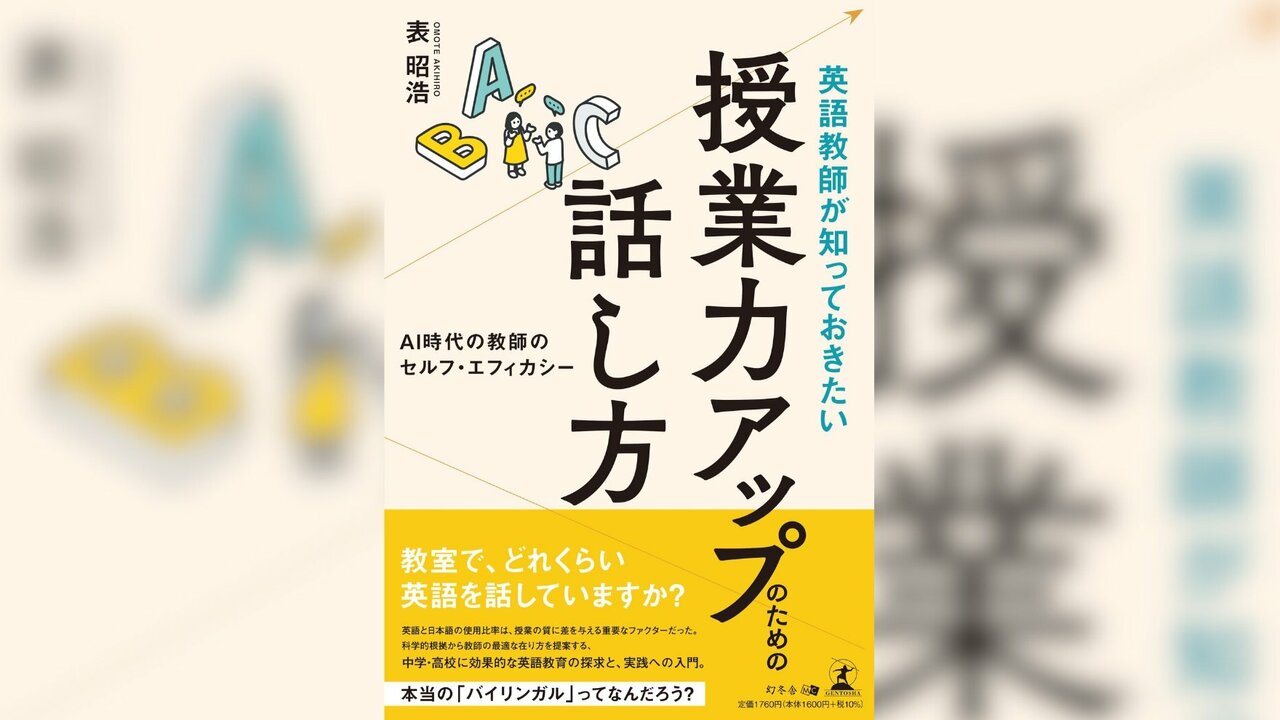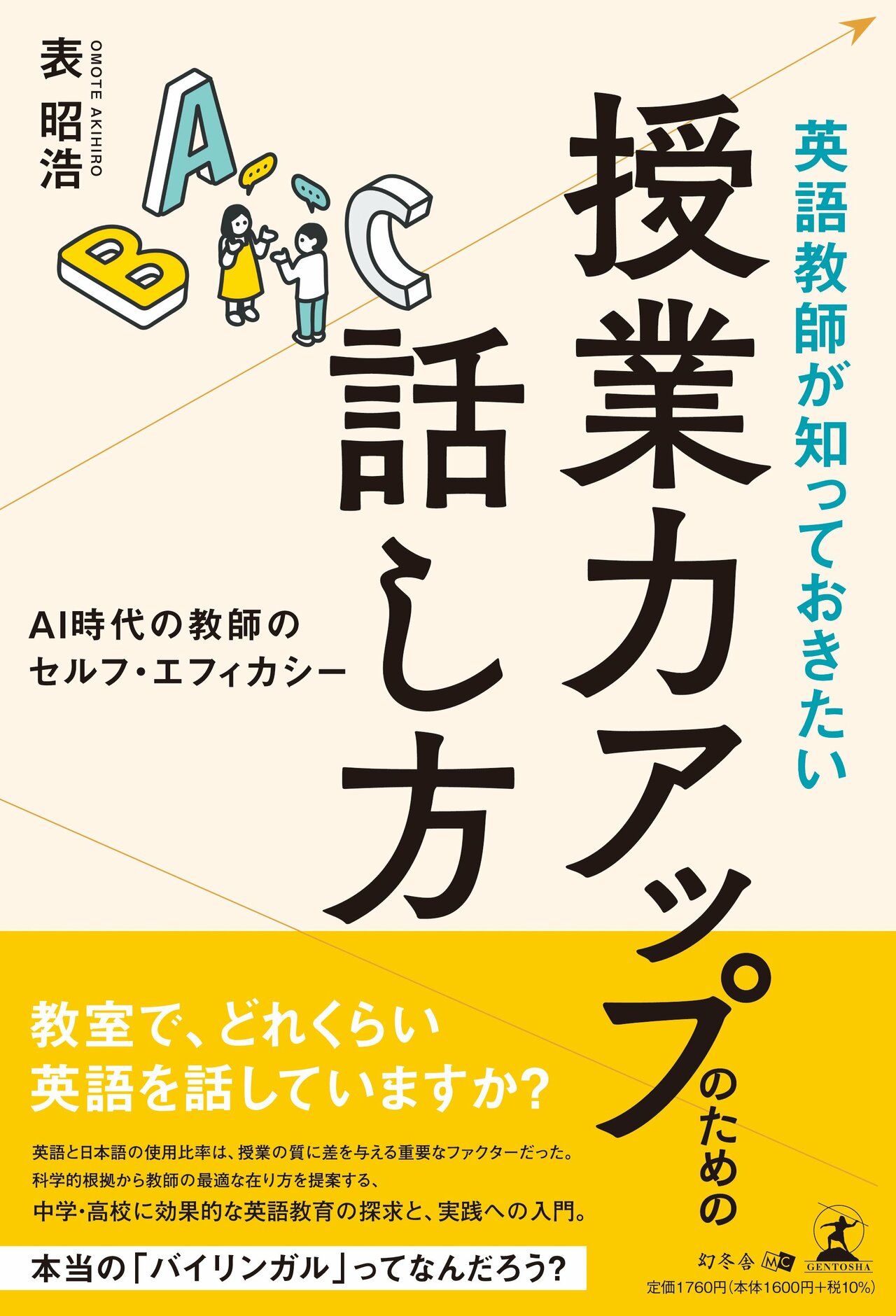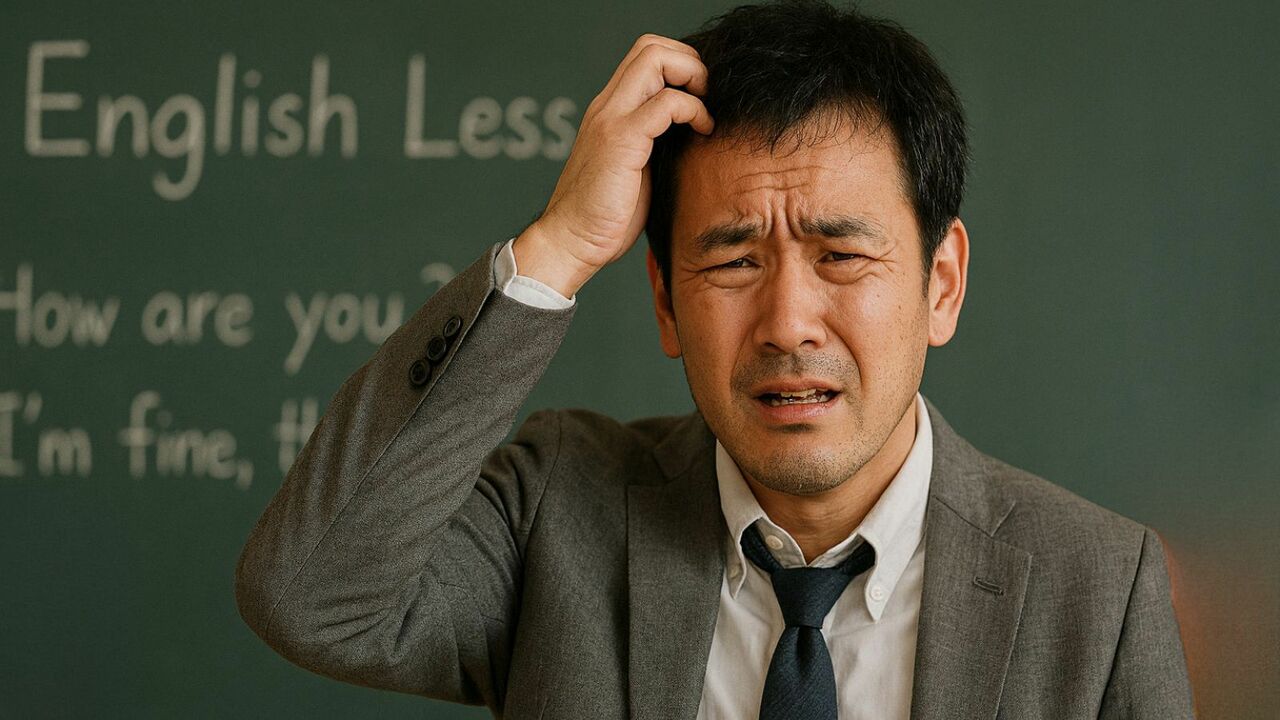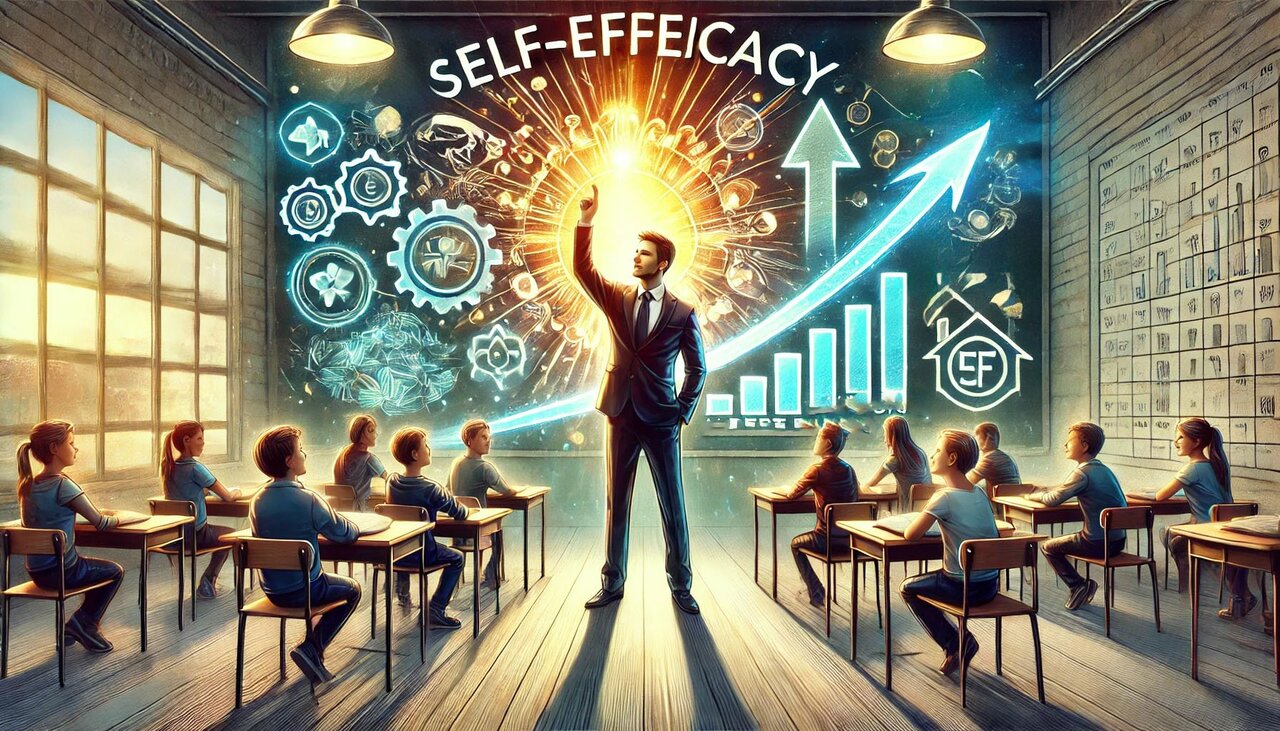第1章英語教師は英語をどう教えているのか
第2節 教師の話し方について何がわかっているのか
第2項 日本人教師のバイリンガリズム
本書は、日本語を母語とする英語教師を対象としていることから、ここで日本人教師とは一体誰を指すのかについてより厳密に考えておきます。
というのも、日本語が母語であり、同時に英語に幼少時から触れて育ったことで英語を2番目の言語として獲得している生得的バイリンガルの教師も存在するからです。
したがって、本書では日本語が母語で、同時に英語との生得的バイリンガルでもある教師や、英語が母語で、同時に日本語との生得的バイリンガルでもある教師は、除外して考えていることに注意して下さい。
多くの日本人教師は、日本で生まれ育ち、日本の英語教育で外国語としての英語学習経験を有する学習バイリンガルだと想定します。
彼ら彼女らは非英語母語話者、非生得的バイリンガルとして英語を話し、職業上の理由から教室で英語と日本語を使用したIS行動をとります。
本書ではこの条件に当てはまる教師を職業的バイリンガル教師と定義し、そのような教師を日本人教師と呼ぶこととします。
国内で日本人教師の英語行使と母語依存の関係を直接検討した実証的研究はあまりありません。
ただし、英語のスキルを専門分野に活用することが目的となる大学のような高等教育機関でも、教授者が英語ネイティブであるか非ネイティブであるかにかかわらず、どちらの教師も学習者の英語能力を無視するような英語オンリーの授業には総じて否定的であることがわかっています4,5,7,8。
また、中等の学習段階においては、目の前の学習者の能力の限界からくる混乱や意欲低下を考慮しながら、それに必要な日本語を使うことが重要だとする中学や高校の英語教師のIS行動、言い換えれば日本語に寛容な行動原理が存在しています6,90,13。
日本人中学高校英語教師の発話とその機能について質問紙を通じて調査したShimura(2007)やYonesaka(2005)の研究によると、教師は高度な内容やスキル目標の達成よりも内容の基礎的な理解や動機づけをより重視して、敢えて英語ではなく日本語を使うことがあると言います14,15,17。
彼らは、これを英語から日本語発話へ「回帰的に」戻る現象だとユニークに表現しています。これまでのIS研究からも、こうした中等教育段階の教室におけるIS行動には様々な社会的3、認知的1,2、あるいは環境的11,16な要因からくる信念と実践の間の矛盾や葛藤が関わっていることがわかっています9,10,12。
例えば、西野(2011)の高校英語教師を対象とした質問紙の分析結果では、「言葉は使うことで効果的に習得(される)」には98%、「コミュニケーション能力の育成が大切」には97%の回答者が賛同しつつも、普段の授業でコミュニケーション活動を使っている回答者は30%に至らず、教師の認識と実践の乖離が示されています9。
しかし、教師がどのような社会的あるいは心理的メカニズムでこうした回帰行動や矛盾した行動をとるのか、その行動は意識的に行われているのか、あるいは無意識のうちに母語行使をした結果の表れなのか、そのような疑問に答えるための研究や、そこに介在する社会的、認知的な心理構造、またその理論的モデル化を扱った研究は無く、日本人英語教師のIS行動は未だに多くが不明なままなのです。