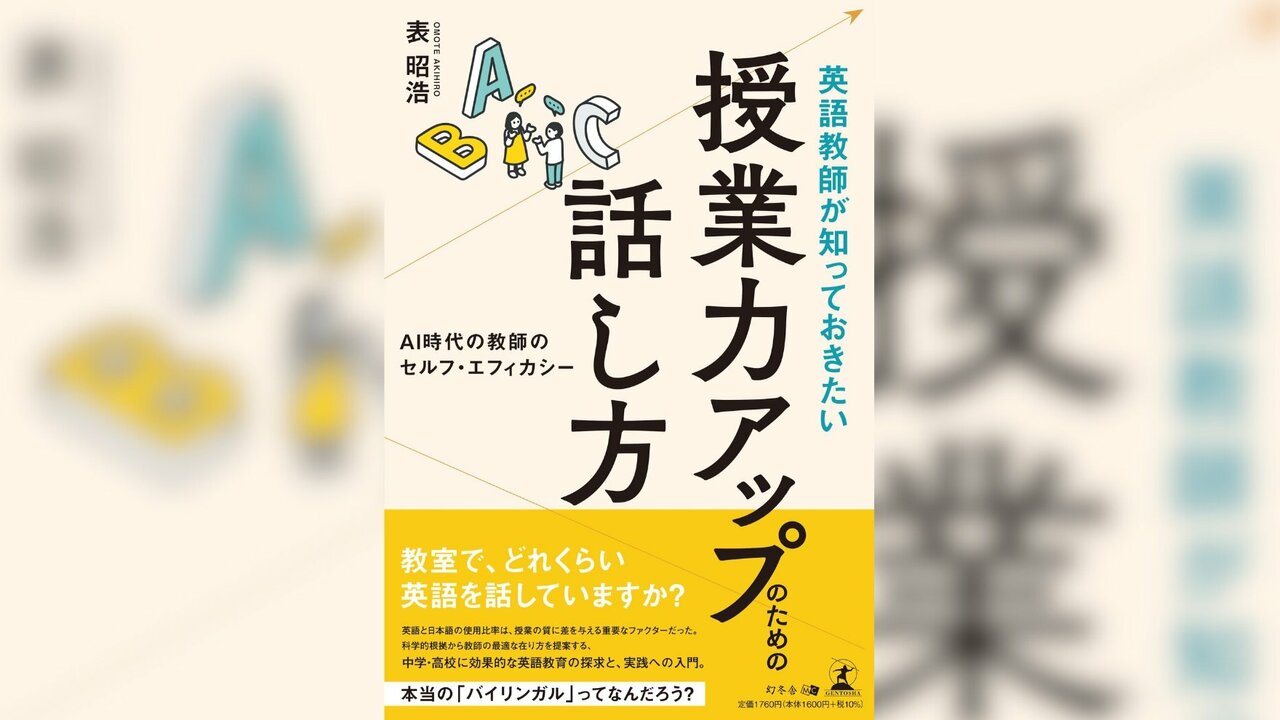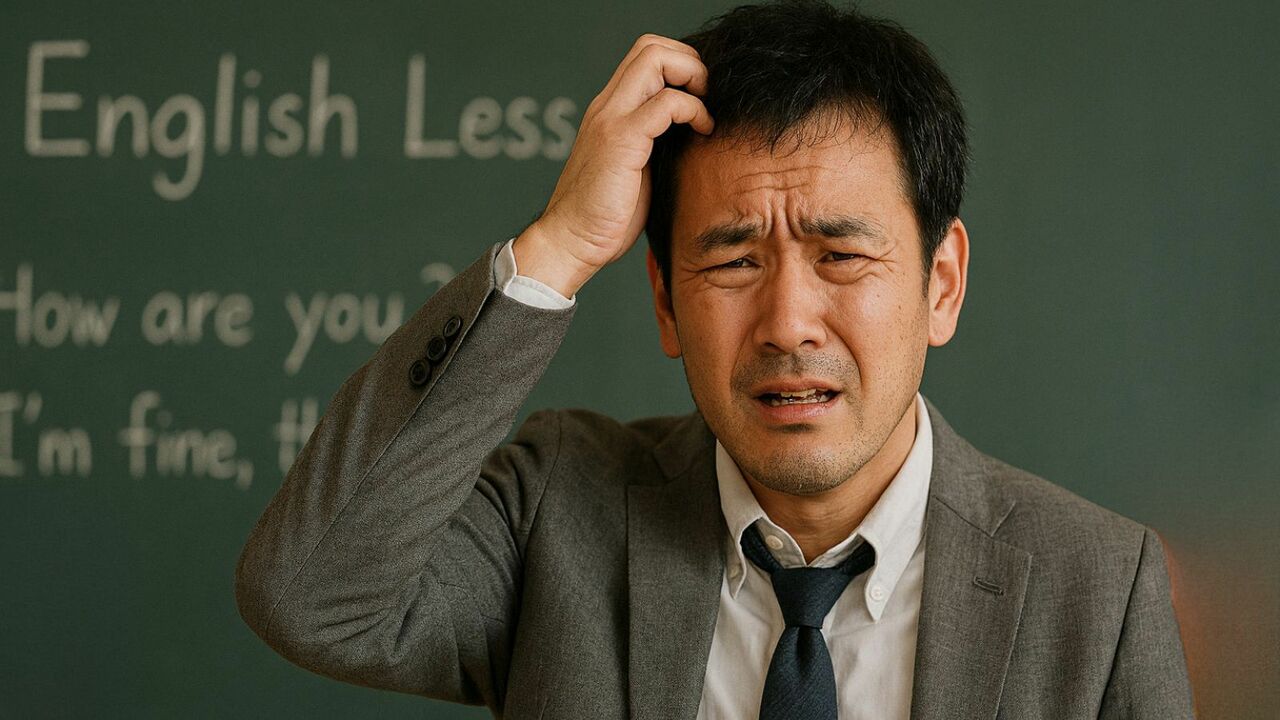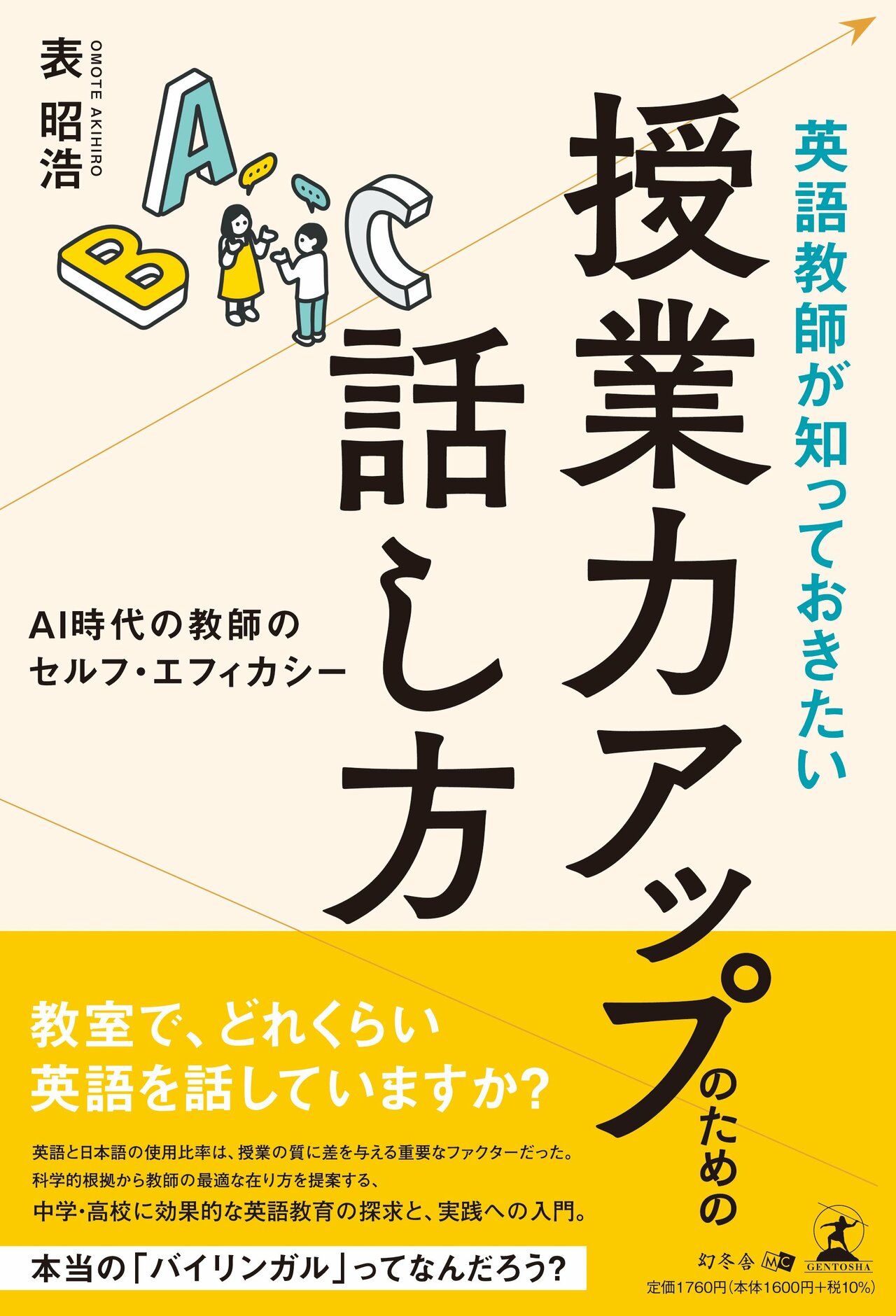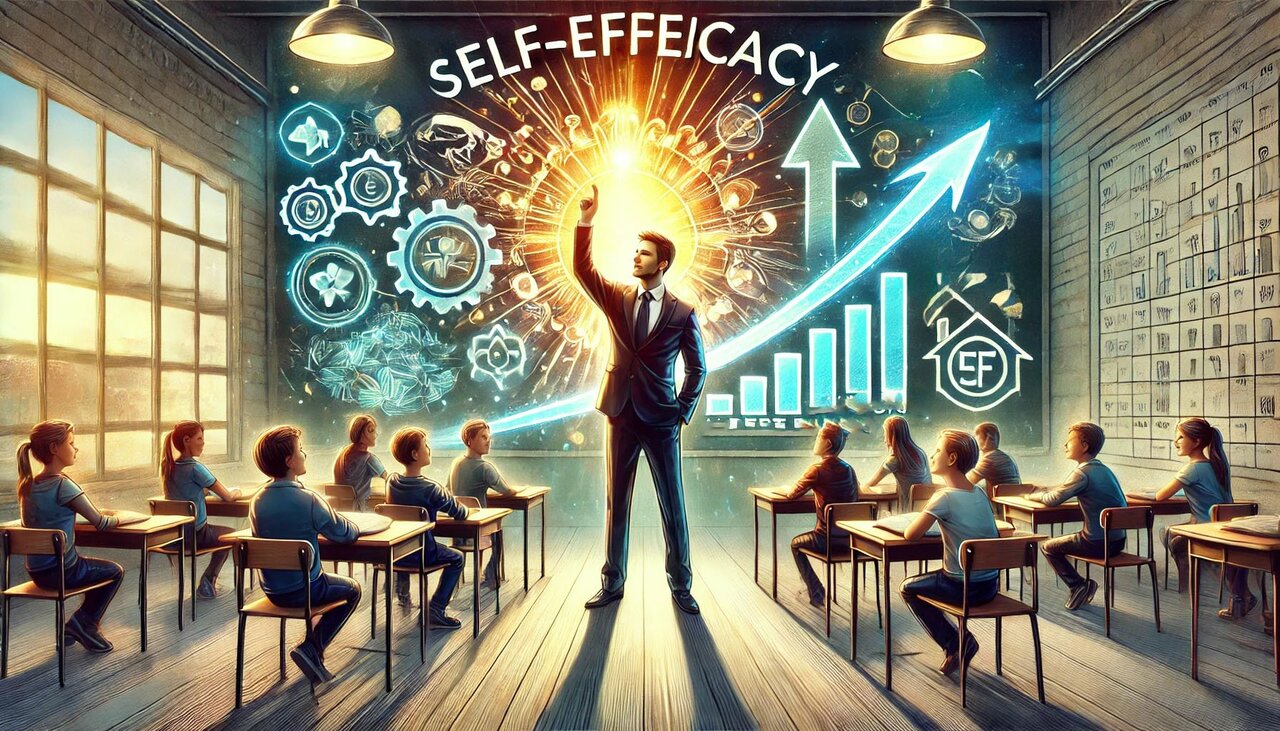【前回の記事を読む】米国の心理学者Banduraが提唱した理論「セルフ・エフィカシー」は自己調整的な教師の行動の予測にも役立つ
第1章 英語教師は英語をどう教えているのか
第2節 教師の話し方について何がわかっているのか
第3項 教師のセルフ・エフィカシー(TSE)と適応行動
2000年以降になると、米国をはじめ、東西アジアや欧州の研究者によっても、Banduraの三位相互決定説に基づく特異性やセルフ・エフィカシーに着目しつつ教授行動の適応性を探ろうとする研究が数多く見られます9,10,37,61,68,114,135,137,146。
それらの先駆けとなり、その後もよく取り上げられているものが米オハイオ州立大学のTschannen-MoranとWoolfolk Hoy夫妻の研究です125,126,127, 142。
彼らは、Banduraの理論を基に、教授行動の判断の元となり学習に良い影響を与えているという感覚を教師自己効力感と呼び、上述した4源泉との関連等についても継続的に論じました。よって本書でもこれからこの定義にしたがい、この教師自己効力感(teacher self-efficacy)の頭文字を取ってTSEと呼ぶこととします。
近年では、Pfitzner-Eden(2016)が、4源泉がTSEの発達にそれぞれどのような影響を与えているのか検討しており、教師が感じる効力感の経路にも、
(1) 自らの行動で目標達成できているという認識(「成功経験」)をはじめ、(2) 信頼に足る他人(生徒や他の教師達)との信頼関係から得た次の行動への自信(「社会的説得」)、(3) 他人の教授行動の観察からのモデル化(「観察経験」)、(4) 感情や体感を通じてできそうだ、あるいはできそうにないとする認知(「感情と生理的体感」)の4つの具体的源泉チャンネルを特定しています101。
ところで、TSEについての科学的検討を行うときは、必ずしも効力感があるときのみに着目するのではなく、効力感が無い、あるいは減衰するときの状況も同様に探っていくことが重要です。
例えば、国内でTSEを研究した渡邊・中西(2017)の研究では、TSEは成功の積み重ねのみで恒常的に維持されるものではなく上手くいかなかった行動を通じても考えるべきだとして、TSE研究における失敗の経験の重要性を指摘しました134。
また、丹藤(2005)は、TSEは学習者の望ましい変化による目標達成の経験のみならず、教師が時に苦いマイナスの経験をすることで葛藤や問題意識の克服に至り、そのときのTSEの変動が時間と共にもたらす行動変容によって教師の成長が促されるのではないかとしています。
これらのことから、日本人英語教師も学校や教室での様々な状況の下、個々の学習者からのフィードバックを繰り返し得ることで失敗や成功を繰り返し、「成功体験」「社会的説得」「観察体験」「感情と生理的体感」の4つの源泉を通じて、折に触れセルフ・エフィカシーを感知(perceive)しながら、主観的なTSEの変動を経験しているのではないかと考えることができます。
これを具体的な教師の姿に例えれば、以前の学校で上手くいっていた経験から比較的安定した効力感を得ていた教師が、異動先の学校では同じ行動が全く上手くいかずに葛藤が生じて効力感の変動や下降を経験することが考えられます。
英語教師についてもこの4源泉を手がかりとして、質問紙や面接法によって一般的な傾向を探ったり、教師の固有の体験(事例)から得られた結果を統合して考察したりすることで、TSEがどのように教授行動に関与しているのか、特に、教授目標を達成しようと努力する中でどのように日本語行使を減らし、英語行使を拡大させてIS行動を適応させているのか、すなわちバイリンガリズムの専門性向上にTSEがどう関係しているのかを探ることができます。