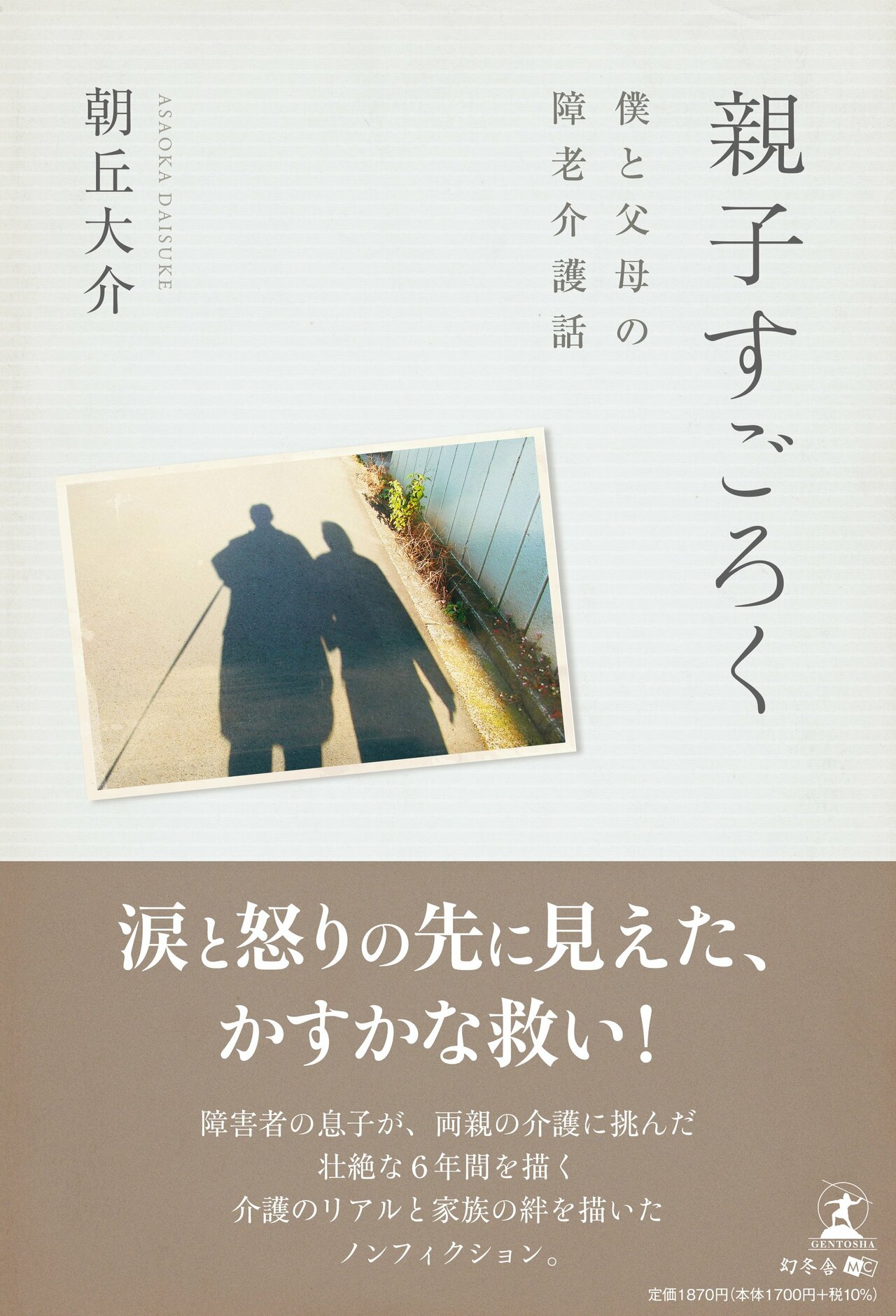老けたのは事実なので、そうするよりほかなかった。一階のロビーでコーヒーを奢(おご)り、彼らの近況報告を楽しんだ。骨盤の粉砕骨折も修復し、三日前からトイレ以外も車椅子で動いてよいことになっていた。見舞客はさまざまな物を置いていき、おかげで枕元は菓子や雑貨で埋まった。
見舞客が帰ると、すぐに眠りについた。骨がつながっても、微熱はまだ続いていた。どういうわけか面会の数が増えれば増えるほど、病棟スタッフの僕への対応はよくなっていった。世の中そういうものか。
日曜の病棟は静かだった。スタッフの数もすくなく、ふだんなら外来患者でごった返している廊下も人影がまばらだ。特にやることもない。
となりには、食事制限のある小太(こぶと)りの中年がいる。奥さんが見舞いに来ている気配がした。
と、突然ベッドが揺れた。となりのベッドとの仕切りのカーテンが盛り上がっていて、その盛り上がりが僕のベッドを徐々に押している。夫のためにすこしでも陣地を拡(ひろ)げようという、涙ぐましい夫婦愛か。当分帰りそうにない。
うんざりして目を瞑ると、何者かが足元を揺さぶった。目を開くと、よく知っている顔がこちらを見ていた。オットセイのような顔をしている。高校時代の同級生、内田だ。
「おお、よく来た」
内田に会うのは昨年、奥さんに殴られて鼓膜が破れた彼を耳鼻科に連れていって以来だ。社会人になり人間関係が複雑になった今でも、一緒にくだらないことができる数すくない友人だった。
【前回の記事を読む】上の者にはヘコヘコ、患者や後輩には「教育」と称してボロクソに言う百九十センチ二十代半ばの男性看護師