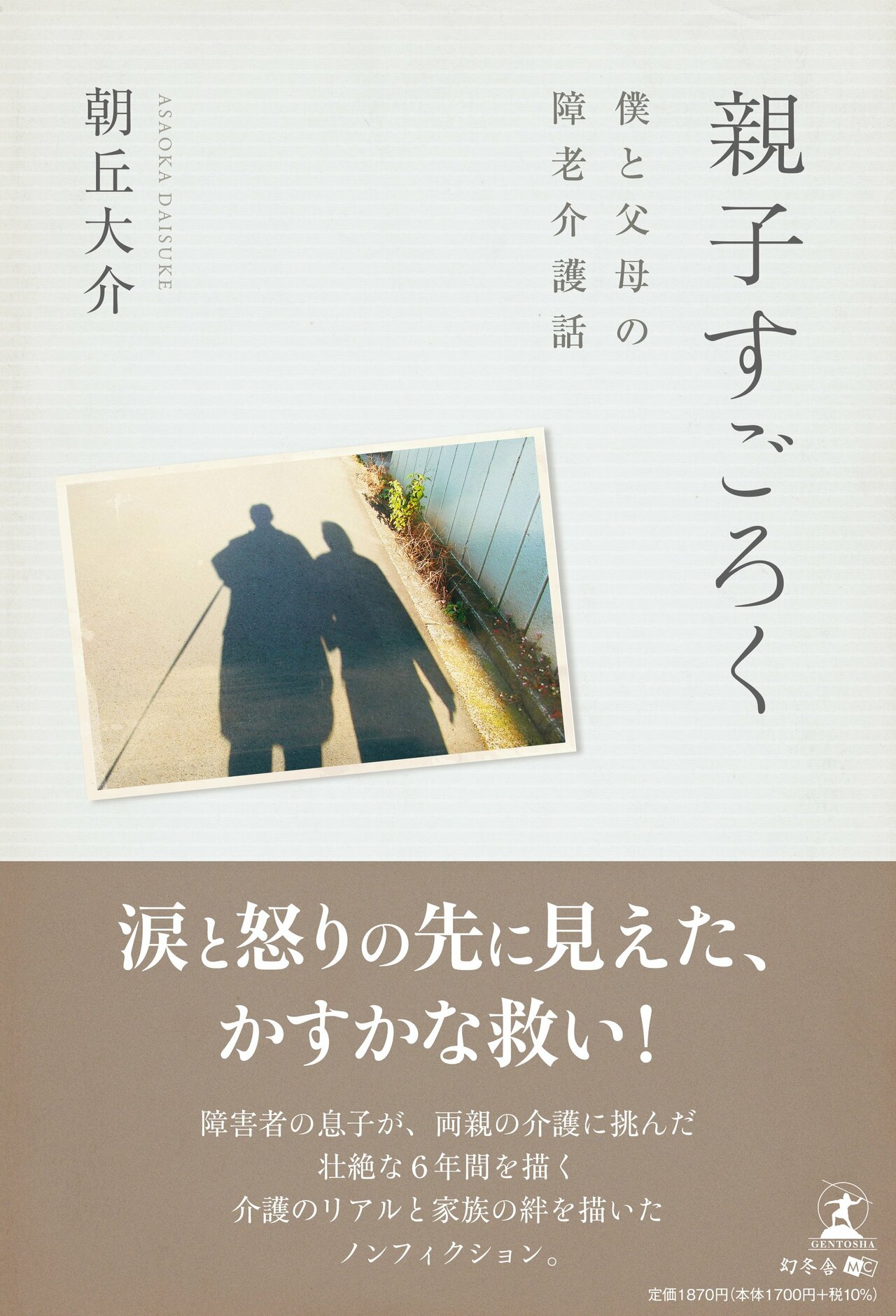港口整形外科
「傷が深いだけだと皮膚科の先生が言っていましたが」
「彼はまだ若いから……」
石橋院長は口ごもると、視線を逸(そ)らした。
「ダメなんだよ、お前は!」
膝の処置をする若い小さな看護師を院長が怒鳴った。どうやら機嫌を損ねたようだ。
院長が直々(じきじき)に肘の創処置をする。
「……あの……そんなにきつく擦(こす)られると痛いのですが」
「わかってるんだよ、そんなことは!」
今度はこっちが怒鳴られた。だったら、痛くないようにやれよな。心の中で僕はぼやいた。続いて、小さな看護師がアイスの棒のようなヘラで傷口に軟膏を塗りはじめた。
僕は自分の左肘を見た。細長い毛が数本、ホッチキスで留められた傷口を覆うように生えていた。人間の体は大切な所を毛で守ろうとするものなのか。それとも、毎日塗ってもらっている薬が関係しているのか。看護師が塗っている薬の容器を見ると、〈亜鉛華軟膏〉と書いてある。
包帯を巻く小さな看護師一人を残して、院長一行はとなりのベッドへと移っていった。
眠気がやんわりと僕を襲う。うつらうつらしているうちに、石橋院長の大名行列は病室からいなくなっていた。
「来見谷さん、起きてください。昼食ですよー」
ヘルパーに叩(たた)き起こされ、ぼんやりしながら体を起こして、枕元の床頭台にはめこまれたスライド式のテーブルを引き出した。昼の献立は、ご飯、味噌汁、あじの塩焼き、ほうれん草のおひたし、茄子(なす)のしぎ焼き。
僕はさっそく味噌汁に七味をふり、啜(すす)りこんだ。舌先にピリピリとした刺激があった。ほかの患者たちもカーテンの向こうで食べはじめている。クチャクチャ、ズズーッという音が耳に触れる。自分が囚人であるかのような錯覚をおぼえる。
カーテンの向こうでは、となりの糖尿病患者が「ちきしょう」、「いっけねぇ」などと、ひとりごとを漏らしている。この人はときどきヘンな寝言を言う人で、「……ちきしょう、ヘンリーの奴ッ! ひどいや」、「……ハイジは老人を殴りました」などとつぶやいては、クスクスと笑っている。
食事が終わり、痛み止めを飲んでいると、白衣を着た大男がワゴン車を押して入ってきた。平岡という二十代半ばの看護師だった。百九十センチはある。