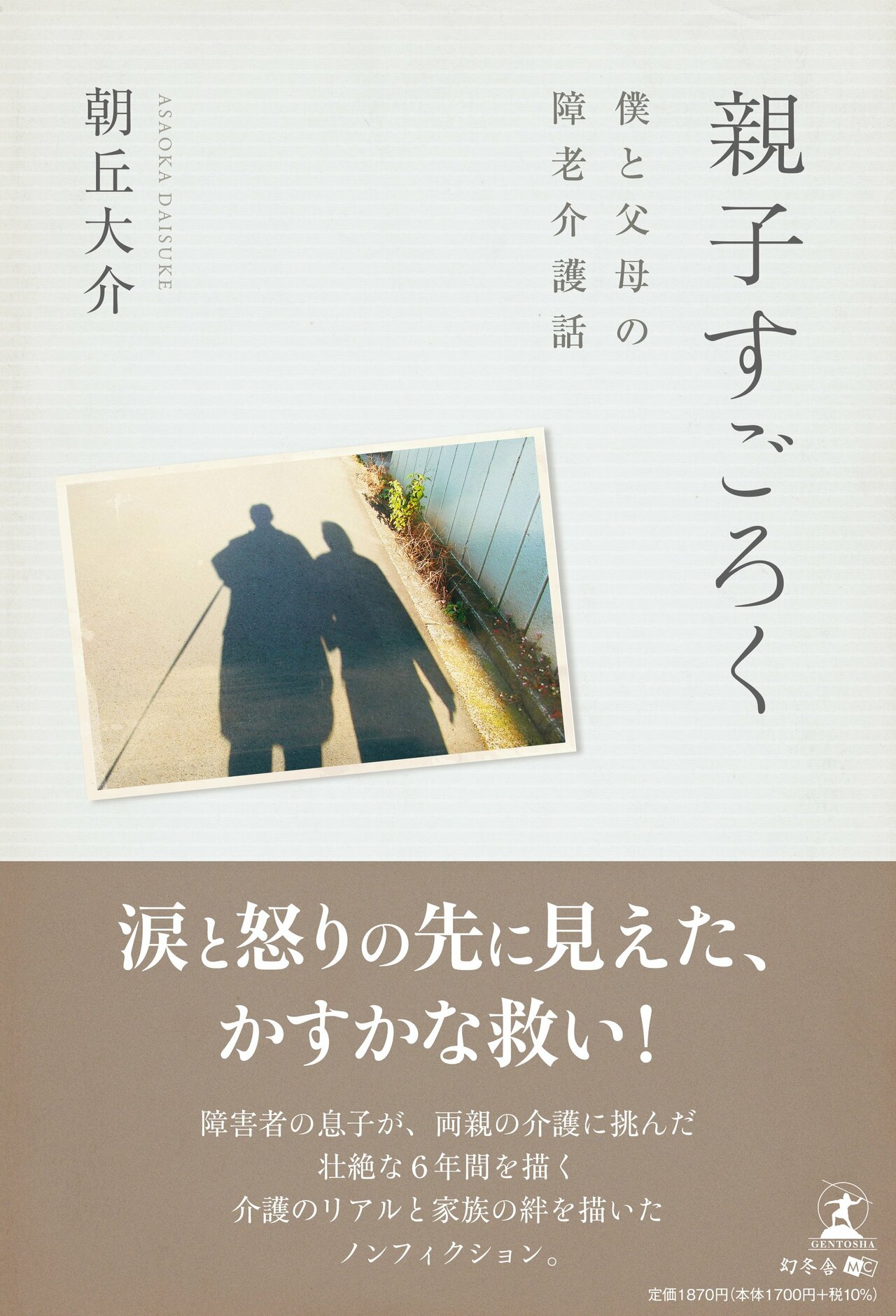夢の中
長い夢の中を僕は彷徨っていた。
柔らかな光に包まれた、まっ白な世界。足元からはるか上方へ石段が続いている。
その石段を僕はゆっくりとのぼっていた。年寄りのように丸まった背中には、なぜかリュックサックを背負っていた。上へのぼればのぼるほど、リュックサックは重たく背中に圧しかかった。
さまざまな人がやってきては、代わるがわる錘を入れていく。錘が入れられるたびに、さらにズシリと圧しかかる。それでも僕は何も言わない。
一歩一歩よろめきながら、黙って石段をのぼっていく。どうして上を目指さなければいけなのか、なぜみんなの錘を背負わねばならないのか、わからなかった。
♬ 九十九まで数えてダメなら
九百九十九まで数えてダメなら
よろめきながら、石段をのぼっていく。一段。また一段。上にのぼるにしたがって、石段は左右の幅が狭まり、傾斜が急になっていく。
♬ 九千九百九十九まで数えてダメなら
九万九千九百九十九まで……
さらにのぼっていく。全身が重くなってくる。
僕は泣きたくなった。手足は枯れ木のように細く萎え、顔はやつれ、髪はパラパラと抜け落ちていく。後ろをふり返ると、石段のはるか下方にぽつんと子どもが立っていた。あどけないおかっぱ頭の少年は、僕だ。まだ人を疑うことを知らない、澄んだ目でこちらに微笑んでいた。
ふいに膝をつきそうになった。つんのめるように石段に手をつく。
もうだめだ。体が重い。寒い。
-
薄ぼんやりとした意識の中で、僕は天井を見ていた。まわりは淡黄色のカーテンで囲われている。月のような薄明かりが、やさしく顔を照らしている。白い靄が視界を覆っている。天井からぶら下がったふたつのビニールパックから、透明な雫がポトリポトリと落ちている。落ちた雫は管を伝い、腕に挿しこまれた針を通って僕の中に浸みこんでくる。ベッド柵には尿袋が掛かっている。
急に意識が冴えてくる。リアルな夢の中にいるようだ。全身が動かない。呼吸をするたびに体中が痛い。
だるい。
寒い。
自分が置かれている状況がわからない。
ただただ点滴が落ちていく様を見つめる。あたりは海の底のように静まり返っている。
僕は観念した。薄れゆく視界に人影が映った。
白衣の女性が立っている。赤い髪をした女性が悲しそうな目で、僕を見下ろしていた。
「殺されど、殺されど、我また殺される……」
僕はかすかにつぶやいた。
次に意識が戻ったとき、目に入ってきたのは白い天井だった。