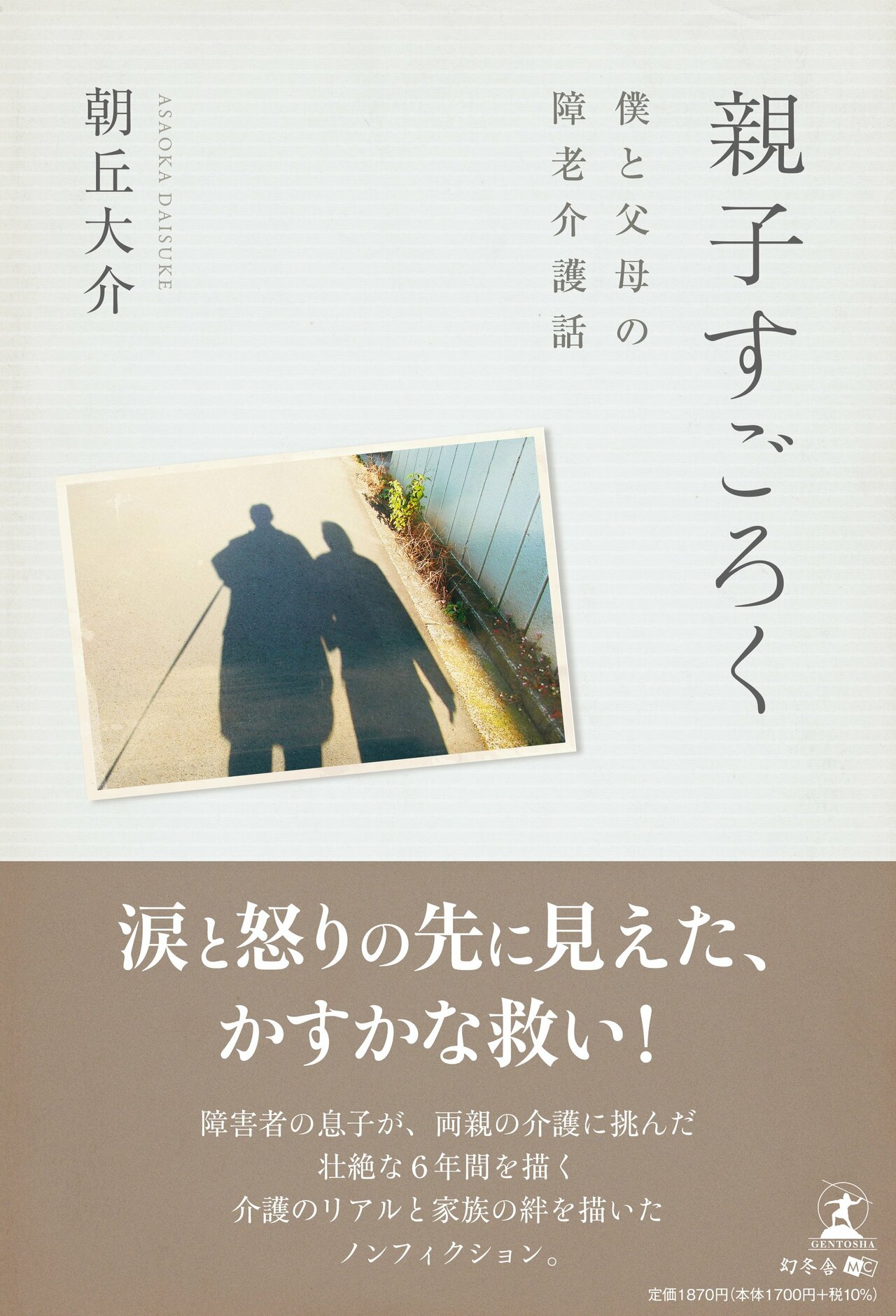ベッドの右手には、十四インチのテレビがのった床頭台。台にはスライド式のテーブルがついていて、その上に育毛剤ヘアハゲーンとたこ焼きスナック・タコちっちの甘辛ソース味、それから見覚えのある携帯電話が置いてある。いつからこのベッドにいるのか、もうどれくらいこうしているのか、まったくわからない。すこし前まで違う部屋にいたような気がする。はっきりした根拠はないのだが、たしかにあれは別の部屋だった。
いったい誰がここまで運んできたのか、どうして今ここにいるのか、まるでわからなかった。
何をする気も起きない。
体が底なしにだるい。
誰かがやさしく肩を揺さぶる。目を開くと、若い女の人が顔を見ていた。色が白い。茶髪だ。
「あなたのお名前は?」
「………………くるみや………………ゆう……と」
「お年はおいくつですか?」
「………………さんじゅう……………よんさい?」
「ここはどこですか?」
「………………………カマタ」
「もう一度聞きますよ。来見谷さん、こ・こ・は・ど・こ・で・す・か?」
「……………イバラ…キ…?」
考える気力もない。そのまま吸いこまれるように、僕は深い眠りに落ちていった――。
-
「看護婦さーん!」
カーテンの向こうで、老人の地獄のような叫び声が聞こえる。あたりはまっ暗だった。
「看護婦さーん! 看護婦さーん!」
痰のからんだ塩辛声。ベッド柵をガンガン揺らす。このいがらっぽい叫び声は、いつも僕を悩ませる。
「うるさいな!」
僕は何度か怒鳴ったが、まるで聞こえていないのか、爺さんは叫び続ける。
「看護婦さーん! 看護婦さーん!」
天井がグルグルと回っていた。
-
目を覚ますと、となりに男がいた。いつも見る丸顔だ。
「体位変換するから、その前に体を動かすよ」
「……イタイ、左足のつけ根がもろにイタイ」
男が、僕の足をかかえて動かしている。馴染みのある白衣だ。
「左の股関節が外側に向いちゃってるね」
言いながら、男は僕の足を動かす。同じ三十代のようだ。
「来見谷さん、理学療法士なんだって?」
「……うーん」
「だったら、このままウチで働いちゃいなよ」
足を動かされると、腰から股間にかけて突き刺さるような痛みが走る。
「イタイ、イタイ」
「ごめんねぇ~。痛いよねぇ~。もうちょっとだからねぇ~」
男は、僕の足をゆっくりと動かした。
「アイタタタ、体、動かさないでください」
「終わったよ。足が変にならないように、枕で固定しておこう」
体勢が整うと、僕はやや落ちついた。
「それじゃ来見谷さん、また来るね」
遠くでサイレンの音が鳴っていた。