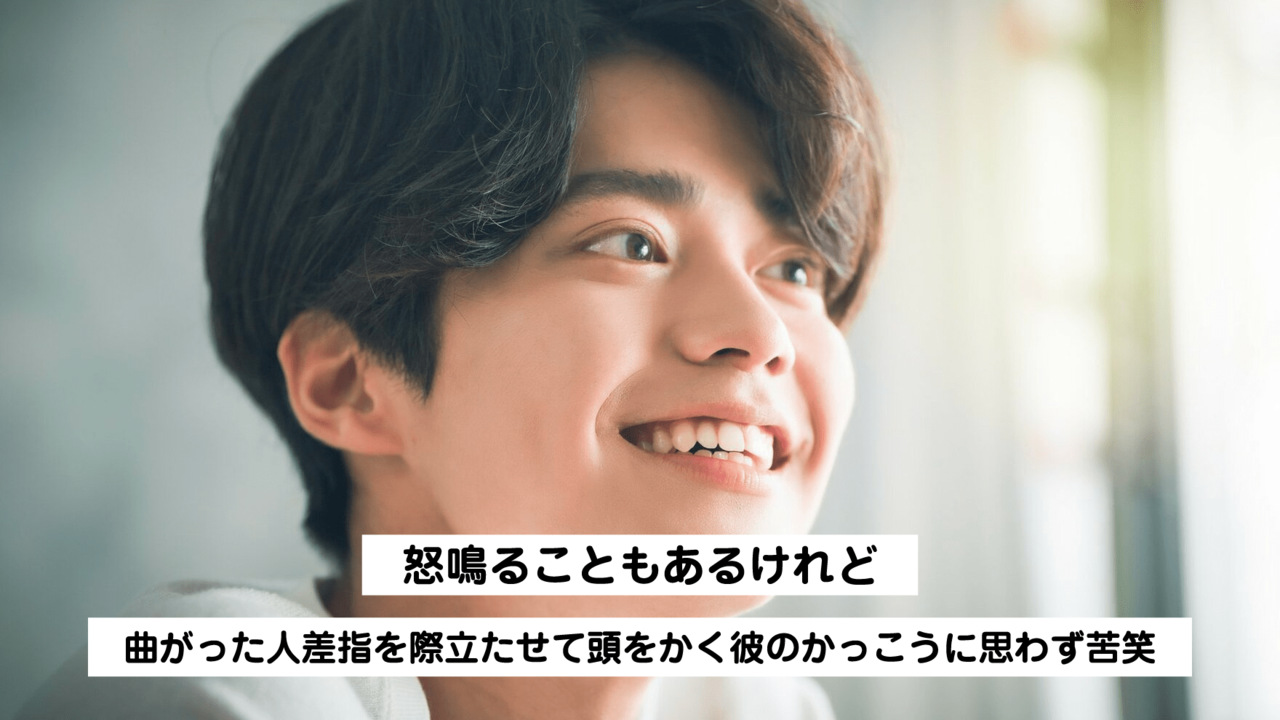(一)
当時毛利という満語の上手いのが居て満服を二着手に入れ保に「一緒に逃げ様、奉天には知っている人が沢山居るからどうにでも後はなるさ。船に乗るまでだ。満人に追いかけられたら河へ飛び込むんだ、さあ」と毎晩となり合った毛布にくるまってささやいたがどうせなる様にしかならぬと思っていた保には命をかけて大陸の端まで行く冒險も恐ろしく、かえって彼の逃亡行に反対し、ついに彼もカラカンダまで来てしまったのだが。
敗戦寸前、東京入営以来一緒だった一寸頭の可笑しい、それこそ員数で兵隊に出された塚本が、新京へ転属させられる日の夕べ、兵舎の裏で保に別れたくないと泣いていたふるえる肩のはるか彼方に紫色に煙った峨々とそびえる千山が美しく目に映えた事等を憶出した。
塚本は皆のわらい者ではあったが妙に保になついて居り、高梁畑を練兵場にする時等、春とは言えまだ浅い三月初め防寒帽を被ってチョコレートの様な固い茶色の土塊に鶴はしをあてながら、「さあ塚本、おれについて言うんだ。一つわがくにのぐんたいは。言って見ろ」
「一つええと何だっけな、あんたが言う時はおぼえる様な気がするけどおれの口からは仲々出て来ないんだ」
教官や戦友が彼を馬鹿にするのに感じた若さからの憤りとでもいったものから保は演習作業は、何時も彼と一緒に働いた。軍隊という異常社会へ入った緊張感からか、保は課された学課も二度読めば丸暗記できるのだった。教官、古年兵も保と塚本はいいコンビと思ったのか何んでも一緒にやらせてくれた。
だが保も終いにはじれて「お前みたいな奴が兵隊になったのがそもそもの間違いなんだ」と怒鳴るけれどギヤに挟まれて曲った左の人差指を際立たせて頭をかく町工場の工員塚本のかっこうに思わず苦笑して「さあもう一度だ。一つ我国の……」。