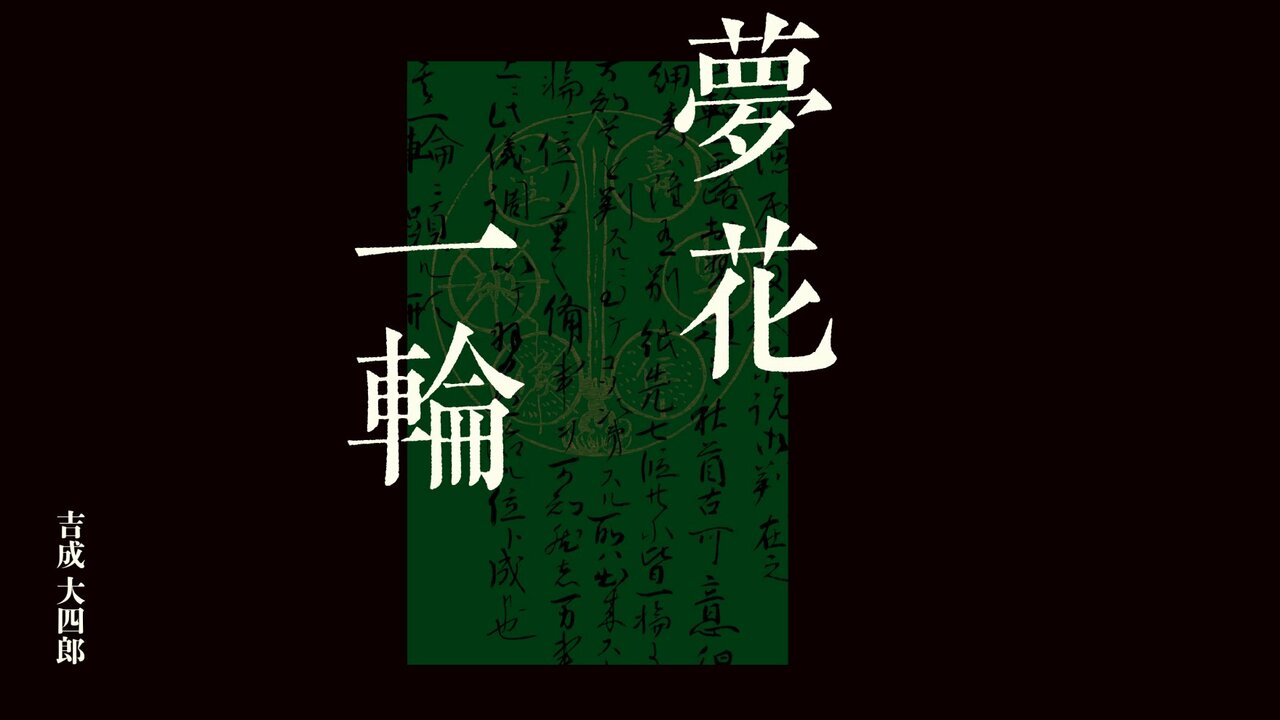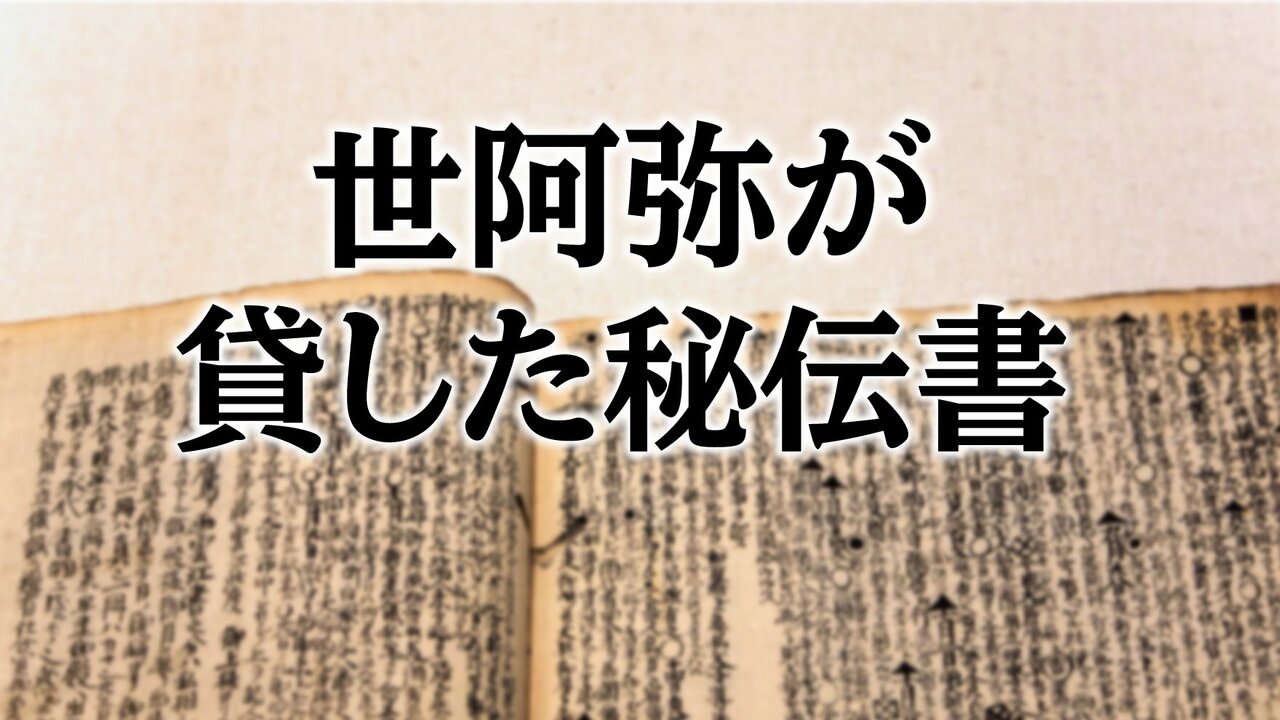四
ある日のこと、弥三郎は世阿弥の居室に招き入れられた。
日頃から、謡や舞の稽古を世阿弥が直(じか)に見てくれるということはない。何か大事な話があるのでは、と弥三郎は緊張の面持ちで深々と頭を下げた。
「これを見てほしい」
そう言って世阿弥が差し出したのは、一冊の書である。『神儀云(しんぎにいわく)』と書き出されたそれは、猿楽の来歴を詳(つまび)らかに書き著したものであった。
「大夫を務めるほどの者なれば、このようなことは大方承知しているものじゃが、何といっても円満井座は大和の中でも最も古い家柄、わしの知らぬこともあるかと思い、御身に教えを請いたい」
弥三郎は世阿弥の丁重な物言いに驚きつつ、改めて気を引き締めた。
観世は山田猿楽の流れから出た新しい家であるという。このようなことについての秘事の伝承は持たぬゆえ、他座の大夫の子である弥三郎を手厚くもてなすのにもそれなりの理由があるのだった。
弥三郎は、とっさに深い洞察はできなかったものの、世阿弥の依頼をはねつけるのも、全く無防備に手の内をさらけ出すのもまずいのだということを本能的に感じていた。
しばらく考えを整えてから、弥三郎はゆっくりと自分の知る限りのことを世阿弥に語って聞かせた。仏在所や神代の伝承、秦河勝からの流れと翁の来歴。ただし最も大事の、隠された神のことだけは触れずにおいてある。
世阿弥は弥三郎の言葉を噛みしめるように深くうなずきながら聞き終わると、深々と一礼した。
「かたじけないことじゃ、やはり御身の座は格別のものと改めて感じ入った」
思わぬ世阿弥の厚い礼に恐縮し、弥三郎も頭(こうべ)を垂れる。
「返礼というのもおこがましいが、この一書を御身にお貸ししようと思う」
そう言って世阿弥はさらに別の書を差し出した。それは書名と内容の概略のみ十郎から聞いて知っていた『風姿花伝(ふうしかでん)』であった。観世の家の大事の秘伝書であり、弥三郎が何としても一見したいと渇望していたその書である。
弥三郎は今度こそしびれるような感激に包まれ、平伏した。
この『風姿花伝』こそは、すべての出発点であった。
弥三郎が借りて筆写したのは『年来稽古(ねんらいけいこ)条々』『物学(ものまね)条々』『問答(もんどう)条々』の三篇であるが、能の基本の要諦はほぼ尽くされているように思われた。
能を学ぶ者が生涯の指針として常に心に留めるべき内容なのだ。
それはまた、大事の書であるがゆえに秘さねばならぬものでもあった。