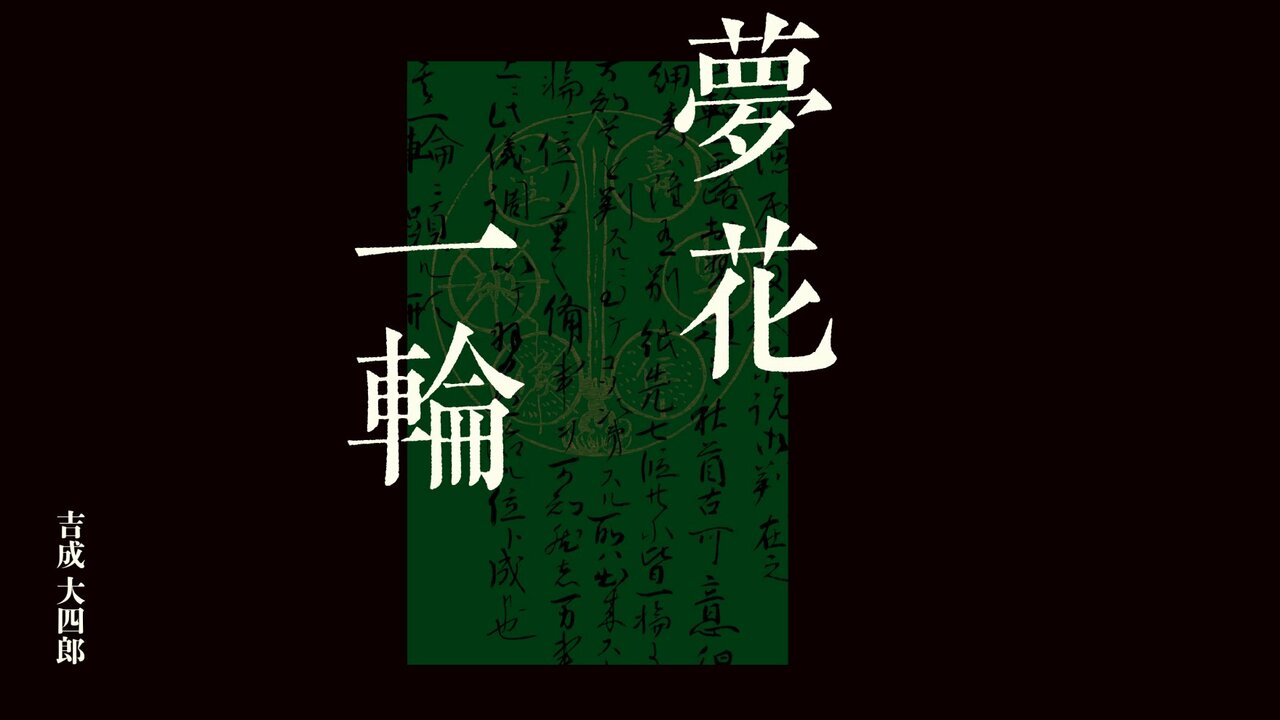第二章
三
世阿弥殿の娘御を娶とるのじゃ、と大蔵大夫から言われたとき、氏信は、は、と間の抜けた返答をした。
世阿弥の娘とはすなわち、あやめのことだ。
あやめが自分の妻になる、ということがすぐには腑に落ちず、それはまことでございますかと聞き返しそうになり、危うく思いとどまった。
大蔵大夫は祖父の金春権守亡き後、氏信の後見をしてくれている人である。
このようなことについていい加減なことを口にするはずはない。すでに世阿弥との間で確かな約束を交わしているに違いなかった。
承知いたしました、何卒よろしくお願い申し上げます、と深々と頭を下げながら、氏信はにわかに胸が騒ぐのを抑えきれなかった。
氏信は、弥三郎であった昔から、あやめのことが好きであった。
だからこの縁談は天にも昇るような幸せのはずなのだが、それでもすぐに浮かれて舞い上がる気持ちにはなれなかった。
あやめの心中がわからぬからである。
世阿弥が決めたことならば、あやめがそれに従わぬということはありえない。たとえ意にそまぬ縁談であったとしても。
あやめに嫌われているとは思わない。
どちらかといえば好かれているであろうと思う。
しかし婿むことして迎えるとなればどうなのか、夫婦として添い遂げる相手としてどう思われているか、そう考えるとまるで自信が無いのだった。我ながら青臭い悩みだと思う。
これは観世座と金春座の縁を固める大事の婿入りなのだ。
どちらにも不足などない立派な縁組である。当人同士の気持ちなど些細なことだ、頭ではそう考えながら、どうしても気持ちが落ち着かないのだった。
そうして割り切れぬ思いを抱えたまま日を過ごしていたが、婿入りまで数日と迫ったある日、氏信はついに思い立ってあやめを訪ねた。
あやめは彼の顔を見ると驚いたように目を見開き、それからいたずらっぽい笑みを浮かべた。
「弥三郎……いえ、氏信様」
「弥三郎でよい、あやめ」
「今日は急にどうされたのです、婿入りが待ちきれなくなったとか」
「からかわんでくれ、わしは真面目なのだ」
「存じておりますよ、弥三郎殿は昔から真面目ですもの」
「だから……いや、そうだな、わしは昔から不器用で、こんなときにうまい言い方もできぬから、まっすぐに聞くぞ」
「はい」