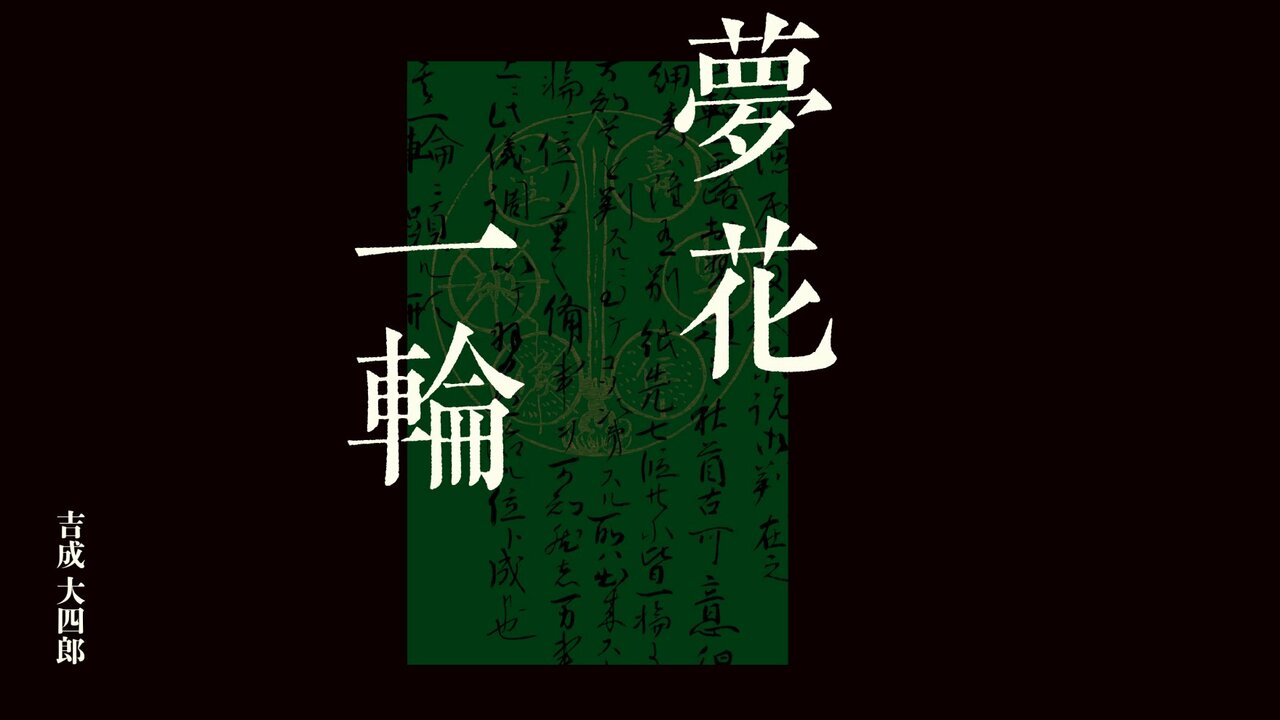第二章
二
あの頃から、長年世阿弥と元雅の背中を追い続けてきて、その距離を少しは縮めることができたのか、氏信はいつまで経っても自信が持てないでいる。
元能の書き物の理由を知ったのは、ずっと後になって、出家の決意を打ち明けられたときのことだった。能の芸において元重や元雅に遠く及ばず、能作の才も無い自分が何かの役に立てるのだろうかと悩んだ末に、元能なりに出した一つの結論であった。
世阿弥が伝書に書き著したことどもは珠玉の教えであるが、書物に残らない言葉も多い。その貴重な教えを少しでも留めておくことは大変に価値のあることなのではないか。
そう考えて父の言葉を折に触れて書き留めたものを、最終的には一冊の聞き書きとしてまとめ、出家の際に家への置き土産としたのだ。その書の名を、『世子(ぜし)六十以後申楽談儀(さるがくだんぎ)』という。
氏信は当時『申楽談儀』を直接読むことはなかった。元能の口から聞いたことがことごとく記されているのを、ずっと後に知ったのである。
能の世界で名を馳せた名人たちの話、能を演ずるにあたって知っておかねばならない決まりごと、「位」や「かかり」など、にわかには掴み難い事柄もあれば、謡の節や舞の手の具体的な説明もある。
また、能作や、能の演じ方についても事細かに語られていて、その中には氏信も世阿弥から直に教えられたこともあり、逆に全く知らずにいたこともあった。
世阿弥が、婆娑羅(ばさら)大名として名高い京極道誉(きょうごくどうよ)と面識があったことには驚いた。まだ少年だった頃に側に侍り、色々と話を聞いたという。田楽本座の大夫、一忠のことも道誉の話からその芸風を推し量ったそうだ。
それによると、伝説の名手一忠は「しゃくめいたる為手」だったという。聞き慣れない言葉だが、雰囲気はわかる。思いに打ち沈んだ女の面を曲見(しゃくみ)というように、しゃくれたような、くせのある感じなのだろう。
そうかと思えば、とても具体的な技の説明もある。反り返りは、腰と膝で返る。張った弓の弦を外すようなものだ。時の間にちらりと返る。
そのとき、後ろに露ほども身が残ってはいけない。これなどは型を身につけた者ならば誰にでもわかる、見事な説明である。それらの中で、最も印象深かったのは、元雅が書いた能についての話であった。
『隅田川(すみだがわ)』の能は、元雅が心血を注いで書き上げた、彼の魂というべき能である。我が子を人買いに取られて物狂いとなった母が、都からはるばる東国へと旅をする。
そうして差し掛かった隅田川を渡る舟の中で、船頭は哀れな子供の最期を物語る。その日からちょうど一年前、人買いに連れられた幼い子が病を得て空しくなり、川のほとりに葬られた。
その子こそ、生き別れになった我が子であることを悟った母は、塚の前に泣き崩れ、我が子を返させ給えと塚にすがりつく。そのとき、塚の陰から子供の亡霊が現れ、母と言葉を交わす。
『声の内より、幻に見えければ、あれは我が子か、母にてましますかと、互に手に手を取りかはせば、また消えきえとなり行けば』
ここの演じ方で世阿弥と元雅の間に論争があったという。元能は氏信ならどう思うかと伺うようにそのときのことを語った。
「父上は、子の亡霊は人に見えぬものなのだから、子方として舞台に姿を見せるべきではないと仰る、しかし兄上はそれではとてもできませぬと頑なに仰るのじゃ」
二人の間に挟まれて困り果てる元能の姿が目に見えるようであった。