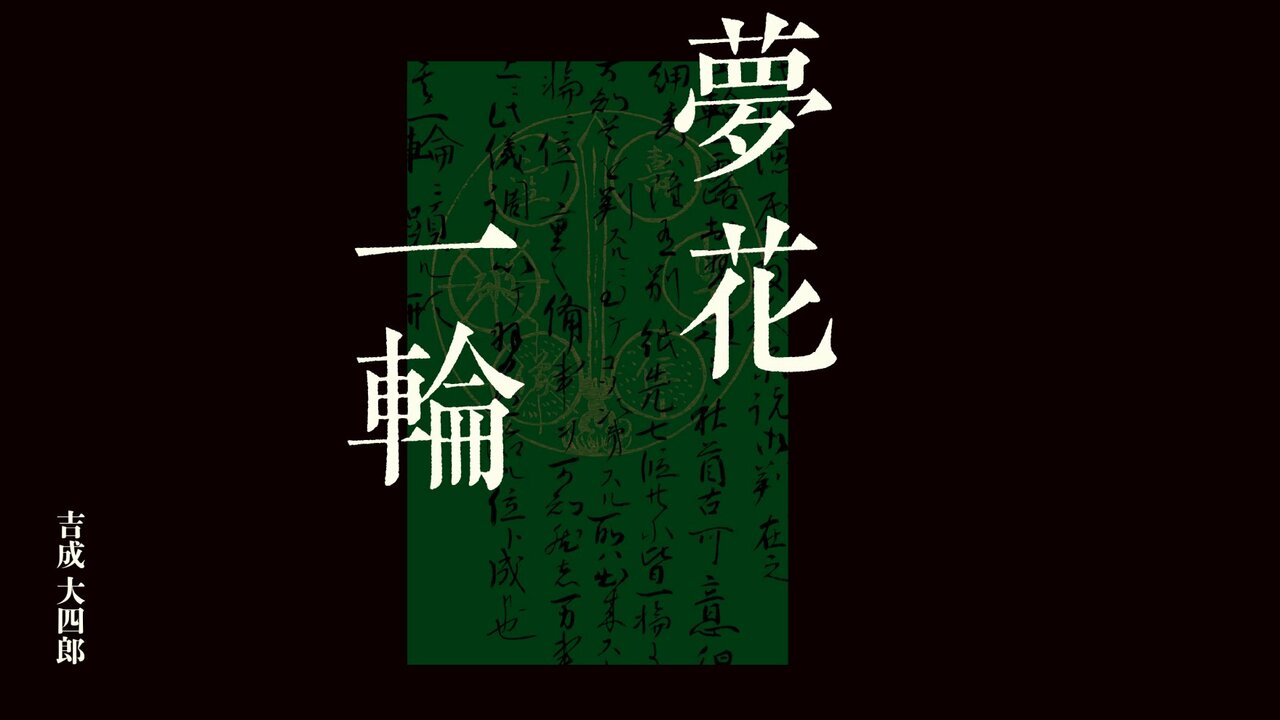一
巌のような人だ、と弥三郎は思った。小柄だと聞いていたのだが、全くそうは見えず、こちらへのしかかってくるような力を感じ、その足元へ向けた目を逸らすことができなかった。
「弥三郎殿の子じゃな」
低く、よく通る声が耳を打つ。
「はい」
弥三郎は軽く手をついて礼をした。
「お父上は残念なことであった、まさかかように早く亡くなられるとは……」
父、金春弥三郎が死んだのは去年の暮れのことで、まだ半年も経っていない。父の名を継いで間もない幼い弥三郎はどのように言葉を返せば良いかもわからず、黙って手を前についていた。
「今日は舞台を助けてもらい礼を言う、こなたも何か困ったことがあれば遠慮せずに申すが良い、同じ大和猿楽なれば助け合うのは当たり前のことじゃ」
年端もゆかぬ少年に向かい、大人に対するような丁重な言葉を使うのは今を時めく結崎座の観世大夫、世阿弥である。弥三郎にとっては憧れの的であり、半ば伝説のような遠い存在に思っていたその人が目の前にいて、自分に対して言葉をかけてくれている。弥三郎は夢の中にいるような心地だった。
「ありがとうございます、どうぞよろしくお願い申し上げます」
それだけは教わってきたとおりの口上を述べて礼をすると、世阿弥は鷹揚にうなずいた。
「舞台のことはすべて三郎に従うが良い、よろしく頼むぞ」
目配せの先にいた背の高い少年がうなずくのを確かめ、弥三郎はもう一度頭を下げると世阿弥の前から退いた。強い緊張から解放されて、ふうっと大きく息をつく。
初めて目の当たりにした世阿弥から強い印象を受けた弥三郎であったが、すぐ後に控えている舞台のことが心をいっぱいにしており、気持ちはすぐに三郎と呼ばれた少し年かさの少年に向いていた。
「こちらへ」
三郎に招かれ、弥三郎は幕屋の内を縫うようにしてその背中を追って行った。すぐ横では鼓の役人が緊張の面持ちで調べ緒を整えている。弥三郎にもなじみの光景だが、張りつめた空気が痛いように感じる。