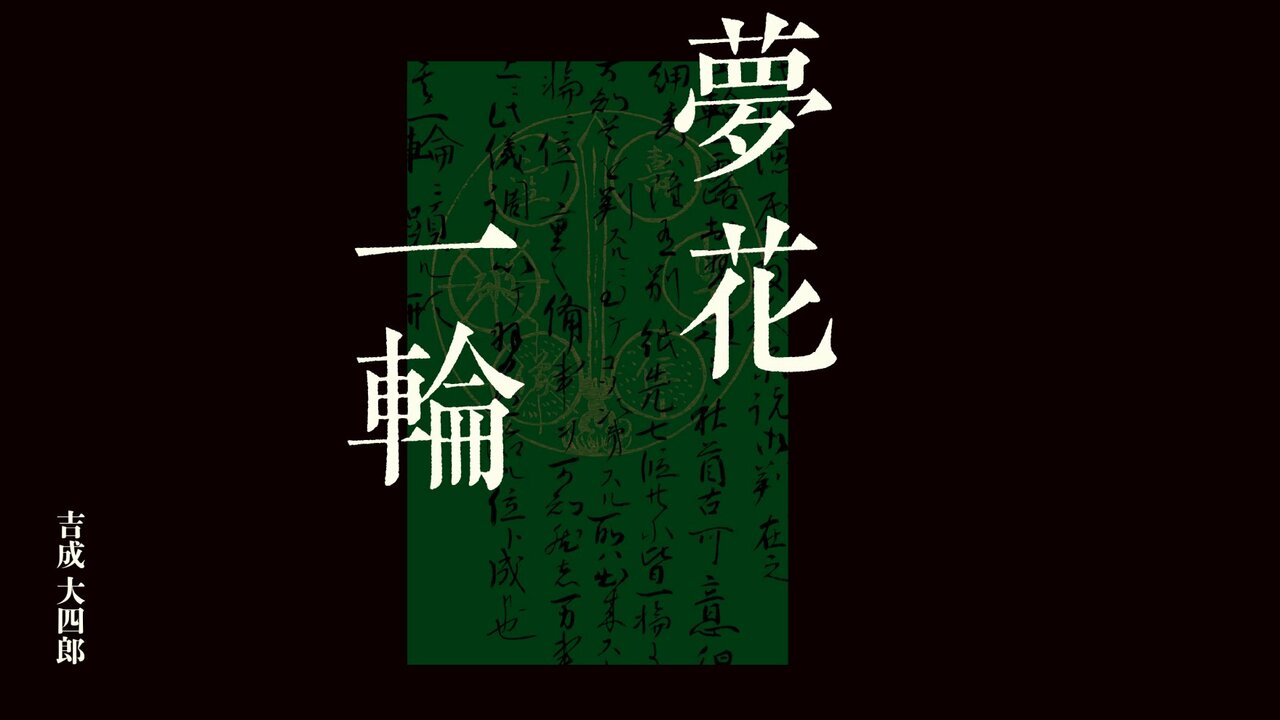一
「どうして、どうして私が能をやめなければならないの」
あやめの悲痛な声が稽古場の中まで響き渡った。
「それが決まりだ」
三郎の声は冷たく、突き放すような厳しさに縁どられていた。
「おなごが舞台に立てるのは幼いうちのみ、本来猿楽は男だけしか舞台に立てぬのだ、そのことはお前も承知していたはず」
でも、せめて稽古だけでも一緒に、そう言おうとして弥三郎は言葉を飲み込んだ。他所の座の自分が軽々しく口を出して良いものではない。それに、あやめもそんなことで満足できるはずがないのだ。
「七郎兄様や、弥三郎より、私の方がうまい」
振り絞るような声が、あやめの口をついてほとばしった。
「あやめ!」
鋭い声が、三郎の後ろで腕を組んでいた十郎から飛んだ。あやめは、はっと身じろぎし、唇をかんでうつむいたが、不意に身をひるがえして駆け出した。
弥三郎はとっさに追いかけようと足を浮かせ、危ういところで踏み留まった。三郎はふっと息をついただけで、もうあやめの去った方を見ようともせず、稽古場の内へ戻っていった。
十郎は少しの間、軽くうつむいていたが、弥三郎の方を見ると小さく頭を下げた。少し離れたところに立っていた七郎は、表情の動きを見せず、軽く頭を左右に振るようにしただけだった。
「あやめのこと、悪く思わんでくれ」
後で十郎からそう声をかけられ、弥三郎は黙って首を振った。
「あれはただ、一途(いちず)に能が好きなだけなのだ」
弥三郎はうなずき、十郎と笑みを交わした。女の身では猿楽の舞台には立てない、それは致し方のないことだ。それとは別に、あやめの謡も、舞も、魅力にあふれていて、舞台に立ちたいという気持ちも痛いほどわかるし、舞台に立たせてみたいとも思う。
女の身でできるとすれば、曲舞(くせまい)や白拍子(しらびょうし)の類(たぐい)があり、その道を習うという手はある。そしてあやめならば、その道でひとかどの者になるのではないかと思われた。
しかし、それはやはり能とは別物で、あやめの本意ではあるまい。また、女芸人にも酒色にまつわる様々なことがあり、そういうことをあやめにさせたくはないという思いも弥三郎にはあった。
それからしばらくというもの、弥三郎はあやめに声をかけることもできず、遠目から様子を伺(うかが)うばかりであった。稽古場に出入りしないのだから、見かける機会も少なくなり、弥三郎は淋しい思いをした。
なぜ猿楽を女がやってはいけないのか、それは弥三郎にとってはあまりに当たり前のことで、改めてなぜ、と考えることもなかったが、猿楽の家のことを思い返すきっかけにはなった。
弥三郎はことに大夫(たゆう)というだけでなく、時が来れば座の長(おさ)ともなるべき家柄の子であったため、一座を受け継ぐ家の秘事にも関わっている。
それは世間に表立っては言わないが、ある隠された神を奉じる教えであり、猿楽の中心をなす『翁(おきな)』に関わることでもある。
その神の名は日常においては秘められており、みだりに口にすれば力を失うのである。その神は翁と一体であり、猿楽の芸はすべてその神に捧げられるものなのだ。