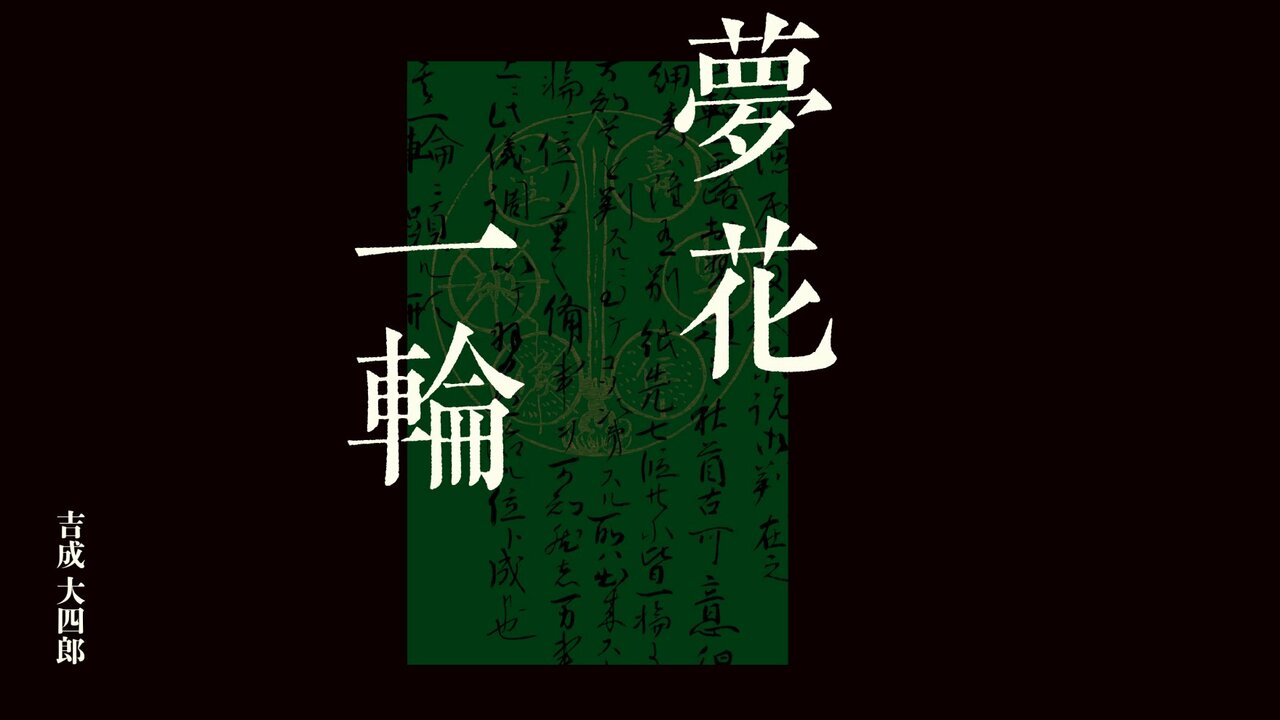一
「弥三郎」
涼やかな、迷いのないきっぱりとした声は、あやめのものだった。
なぜここにあやめが、と訝りつつ、弥三郎は身の置きどころのない恥ずかしさをなんとか押し隠して振り向いた。
稽古場に出入りしなくなってから会うことも少なくなり、久し振りに見るあやめの顔を、今ばかりは決まりの悪い思いで伺う。
「十郎兄様に聞いたのだけれど」
自分でも顔がこわばるのがわかる。
あやめは弥三郎の様子を見つつ、それでもためらいを見せず落ち着いた声で言葉を継いだ。
「海人の玉取りの仕舞を見せたのでしょう」
弥三郎は硬い表情のままうなずいた。
「あれは金春権守殿の能で、口伝のものではないか、と兄様は言っていた」
黙ったまま口を引き結ぶことで暗に肯定の意を示す。
「家の大事のことはみだりに漏らさぬ方が良いと思って途中で止めた、弥三郎が気を悪くせぬよう伝えてほしい、と」
それは弥三郎にとって意外な言葉であった。
十郎は大事なことを惜しげもなく自分に教えてくれているではないか。なぜ自分が同じことをするのを止めるのか。
家の芸を無視されたわけではなく、逆に大事に思ってくれたということには安堵したものの、割り切れない思いは消えなかった。
「私だったら最後まで見せてもらったのに、ねえ、弥三郎、今からこっそり稽古場へ行って……」
弥三郎は改めてあやめの顔をまじまじと見た。能の稽古はきっぱり諦めたと思っていたが、全然変わっていないのだろうか。
「……わかってるわ、稽古場に出入りするのは三郎兄様が認めてくれないし、でも能を見ることまでやめたつもりはないから」
久々に聞くあやめの言いようは実にあやめらしく、弥三郎は不思議に心が軽くなるのを感じた。