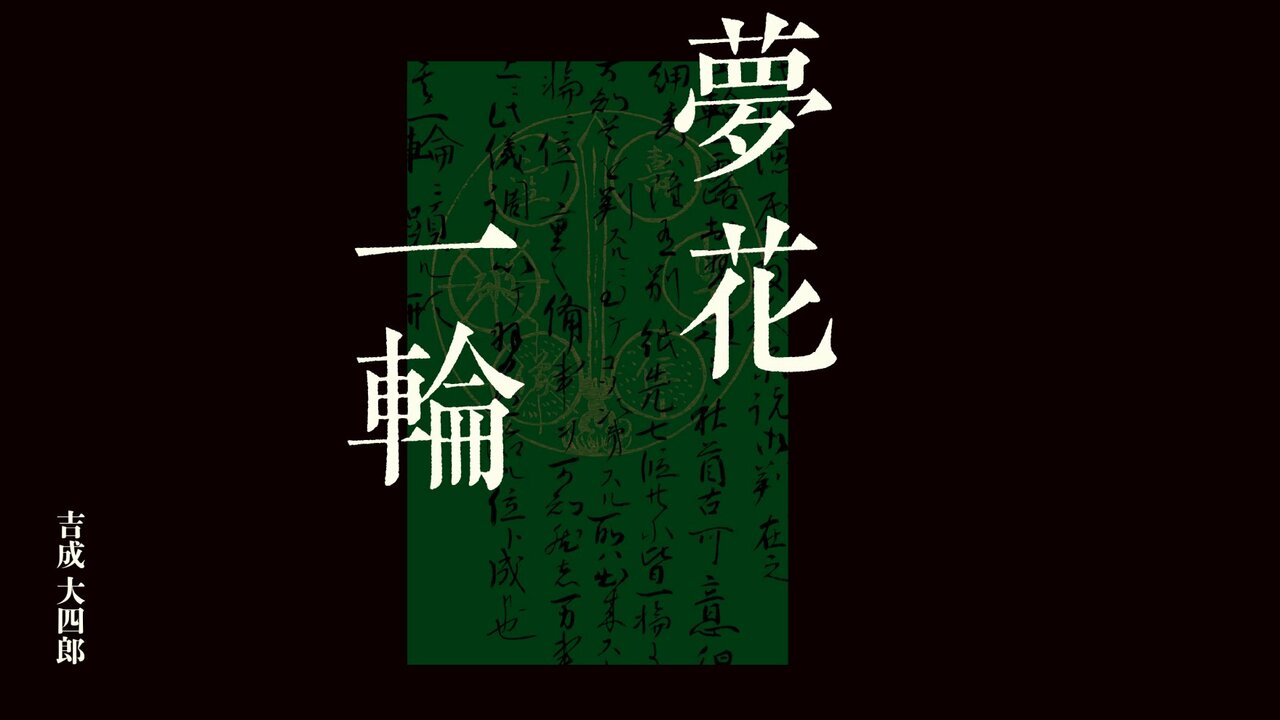五
あの頃が一番幸せだったのかもしれない。
十郎、七郎、あやめがそばにいて、ひたすらに能を学ぶ毎日。そこにはなんの迷いもなかった。しかしまた一方で、それは能そのものが大きな曲がり角を迎えているときでもあった。
大樹義満(よしみつ)が没したときのことを、弥三郎はかすかに覚えている。
応永(おうえい)十五年、弥三郎はやっと物心がついたばかりではあったけれども、世の中が大きく揺らぐような空気が漂っているのを子供心に感じていた。
それから新しい将軍の御代になって、まだ十年も経っていない。そもそも世阿弥が華やかな表舞台に立った始まりは、父観阿弥(かんあみ)とともに将軍義満の前で能を演じて見いだされたからだ。
今熊野(いまぐまの)で行われたそのときの能は、観世座だけではなく大和猿楽全体の、いや、能に携わるすべての者にとっての語り草となっている。
時に永和(えいわ)元年、足利(あしかが)義満は十八歳の若き将軍であり、観阿弥は四十歳を過ぎたばかりの心技ともに充実した盛り、そして世阿弥は花もほころぶような十二歳の少年で、その美しさに似ぬ鬼夜叉(おにやしゃ)という名を名乗っていた。
初めて見る能は、ただ一度で見事に義満を魅了した。観阿弥の円熟した芸と鬼夜叉の初々しさを愛した義満はその後も観世親子に愛顧を与え、観世座は確かな隆盛の基礎を築いたのであった。
義満のおかげを被ったのは観世座だけではない。弥三郎が属する金春の円満井座も余録に与(あずか)っているし、大和猿楽ですらない近江(おうみ)猿楽の犬王(いぬおう)もまた、義満の贔屓(ひいき)を受けて時めいた者の一人であった。
詳しい話は後に七郎から聞いたことではあるが、義満が最も愛した能の大夫は、観阿弥と犬王の二人だったようだ。犬王が義満の法名である道義から一字を戴いて道阿弥(どうあみ)と名乗ることを許されたのはその何よりの証拠である。
その犬王は観阿弥を出世の恩人として心から敬愛しており、観阿弥亡き後は終生供養を欠かさなかったという。近江の能はかかりを本とする、とは世阿弥からも直接聞いたことである。
筋立てや物まねにはあまりこだわらず、全体の雰囲気を大事にするのだ。犬王がことに得意とした天女の舞など、さらりさ、さらりさと飛鳥が風に従う如くに舞ったという。
その犬王も義満の死後数年のうちに空しくなった。そのとき、中空に香をたきこめたような紫色の雲がたなびいたというのは色をつけた噂に過ぎぬであろうが、それほどの名人であったということだ。
観阿弥は早くに世を去っていたため、義満を中心に華やいだ能の者たちはそれでひとしきり舞台から退いたこととなる。では、今こそ世阿弥が天下を取ったのではないかというと、ことはそう簡単ではない。
義満が没してようやく実権を手にした次の将軍義持(よしもち)が最も贔屓にしたのは、田楽新座(でんがくしんざ)の増阿弥(ぞうあみ)なのである。
そもそも、能は猿楽のみのものではない。田楽の座や、大和や近江その他の猿楽の座、あるいは呪師(しゅし)の座までが競い合ってそれぞれに工夫をこらし、新しい能を生み出しつつこれまでに至っているのだ。
この道の聖(ひじり)とまで言われ、観阿弥が我が風体(ふうてい)の師と仰いだ一忠(いっちゅう)は田楽本座(ほんざ)の大夫であった。
音曲(おんぎょく)の名人と言われた喜阿弥(きあみ)は増阿弥と同じ田楽新座の大夫であり、その喜阿弥が音曲の手本にしたのは近江猿楽の牛熊(うしくま)という脇(わき)の大夫であった、という具合だ。
このように混沌とした世界の中で、観阿弥と世阿弥の親子が二代で起こし、一頭抜きん出た存在となった観世の座であるが、それは絶対安泰な地位ではない。犬王亡き後、世阿弥の最大の好敵手が増阿弥なのだ。