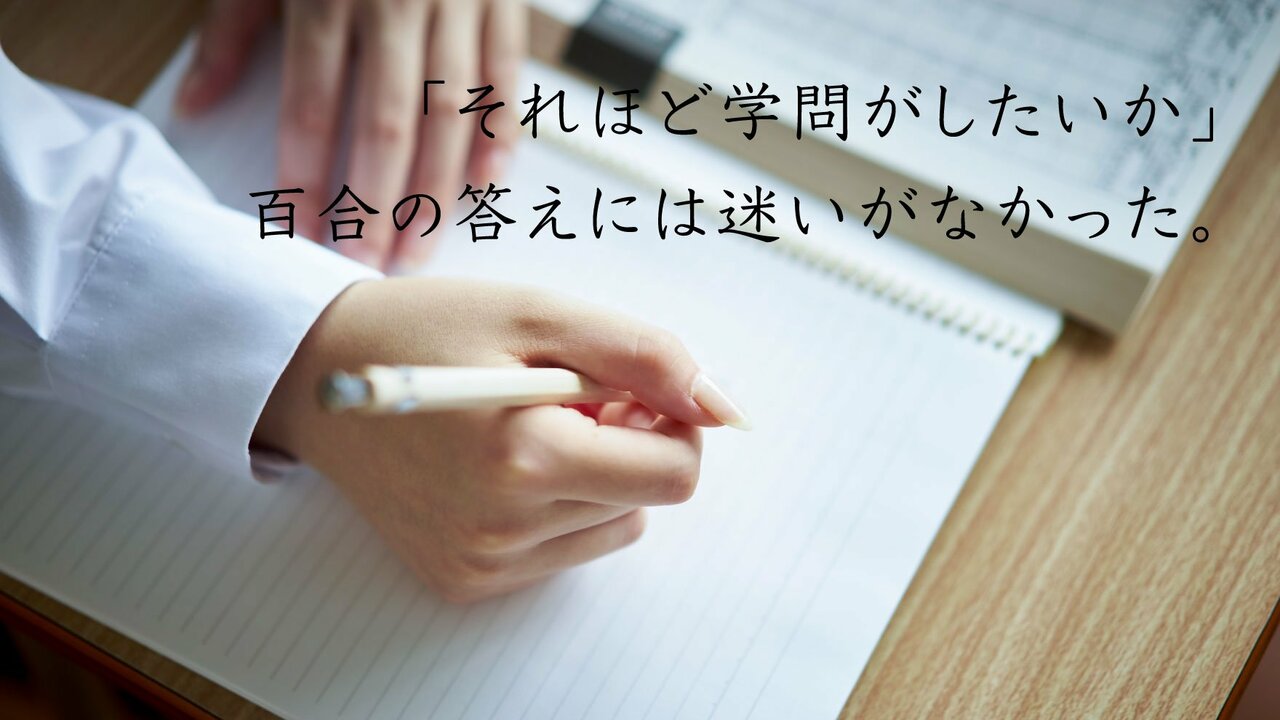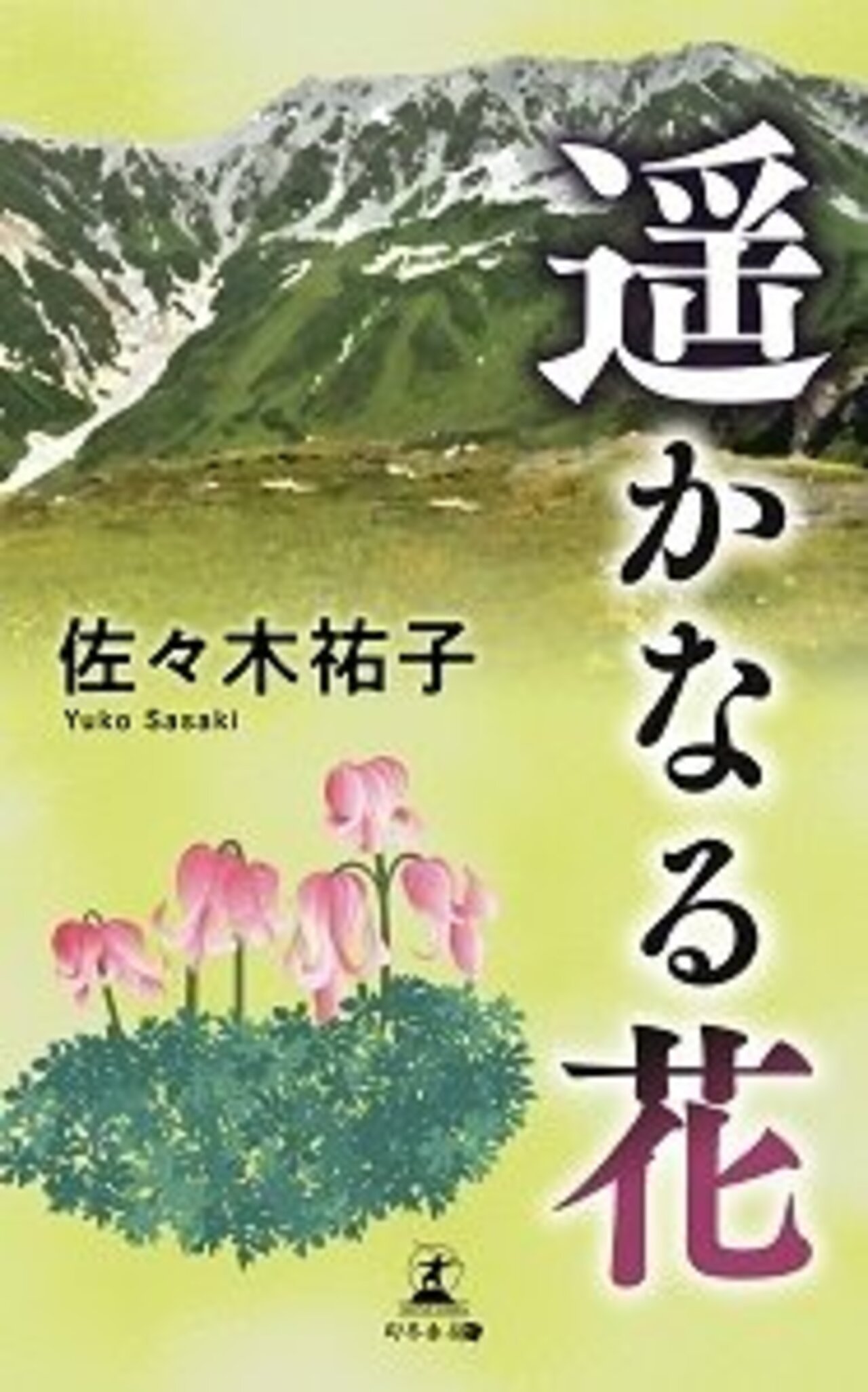地図

初夏
百合は全く屈託なくすぐに「はい」と返事して近付いて来た。聡順は自分のすぐ前を指さし、そこに百合を座らせた。
「さて百合、お前は幾つになった」
「はい、今年のお正月で十歳に相成りました」
「うむ、十というのがどういう年齢か分かるか」
百合はきょとんとしている。
「良く分かりませぬ」
「うむ、そうであろうな。よいか百合、十というのは大人になる準備を始める年ぞ」
「はい……」
「人として生まれたからには、いつまでも子供でいられるわけではない。大人になれば、仕事もせねばならぬ、女子であれば家の仕事などをおぼえ、嫁入りし子を産み育てる。男であれば、将来の仕事に向けて必要な学問をし、体を鍛え、やがて仕事をして家族を養う。それが武士であれ、職人であれ、商人であれ、農民であれ、皆同じことだ。そして百合、お前は女子故、そろそろ家の仕事など母を手伝い、縫物をおぼえ、料理を習う。嫁入りの準備のため、女子の着物を着ての所作も覚え、髪も結い、お茶やお花を習う。どうだ、出来そうか」
聞いているうちに、みるみる百合の顔が曇り、やがて俯いて黙ってしまった。まるで花がしおれてうなだれたような塩梅であった。
周りにいた家族も、急に静かになり、固唾を呑んで二人を見守っている。
百合の脳裏には、今年の正月のことが鮮明に思い出されていた。珍しく姉のおさがりの丈の長い美しい着物を着せてもらい、髪も上げて結ってもらったので、家中の者が一瞬誰だか分からないほど愛らしくなり、皆にやんやと褒めそやされて、最初はご機嫌であったのだが、年始のお祝いの膳が終わる頃には、もはや窮屈になってきて、兄が凧揚げなどに打ち興じ始めた時には、それに加われず大人しくしていることにほとほと嫌気がさしてしまったものだ。
それでその後すぐ母に泣きついて早々に脱がしてもらい、普段の様子に逆戻り。周りはあきれたが本人はやっとご機嫌になって、楽しく自分も凧揚げなど始めたのであった。百合はあの時の、まるで自分が別人になってしまったような窮屈さを体で覚えていて、それが一生続くのかと思うと、生まれて初めて生きていくことに疎ましさを感じた。
「黙っていては分からぬ、返事をしなさい」
「父上、今すぐそのように変わらなければいけないのですか」
「うむ、そうだ」
その返事には有無を言わせぬ強い響きがあった。