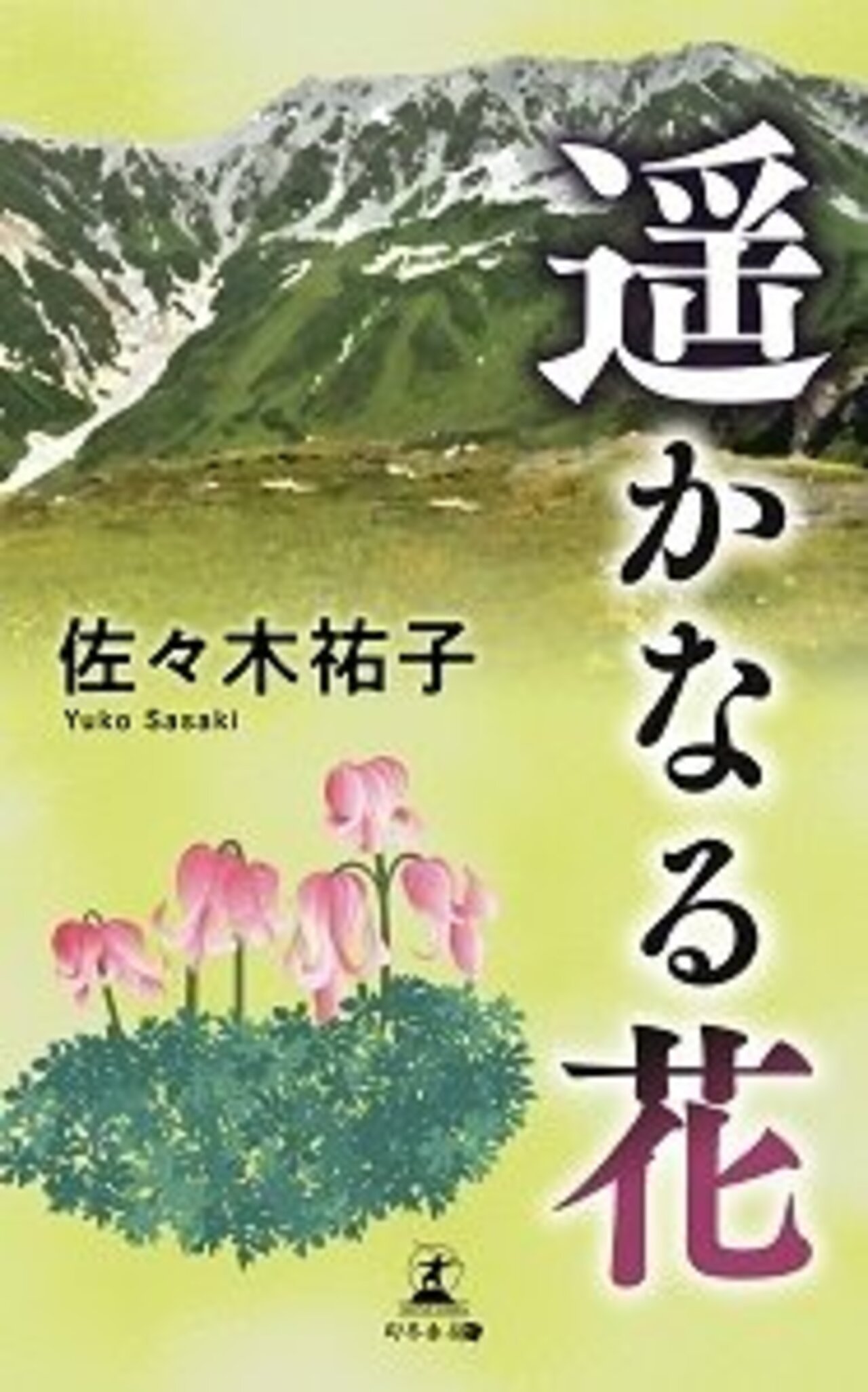ついに百合は俯いたまま、ぽたぽたと涙をこぼし始めた。百合は滅多に泣かない子故、これには誰もが驚いた。
その時、姉の綾菜が百合の傍らに来て百合を抱き、父に向かって言ったのだ。
「父上、もう少し待ってやって頂けませんか。百合はまだ幼い子です。そのようなことはもう少し遅くても良いのではありませんか」
「いや綾菜、だめだ。たとえ今でも、もう少し遅くても、百合の気持ちは変わるまい。同じことだ」
「それでも、それでは百合があまりにも可哀想です」
「だが綾菜、そなたが百合の年には、もう立派な女子であったのだぞ」
「父上、人は皆それぞれです。百合には百合の良い所が沢山ございます。お考え直し頂けませんか」
聡順は苦笑した。この前の深雪にしろ、今日の綾菜にしろ、なぜこう我が家の女共は百合をかばうのであろう。
「百合、どうしてもいやか。お前はれっきとした女子なのだぞ」
「父上、お許し下さい。私は女らしゅうなどなりとうございません」
聡順はそこでため息をついた。思った通りの展開が内心おかしくもあり、深雪の洞察力の深さに脱帽でもあった。
「では仕方がない。別の案を出そう。このまま好き勝手する子供のままで、いつまでもいさせるわけにはいかぬが、いっそ聡太朗のように男の子として育つのはどうだ」
百合は泣くのをやめてぽかんとしている。
「男の子として育つ……ですか」
「そうだ、家の仕事の代わりに、剣を習い、学問をし、家では本草学や医学を習う。医者になれるかどうかはともかく、いずれ聡太朗の手伝いなど出来るようになれば、また違った生き方も出来よう。今のままでは決して嫁のもらい手などない故、何か違う生きる道を模索せねばならんぞ」
それを聞いているうち、少しずつ百合の瞳に新しい希望の光が宿ってきた。
百合にとって、嫁入りするということは今のところさっぱり魅力を感じなかった。それより兄聡太朗のように、剣を習い学問をするということが、どれほど羨ましかったことか、父に今言われるまではっきり認識していたわけではないが、心の底に長い間くすぶっていた思いである。
「父上、百合は是非そのようにしとうございます」
「よいか百合、男の子として育つというのは、お前が考えているほど簡単なことではないのだぞ。剣の修業は体がきついし、学問をする時は、じっと座っていなくてはならない。所作にしても、礼儀をわきまえたきちんとした所作は女子のものより厳しいこともある。そういったことは、実際やってみねば分からないものだ。お前はそれを我慢出来るかな」
「兄上に出来るのですから、私にもきっと出来ると思います」
それを聞いて聡太朗はむっとしたような様子をした。
「お前はいつも少しもじっとしていられないではないか」
「それは、何も目的がなかったからです。学問をさせてもらえるのでしたら、百合は大抵のことは我慢出来ます」
「百合はそれほど学問がしたいか」
「はい」
答えには全く迷いがなかった。